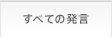サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 21:49:28
icon
創価学会・池田/大作氏に問う
31年前の「猛省」は世をあざむく虚言だったのか 不破 哲三
2001年7月22日(日)「しんぶん赤旗」
--------------------------------------------------------------------------------
◇私は、一瞬、目を疑った
◇一九七〇年の言論・出版問題の真相
◇「言論・出版の自由をまもれ」の声の国民的な広がり
◇池田/大作氏はなにを「猛省」したのか
◇三十一年前の「猛省」は世をあざむく虚言(うそ)だったのか
◇何をやっても自分は「仏」、批判者は「仏敵」
私は、一瞬、目を疑った
参院選のさなか、選挙戦を走りながらのことですが、公示直前七月十日付の「聖教新聞」を手にとって、私は、一瞬、目を疑いました。
この新聞では、池田/大作氏が、“法悟空”の名で、「随筆 新・人間革命」と題した文章を連載していますが、創価学会の愛知県組織の歴史をたたえたこの日の連載「戦う愛知の誉(ほま)れ」のなかに、一九六九〜七〇年の言論・出版妨害問題をとりあげた次の文章があったのです(括弧内は原文のフリガナから)。
「昭和四十五年の“言論問題”の前後より、学会は、数人の代議士からも罵倒され、ある時は、テレビを使い、雑誌を使い、演説会を使い、非難中傷された。あらゆる会合で、火をつけるように、悪口罵詈(あっくめり)を煽り立てられた。
なんという悪逆(あくぎゃく)か! なんという狂気じみた悪口か!
私自身も、愛知県の代議士から、国会喚問(かんもん)の要求を初めてされた。
『信教の自由』を侵害する狂暴な嵐であった。理不尽(りふじん)な罵倒(ばとう)の連続であった。
ともあれ、中部の同志は、血の涙を拭(ぬぐ)いながら、断固として仏敵(ぶってき)と戦う決意を、炎と燃やした。卑劣な強敵(ごうてき)と、真っ向から勇敢に戦った。
全会員が、極悪(ごくあく)の非難に対して、怒鳴(どな)り返し、堂々と反転攻撃の闘争を、連日、続け始めた。
人びとの幸福と平和を願い、基本的人権をもつ市民として、正義の信仰を流布(るふ)して、何が悪いのか!
信教の自由ではないか!
社会の改革に奔走(ほんそう)して、いったい、何が悪いのか!
憲法に保障された、最も正しい人権闘争ではないか!
勇気凛々(りんりん)たる中部の同志のスクラムは、敢然として、真っ向から、敵に火を吐く思いで戦い抜いた。
何人かの臆病者は、逃げた。敵についた者もいる。
しかし、今の大野和郎副会長を中心に、すべての真の同志は、未曾有(みぞう)の弾圧の嵐を堪(た)え忍んで、遂に赫々(かっかく)たる太陽の昇るが如き、勝利の中部の堅塁(けんるい)を護り、盤石(ばんじゃく)にしていった」
池田氏が、自分が統率する組織のどの地方をどう評価しようと、それは、私たちのかかわるべき問題ではありません。しかし、見過ごすわけにゆかないのは、池田氏が、この文章のなかで、一九六九〜七〇年の言論・出版妨害問題を、「仏」の側にたつ者(創価学会)の「仏敵」にたいする闘争、「悪逆」「狂気じみた悪口」、「理不尽な罵倒」、そして「未曾有の弾圧」に立ち向かって「正義の信仰」と「信教の自由」をまもりぬいた闘争として描きだしていることです。
私自身、ここで問題の火付け役として名指しされている「数人の代議士」の一人として、今回の池田発言について、それが歴史をいかに偽っているか、またこの歴史のつくりかえが、日本の社会と政治のうえでいかに重大な意味をもっているかを、述べたいと思います。
一九七〇年の言論・出版問題の真相
一九六九〜七〇年の言論・出版問題とは、評論家の藤原弘達氏が著作『創価学会を斬る』を日新報道という出版社から発行しようとした時、これを闇(やみ)に葬ろうとする創価学会・公明党の妨害にぶつかったことから、明るみに出たものでした。
私は、事件が明るみに出た直後の総選挙(一九六九年十二月)で初当選し、翌七〇年二月の予算委員会での初質問で、佐藤栄作首相を相手に、この問題にたいする政府・自民党の態度を追及しました(二月二十七日)。その時、藤原氏ら多くの関係者に直接あい、創価学会・公明党の言論・出版妨害の事実経過を確かめたうえで、その全貌(ぜんぼう)を示しました。
私が、国会で示した事実経過は、次の通りです。
(1)まず藤原氏の著書『創価学会を斬る』にたいしては、公明党の竹入委員長からの依頼で、自民党の田中角栄幹事長が、『創価学会を斬る』の出版を思いとどまるよう、また出版された場合には、その大部分を公明党に買い取らせるよう、藤原弘達氏にくりかえし申し入れてきました。藤原氏がそれを断って著書を出版すると、今度は、取次店に手をまわして取り扱いを断らせ、本が店頭に出ないようにしたのです。
(2)そのほかにも、本の取り次ぎ拒否などの手段で、事実上“闇に葬られた”本は、数多くありました。私が国会で取り上げただけでも、植村左内『これが創価学会だ』(しなの出版)、内藤国夫『公明党の素顔』(エール出版)、福島泰照『創価学会・公明党の解明』(展望社)などです。どの場合にも、公明党や創価学会との関係を理由に、取り次ぎを拒否されたのでした。
言論の自由、出版の自由を保障されているこの日本で、公明党・創価学会を批判する言論は公表を許さず、買収、取り次ぎ拒否、政権党への依頼、おどかしなど、あらゆる手段を使って、未然に封殺する、これは、基本的な人権を否定する民主主義への正面からの挑戦でした。こういう事態が、国民の知らないあいだに、言論・出版界では奥深くまた広く進行し、いわゆる“鶴タブー”(公明党・創価学会への批判を“タブー”とすること)がすでに、簡単にはくつがえし難いかに見える強固な既成事実となっていたのです。
「言論・出版の自由をまもれ」の声の国民的な広がり
ついに池田会長が「猛省」発言(一九七〇年五月)
しかし、この事実が明るみに出ると、日本社会の各界・各分野は実に敏感に反応し、“言論の自由をまもれ、出版の自由をまもれ”の声が沸き起こりました。
私たちは、十二月の総選挙のなかでも、この問題を重視し、国会でとりあげることを公約していましたが、一月に開かれた国会では、私たちだけでなく、社会党や民社党の議員からも、予算委員会で言論問題をとりあげる動きが出ました。
マスコミでも、この問題は広く取り上げられました。いわゆる三大紙の社説の題をあげただけでも、次の通りです。
「毎日」一月十八日「言論出版妨害事件について」。「朝日」二月三日「公明党は徹底的に体質を改めよ」。「読売」二月四日「公明党の抜本的体質改善を」。「毎日」二月五日「公明党の体質改善に望む」。「読売」二月二十六日「議員“脅迫”問題を究明せよ」。「朝日」三月十四日「出版妨害問題の究明を要求する」。「毎日」三月十六日「“言論・出版の自由”究明を」。「読売」三月十九日「出版妨害問題の真相究明を」。
この問題について発言し、言論の自由を守る意思を明らかにした知識人・文化人は、数知れません。そして少なからぬ人びとが、一九六九年十二月に、「言論・出版の自由にかんする懇談会」をつくり、問題の解決に大きな力を発揮しました。
この批判のなかで、公明党・創価学会の体質にかかわる問題として、「国立戒壇」の問題が大きな焦点として浮かび上がってきました。創価学会は、自分たちの信仰である日蓮正宗を国の宗教とすること(国教化)をめざしており、国会の議決により「国立戒壇」を建立することをもって、その手段だとしていました。公明政治連盟をつくり、さらにこれを公明党に発展させて、国会進出をはかったのも、大目標は「国立戒壇」の国会議決にあるとされてきました。公明党・創価学会が、他の宗教・宗派をすべて「邪宗」と呼んでその「撲滅」を公言してきたのも、おおもとでは、すべての日本国民を日蓮正宗の信者にするという「国教化」のこの目標と、結びついていたのです。
国会の内外での批判にたいして、公明党・創価学会は、出版妨害は「デマ」だといった調子の無法な反撃に出、とくに日本共産党にたいしては非難中傷の攻撃を集中しました。
しかし、民主主義をまもる国民的な世論と運動はいよいよ高まり、それに抗しきれなくなった創価学会は、ついに七〇年五月三日、池田会長が創価学会本部総会で「猛省」講演をおこない、国民世論の前で、事件への反省と今後の党および学会の体質改善の意思を表明するにいたりました。
池田/大作氏はなにを「猛省」したのか
では、池田/大作氏は、この会長講演のなかで、何を「猛省」したのか。要点を見てみましょう。
言論・出版問題について
池田氏は、言論妨害というような陰険な意図はなかったと言い訳しながらも、「これらの言動が全(すべ)て言論妨害と受け取られ、関係者の方々に圧力を感じさせ、世間にも迷惑をおかけしてしまった」ことについて、「まことに申しわけなく、残念」だ、「今後は、二度と、同じ轍を踏んではならぬと、猛省したい」と述べ、さらに関係者と国民への「おわび」の言葉をくりかえしました。
「私は、私の良心として、いかなる理由やいいぶんがあったにせよ、関係者をはじめ、国民の皆さんに多大のご迷惑をおかけしたことを率直におわび申し上げるものであります。もしできうれば、いつの日か関係者の方におわびしたい気持ちであります」
「国立戒壇」について
池田氏は、日蓮正宗と創価学会が「国立戒壇」を目標としてきたことは、事実として認めたうえで、「国立戒壇」というと、「国教化、一宗専制を目指し、他教を権力によって弾圧」するかのような誤解をあたえるので、「国立戒壇」という表現は将来ともに使わないこと、国会の議決を目標にしないことなどを、約束しました。
学会と公明党の関係
池田氏は、講演のなかで、創価学会と公明党の関係をとりあげ、「政教分離」は党の出発の時からの方針だった、これを実行することで、「今後、たとえ票が減ろうと、議員数が減ろうと」、それは「近代政党として当然の道」だと述べたうえで、具体的には、次のことを約束しました。
イ、創価学会と公明党の関係は、制度の上で明確に分離していくという原則を貫く。
ロ、創価学会は公明党の支持団体であるが、学会員個人個人の政党支持は自由とし、政党支持について、会員の自由意思には、全く干渉するものではない。
ハ、選挙は、公明党の党組織を思い切って確立し、選挙活動はあくまで党組織の仕事として、明確に立て分けて行う、創価学会は支持団体として「地域ごとの応援」をしてゆく。
(このあと開かれた公明党大会では、公明党の“独立性”と“政教分離”のあかしとして、宗教の政治支配を意味する「王仏冥合〈おうぶつみょうごう〉」の文言を削除する綱領改定など、一連の軌道修正をおこないました)。
共産党に対する態度
池田講演は、共産党との関係について、これまでの敵対関係は不当な攻撃にたいする防衛的な「反撃」だったと、事実をゆがめた弁明をおこなってはいますが、今後の問題としては、「かたくなな反共主義」はとらないことを強調しました。
「私としては、こうした泥仕合はできるかぎり避けたいというのが本意であります。我々は、かたくなな反共主義を掲げるものではない。また、そうあってはならない。……創価学会は、宗教の次元に立つものであります。……ゆえに、政党と同じ次元で争うものではありません」
三十一年前の「猛省」は世をあざむく虚言(うそ)だったのか
これが、公明党・創価学会による一九六九〜七〇年の言論・出版妨害問題の大まかな歴史です。
公明党・創価学会の側に「言論妨害と受け取られ」る誤りがあったことは、池田/大作氏自身がその講演のなかで明確に認め、その誤りにたいする「猛省」と「おわび」をくりかえすとともに、公明党・創価学会の体質改善にかかわる、いくつかの点での転換の公約を発表したものでした。そして、その「猛省」と転換が、その後の公明党・創価学会の活動の大前提となってきたはずでした。
ところが、池田/大作氏は、今回の“法悟空”名の文章のなかで、この事件にたいして、歴史をも自分自身の反省の言葉をもくつがえす、正反対の評価を宣言し、そこに自分の本音があったということを、あらためて告白したのです。
それは、
――言論問題とは、「仏」を守るものの「仏敵」にたいする闘争だった、
――言論・出版問題で公明党・創価学会に批判をくわえたものは、悪逆な「仏敵」、「卑劣な強敵」だった、
――創価学会が取り組んだのは、「信教の自由」をまもる戦いであり、「憲法に保障された、最も正しい人権闘争」だった、
というものです。これによれば、言論の自由をまもる立場から、国会でこの問題を取り上げた「数人の代議士」も、社説や放送でその体質に批判をくわえたマスコミも、良識と勇気をもって発言した知識人・文化人も、すべて「仏敵」だということになります。
それなら、私たちは、池田/大作氏に問わざるをえません。
三十一年前に池田氏がおこなった「猛省」の言葉の数々は、世をあざむくための虚言(うそ)だったのか、と。
そして、この告白が創価学会と公明党の本音だとすれば、この集団は、本音をおしかくした巨大な虚言によって、三十一年にわたって日本の国民と世論をもてあそんできた、ということになります。いったい、この集団は、日本の社会と国民そのものを、何と考えているのか、そのことがあらためて問われるではありませんか。
以前、池田/大作氏の側近であり、言論問題と「猛省」講演の時期にも、身近にいた原島嵩氏(一九七〇年・教学部長、『大白蓮華』編集兼発行人、副青年部長、一九八〇年に除名された)が、池田氏と当時かわした会話を、その著書のなかで、次のように記録していますが、私は今回の文章を読んで、原島氏の話がまさに池田氏のありのままの姿の記録であったであろうことを、あらためて痛感しました。
「言論問題の責任をとって、池田先生が『関係者の方々にお詫びに行きたい』などというのも、やはり建て前であったことはその後の歴史が明確に物語っています。事実、その当時、逆に、私にすごい形相で『タカシ!(私の名前) いいか! 必ず仇をうて、いつか、この本は何だ!と本人の前にたたきつけるのだ』と、それは恐ろしいけんまくで言うのでした。私は、『ハイ! 必ず先生の仇をうちます!』と返事をし、必ず先生を苦しめた人間たちを先生の前にひれふさせてみせるという誓いを心に決めたのです。
しかし、結局のところあの五月三日の発言は、一時撤退、ないしは迂回作戦にすぎなかったのです。報道関係者、文化人を多数呼び、公の席上発表したことも平気でホゴにしてしまうことが、はたして仏法の上でも、社会の上でも許されることなのでしょうか」(原島嵩『池田/大作先生への手紙――私の自己批判をこめて』一九八〇年)
何をやっても自分は「仏」、批判者は「仏敵」
この究極の独善主義に未来はない
池田/大作氏の告白の重大性は、それだけにとどまるものではありません。この告白によると、あの会長講演のなかで、池田氏が国民の前でおこなった公約も、すべて心にもないことだった、ということになります。実際、“選挙は公明党を中心に”という公約も、“かたくなな反共主義は掲げない”という公約もすでに完全に投げすてられて、実際の活動の上ではそのかけらも残っていません。
会長講演では、創価学会は「宗教の次元」に立つものだから、「政党と同じ次元で争うべきではありません」とされましたが、いまでは、「聖教新聞」が「公明新聞」以上の反共デマ宣伝製造元になっている事実が示すように、創価学会主導の反共作戦が全国で展開されています。夜陰に身をかくしての卑劣な謀略ビラの配布でも、創価学会の会員たちがこの暗闇部隊の主力となっていることは、かくれもない事実です。
なかでも、私がとりわけ重要だと思うことは、“自分たちは、どんな無法なことをやってもいつも「仏」、それを批判するものはすべて「仏敵」だ”という究極の独善主義――以前、「邪宗撲滅」を前面に押し出していた時期にむきだしの形で現れ、社会的な批判の的となった独善主義が、この文章のなかに、まるごと復活していることです。自分たちへの批判をおさえこもうとした言論・出版妨害の行為の是非を、社会的道義の立場から吟味しようという理性は、ここにはまったくありません。創価学会・公明党がやった行為が何であれ、それに批判をくわえるものは、撲滅すべき「仏敵」であり、この「仏敵」にたいする戦いでは、どんな手段も許されるのです。
この数年来、選挙戦における公明党・創価学会の活動が、極端な反共主義の点でも、活動の謀略性の点でも、きわめて異常なものとなっていることが、各方面から注目されてきました。それが、社会的道義にも市民道徳・政治道徳にも背をむけた「仏敵」撲滅論に裏うちされたものだったとなると、全国各地で現れている多くの異常な事態の背景がよく分かります。
池田氏は、参院選を前にして、なぜ、いま、「仏敵」撲滅論をあらためて宣言してみせたのか。
池田氏が、今回の“法悟空”名の文章で、三十一年前の自身の「猛省」講演を正面から否定し、その独善主義をあからさまに宣言してみせた背景には、公明党の政権参加によって「ついに権力についた」者のおごりが浮かび上がってみえます。この文章の大見出しに、「広布の堅塁 卑劣な権力に勝てり!」と、ことさらに「権力」の問題をひけらかしているところにも、その思いはおのずからあらわれているようです。
しかし、自分たちを批判するものにすべて「仏敵」のレッテルを張り、手段を選ばずその「撲滅」をはかるという組織は、現代の民主主義のもとでは、政治の世界でも、宗教の世界でも、存在の資格を疑われても仕方のないものです。この究極の独善主義には、未来はありません。とりわけ、このような集団が、政権に参加していることの是非は、宗教政党の政権参加が憲法上許されるかどうかという一般的な角度の問題ではなく、この異常で特殊な集団の政権参加の是非の問題として、社会的な批判と吟味にさらされる時期が必ずやってくるでしょう。
最後に、“法悟空”の文章が、創価学会・公明党およびこれと連合するものの陣営に、新しい矛盾を激発する深刻なページを開いたことを指摘しておきたい、と思います。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 20:15:50
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
『五人所破抄見聞』の著者についての小林の邪論を破す 法義研鑽委員 高 橋 粛 道
小林は『五人所破抄見聞』の著者について、
「『五人所破抄見聞』は、妙蓮寺三世(ママ)日眼説に立てば、宗祖滅後約百年ごろ、大石寺では六世日時上人存命中の著作ということになる。しかし、『五人所破抄見聞』には明らかに文明二(一四七〇)年以降でなければ書けない記述があり、妙蓮寺日眼説に大きな疑問が投げかけられている。むしろ同名の西山八世日眼(十五世紀後半)の著作とした方が落ちつきがよい」(東学研一一五頁)
と述べている。小林の邪論は小林自身が記するように、身延派である宮崎英修氏の『棲神』四一号を依拠としている。
まず、宮崎氏の説を紹介すると、
「本論の五人所破抄見聞の真偽についてのべよう。本書は日蓮宗宗学全書興尊集、富士宗学要集等に載せられているが、本書の著者日眼は南条時光の子と伝え、下条妙蓮寺三世(ママ)となって住し至徳元年(一三八四)二月二十二日入寂という。世寿は不詳、著書はこの見聞のみである。この見聞には冒頭の題号の下に『釈日眼述』とあり、奥書に『伝写本云康暦二庚申年六月四日書畢。本化末弟日眼判』と記している。一般にこのような年記の書き方は直ちに時代的通格の批判対照になる。このように年号、年数、干支、年月日という書方は戦国時代の末ごろから稀に見られ始め、江戸期に入って間もなく一般的になるものであって鎌倉時代、室町時代の通格は康暦二年庚申六月四日と記し決して康暦二庚申年六月四日とは書かない(中略)武家伝奏は正長元年(一四二八)にはじめて設けられている(中略)さて、五人所破抄見聞には、前述の如く『総ジテ公家ノ伝奏卜云テ当御代ハ勧修寺殿、広橋ナド伝奏衆ヲイフ也』とある。武家伝奏が設けられたのは正長元年(一四二八)で所破抄見聞が著わされたと伝える康暦二年(一三八〇)より四十八年ものちのことであり、而もそれは日野(号裏松)、万里小路、勧修寺の三家で、これは短期間であったようである。勧修寺、広橋二家が任ぜられるのはこの時より四十二年も後、文明二年(一四七〇)以降で、それも九年間その後は二家が共に任ぜられるのは、まだまだ後のことである。所破抄見聞の記事によれば、勧修寺、広橋の両伝奏はあたかも世間一般周知の役柄のように記されている。このような表現をするのは室町末期の永正年間(一五〇〇ごろ)以降のことでこうした伝奏衆が百四、五十年前に存するはずはない。当然、本書は勧修寺、広橋両伝奏の存在が周知のこととなった時代の産物といわねばならぬ。そしてもしかりに、所破抄見聞が勧修寺、広橋両家が始めてつとめた時代・文明初年に著わされたとしても、康暦二年より九十年ものちの事でなければならない。以上、年記の識語、伝奏の設置時期及び人名の点から考えると、本書を妙蓮寺日眼の著とすることはできない(中略)本書は如何に早くとも文明二年以降でなければ作られないものである」(棲神四一号一五九頁)
このように宮崎氏は、一、年号の識語。二、伝奏の設置時期。三、人名の三点から偽書としている。
以下、順次破折して『五人所破抄見聞』が妙蓮寺日眼の著作であることを論証する。
一、 年号の識語
1、「康暦二庚申年」のように年数と年月日の間に干支が入るのは戦国時代の末ごろから稀に見られ始め、江戸期に入って間もなく一般的になる。
2、「康暦二年庚申」のように干支が年数のあとにくるのは鎌倉・室町時代の通格である。
これが宮崎氏の主張である。これに当てはまらなければ偽書の疑いがあるというのである。
1、に関して、戦国時代の通格が鎌倉時代に見られるもの。
『富士宗学要集』八巻に秋山家の書状がある。それには、
「ぶんはみづのとみのとし二年正月廿二日」
(文 和 癸 巳 歳 二年正月廿二日)(同書一二三頁)
とあり、もう一つは、
「文和みづのとのみのとし二年三月五日」
(文和 癸 巳 歳 二年三月五日)(同一二六頁)
とある。前者は泰継の孫の状、後者は泰忠の状で、二本とも秋山家に所蔵されている正本である。
また、同じ年月日に秋山泰忠が認(したた)めた書状には、
「文和二年みづのとのみのとし三月五日」
(文和二年 癸 巳 歳 三月五日)(同一二七頁)
と書かれたものがあるが、同一人が同じ日に書いたものにもこのような差異が見られるのであり、宮崎氏の如く年号の書式が通格と相違するから直ちに偽書と断ずるのは早計であろう。年号の書式が通格と異なる場合、一往確かめる必要はあろうが、その確認作業はどこまでも謙虚にして慎重でなければならない。宮崎氏のように思い込みと独断で真偽を決定づける方法は学問的とは言えない。
このほか他門流にも『五人所破抄見聞』の奥書と同形式のものがある。それは『日成譲状』と呼ばれるもので、
「徳治二丁末未年三月二十八日 法印日昭在判」(日蓮宗宗学全書一巻一一頁)
とある。これについては古来、特に偽書説はないようである。徳治二年(一三〇七)は鎌倉時代である。このように数こそ少ないが年号と干支の書き方は一様ではなく、宮崎氏のようにすべてを通格で押し切ってしまう論議は乱暴と言うほかはない。
2、に関して、
「天文十五年丙午正月廿三日之を述ぶ日我敬白」(富要一巻三二五頁)
「永禄十年丁卯十月十三日 六十才 日我在り判」(同八巻八九頁)
「于時天正六年戊寅二月時正書写之畢 本乗寺善行坊日膳阿闍梨」(同四巻一三五頁)
「天正四年丙子八月十三日 勝資在り判」(同八巻一一五頁)
等があるが、前三書は保田文書、最後は公文書である。保田では書式の通格にとらわれていないようであり、一通は公の文書でありながら、これも規格どおりでない。宮崎氏からすればあってはならない書式であるが、実際には存在するのであり、学問は現実の証拠を重視するところから始まるのであるから、宮崎氏には大きい視野に立って公平に判断することを強く望みたい。
二、伝奏の設置時期
宮崎氏が『棲神』四一号に投稿したのは昭和四十三年で、今から二十七年も前のことであり、今日では日本の歴史、ことに伝奏に関しても研究が進んでいる。宮崎氏は武家伝奏は正長元年に始めて設置されたと言うが、今はこの説は通らない。公武関係は関東申次から武家執奏(文和二年〔一三五三〕の実俊に始まる)を経て武家伝奏(江戸期には単に伝奏とも言うようになった)に変わるが、武家伝奏は康暦から永徳年間(一三七九〜八三)ころには始まっている。『見聞』は康暦二年の成立なので同時代ころである。
ところで、宮崎氏は勧修寺、広橋両家の伝奏が周知の役柄のように『見聞』に記されているから、『見聞』はどう見ても康暦二年より九十年後の成立であると、武家伝奏の始まりから逆算して述べている。だが、ここに誤りがある。一には両家の伝奏は康暦二年以前からであったこと。二には『見聞』には公家伝奏とは言っても武家伝奏は述べていないことである。述べていないことを述べてあるように考えても意味をなさない。
まず、『見聞』には、
「総じて公家伝奏と云って当御代は勧修寺殿広橋殿など伝奏衆と云ふ也、武家へは訴訟と云ふ」(同一巻一一頁)
とある。ここに「武家へは訴訟と云ふ」とあり、けっして武家伝奏と記していない。周知の役柄なら武家伝奏と記していいはずなのに、日眼が「訴訟」と述べたのは、いまだ周知の役柄でなかったのではなかろうか。武家伝奏は義満時代からは重要な柱となったことは事実であるが、それが世間に広く知られる前であったので、日眼は「訴訟」と記したと考えるのである。
また、日眼は「公家伝奏」と記しているが、「公家への伝奏」、あるいは「公家による伝奏」という意味に解される。『見聞』にはこのあと、「当御代は勧修寺殿広橋殿など」と続くので、両家の公家による伝奏と解したほうがよいかも知れない。いずれにしても、かつて日目上人が国家諫暁され、天皇から『園城寺申状』の御下文を戴いたことに関連しての記述であることを知っておく必要がある。
次に、宮崎氏は武家伝奏の始源を求めて、そこから『見聞』にあるべきはずのないものが記述されているから後人の仮託だと主張したが、勧修寺、広橋両家は康暦二年以前に伝奏に任じられている。
勧修寺経顕(一二九八〜一三七三)は『大日本史料』の応安六年(一三七三)正月六日の項を見ると伝奏であったことが判る。また、『小槻匡遠記』建武二年(一三三五)六月十三日条に「伝奏大弐」(大弐とは経顕のこと)とある。
広橋兼綱(一三〇二〜一三六六)は貞治六年(一三六七)の時点で伝奏であったことが確認されている。『見聞』より十三年も前である。
兼綱の子である広橋仲光(一三四一〜一四〇五)は『東寺文書』(永和二年〈一三七六〉)三月八日に「伝奏広橋仲光奉書」とある。さらに『迎陽記』康暦二年五月二十六日・八月六日条からも伝奏であったことが知られる。
このように『見聞』以前から勧修寺、広橋両家は伝奏の任を奉じていたからこそ日眼が記述できたのである。国諫に情熱を込めていたから伝奏衆には敏感で、いち早い情報が入ったのであろう。なお、広橋家の系図は左の如くである。
三、著 者 名
『見聞』の奥書には、
「伝写本云 康暦二庚申年六月四日書畢 本化末弟日眼在御判」(同二六頁)
とある。宮崎氏は『富士戒壇論について』のなかで、
「このころ存命の富士門家の日眼といえば西山本門寺八世日眼のみで、百余年前に没した妙蓮寺日眼は年代不相応、別人である」(仏教の歴史と文化六五二頁)
と言い、『見聞』の著者を西山日眼と推定している。『見聞』には二箇相承が記されているので氏としては時代を下げたいようであるが、『見聞』の記述内容から妙蓮寺日眼なのか、西山日眼なのか、その作者を検討してみたい。
西山本門寺八世日眼は文明十八年(一四八六)、祖滅二〇〇年ごろに寂している。この日眼は日有上人と同時代で左京日教より少し前の人である。既に祖滅二〇〇年ともなれば富士五山はそれぞれ門流意識が形成されており、日代の流れを汲む日眼としても少しはその主張が見られるはずであるが、それがない。『見聞』には仙代問答の記述があるが、そこには河合の義、日仙の義、上野の義、重須の義、日代の義を列挙し、
「何(いずれ)も大事也」(富要一巻二五頁)
と中立を保って日代びいきをしていない。これは、宗門上古のことでなければならず、祖滅二〇〇年まで下がらない。
また、西山門流は宗祖―日興上人―日代―日任と次第して日目上人を除外する教団であるが、日目上人の四十二度の天奏や御下文を挙げ、
「広宣流布は必ず当門徒に在る可き也」(同四巻一一頁)
と言うのも変である。当門徒とは石山を含む妙蓮寺を指すと考えるのが妥当であろう。それは、妙蓮寺日眼が大石寺開基檀那南条時光の子息・乙次丸だからである。如上のことから西山日眼は、「広宣流布は必ず当門徒に在る可き也」とは、表現できないはずである。
また、『見聞』に、
「日朗は大聖御入滅已後二十九年目に日興上人へ御同心有」(同一巻一〇頁)
と、日朗の富士帰伏を具体的な数字をもって記せるのは妙蓮寺日眼がふさわしい。それは、日興門流の正統意識が裏打ちされているからである。『見聞』に、
「一瓶の法水を日興に御付属あり、日興も寂を示し玉ひ次第に譲り玉ひて当時末代の法主の処に帰り集る処の法花経なれば法頭にて在す也」(同九頁)
と、宗祖からの付嘱、そして歴代上人への相譲(相承)が記されている。相承はあまり他派では言われず、これは大石寺の血脈相承のことと思われる。石山と姻戚関係とも言える妙蓮寺の住侶にして言える表現であると考えるのである。
このほかに本仏論、本因妙思想、文底などが記されているが、上代での成立であることを窺(うかが)わせ、西山日眼まで下がらない。故に『見聞』の奥書に示す如く、康暦二年に妙蓮寺日眼によって著されたと信じるのである。
広橋家icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 20:08:12
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
日有上人文書に対する小林の疑難を破す
法義研鑽委員 影 山 広 道
《は じ め に》
日蓮正宗中興の二祖として、総本山第二十六世日寛上人と共に仰がれているのが、第九世日有上人である。日有上人の御指南は、弟子の南条日住師が筆録した『化儀抄』やその他の聞書(ききがき)等によって現在に伝えられており、その御高徳を拝することができる。
ところが小林正博は、『化儀抄』等が聞書であることをよいことにして、日有上人の御正意を曲げてしまおうと企むのである。よって今回は、小林正博の日有上人文書に対する疑難を破折することにした。
一、日有上人文書に対する疑難について
『化儀抄』第四条には、
「手続(てつぎ)の師匠の所は三世の諸仏高祖已来代々上人のもぬけられたる故に師匠の所を能ク々取り定メて信を取るべし、又我カ弟子も此クの如く我レに信を取るべし、此ノ時は何レも妙法蓮花経の色心にして全く一仏なり、是レを即身成仏と云ふなり云云」(富要一巻六一頁・傍線部分が小林の引用箇所)
とあり、同抄第十四条には、
「信者門徒より来る一切の酒をば当住持始めらるべし、只シ月見二度花見等計り児(ちご)の始めらるゝなり、其ノ故は三世の諸仏高祖開山も当住持の所にもぬけられる所なるが故に、事に仏法の志を高祖開山日目上人の受け給ふ姿なり」(同六二頁・傍線部分が小林の引用箇所)
とある。「もぬける」とは、蝉、蝶などが脱皮をしてその身を新たにすることであり、そのように三世の諸仏はもとより御本仏日蓮大聖人、御開山日興上人以来の御法主上人のお心が抜けられて、当代の御法主上人のところに来ているのであるから、仏法のすべては当代の御法主上人のところに存するの意である。また、広く言えば御法主上人に信伏随従する末寺住職のところにも、一切を御所持の御法主上人のお心が抜けてこられるという意でもある。
このように第四条は、本宗の唯授一人血脈相承とそれに基づく師弟相対の筋目を、総別の二義の上から御教示なされた条文であり、第十四条は、本宗の唯授一人血脈相承の意義を御教示なされた条文である。
しかし小林は、このなかの傍線部分を引用して、
「日有上人には次のような『法主絶対』的表現が見られるのである」(東学研一二二頁)
と述べて、これが「法主絶対的表現」であると言う。そして、このような日有上人文書の表現が、
「日有文書を読む場合、注意すべき視点がいくつかある。一つは、日有文書のすべてが後代の者の聞き書きによるということである(中略)その他の聞き書きも、そのまま日有上人が言ったものとしていいかどうか慎重に考える必要があろう」(同頁)
と、実際の日有上人の御指南ではないのではないか、と疑うのである。
小林は、このなかで、「日有文書のすべてが後代の者の聞き書きによるということである」と述べているが、この表現には二つの問題点がある。一つは「すべてが聞き書き」であるのか、ということ。二つには「すべてが後代の者」によるのか、という点である。
(1) 日有上人文書の分類
日有上人には、次のような直筆の御消息が現存している。
大石寺所蔵の『御歴代忌日表』(寛正二年十月二十九日の書)・『大仙坊御返事』・『くすし御消息』、宮城県築館町・妙円寺所蔵の『壹岐殿御返事』、静岡県沼津市・本広寺所蔵の『きようとの御消息』等である。また、日有上人の申状は、総本山第十九世日舜上人の写本によって伝えられている。さらに、『化儀抄』等の聞書が数本存在する。このように、日有上人文書は、
イ、直筆
ロ、写本
ハ、聞書
の三種類に分類されるのである。
小林は、「日有文書のすべてが後代の者の聞き書きによるということである」と言うが、いったいどんな研究をすれば、このようないい加減な見解が出てくるのであろうか。
(2) 後代の者の聞書
もう一つの 「すべてが後代の者」によるのかという点であるが、そもそも聞書とは、本人の講義なり話を直接聞いた者がその内答を筆録するから「聞き書き」というのである。
「後代」とは、『広辞苑』に、
「後の世。後世」
とあり、『新明解国語辞典』には、
「ある時代を基準にして、それより後の時代」
とある。したがって、小林のように「後代の者の聞き書き」といえば、日有上人御遷化後に成立した文献を意味することになる。しかし、『有師談諸聞書』には、
「右ノ此ノ書は坂東下野国金井法華堂住侶下野阿闍梨・一夏中・冨士大石寺に住山申し日有の御法門を聴聞申し書く時なり。文明四年夏中の聞書・弁阿闍梨日達」(富要二巻一五八頁)
「長禄二年初春の比(ころ)・筑前阿闍梨日格・登山の時・日有に尋ね申す法門なり秘事なり」(同頁)
「四国土佐の吉奈(よしな)連陽房の日有より聞書。文明八年五月廿三日 大円日顕之を相伝す」(同一四八頁)
と記されている。これらを年代順に列記すると次のようになる。
応永二十六年(一四一九)日有上人御登座
長禄二年(一四五八)筑前阿闍梨日格師の聞書
文明四年(一四七二)下野阿闍梨の聞書
文明八年(一四七六)連陽房聞書
文明十四年(一四八二)日有上人御遷化
文明十五年(一四八三)化儀抄浄書
※『有師談諸聞書』とは、筑前阿闍梨日格師の聞書、下野阿闍梨の聞書、連陽房聞書の三書のことを指す。
このように、筑前阿闍梨日格師、下野阿闍梨、連陽房の三師の聞書が、日有上人の御在世中のものである。「後代」ではなく「同代」の人物による、「同代」の文献であることは明白ではないか。
二、『化儀抄』の筆録者について
小林は『化儀抄』の第四条、第十四条を挙げて、「法主絶対」の文証としている。そして、
「『化儀抄』は南条日住と日教によって編されたものであり、そこに法主絶対論者の日教の恣意(しい)的表現が付加されていることも可能性としてないとはいえない」(東学研一二二頁)
と、『化儀抄』に対して、日有上人以外の人物の恣意的表現が付加されている可能性があるとする。
その理由として、まず最初に、
「日教が『化儀抄』の編纂に携わったことは堀日亨上人も認めているところである」(同頁)
と言う。日亨上人が仰せられた証拠として、小林が提示したのは、『富士宗学要集』の解説十五(日亨上人よりの大橋慈譲師の聞書)の、
「堀日亨上人のおおせにいわく、『この文は、化儀抄の引用である。下に、化儀抄に云くとあるが、南条日住の化儀抄の蒐集(しゅうしゅう)に左京日教も参加し、左京日教は、ここに化儀抄というのは、当然と思う』」(大白蓮華一〇七号八〇頁)
との記述である。
これだけの材料で、「『化儀抄』は南条日住と日教によって編されたものであり、そこに法主絶対論者の日教の恣意的表現が付加されていることも可能性としてないとはいえない」と推測するのである。
しかし、『富士宗学要集』の解説十五(日亨上人よりの大橋慈譲師の聞書)の記述から確認できることは、
〝日亨上人は、南条日住師の『化儀抄』の蒐集に左京日教師も参加したと推測されたことがあったらしく、それを大橋慈譲師に話されたことがあったようだ〟
ということである。これだけで、「『化儀抄』は南条日住と日教によって編されたものであり、そこに法主絶対論者の日教の恣意的表現が付加されていることも可能性としてないとはいえない」とまで言うことは、あまりにも乱暴であり、あくまで小林の邪推であると言えよう。
まして、日亨上人までが『化儀抄』に南条日住師や左京日教師の恣意的表現が付加されたと考えられていた、かのように受け止めるとしたならば大変な誤りである。
もし左京日教師が『化儀抄』蒐集に参加していたならば、日亨上人の左京日教師に対する絶大な評価からして、日亨上人は左京日教師の『化儀抄』蒐集への参加によって日有上人の御指南が、より忠実かつ正確なものになったと考えられた、と拝するべきである。
『化儀抄』蒐集は南条日住師の畢生(ひっせい)の浄業であり、左京日教師は補佐的な立場にあったと考えるのが穏当であろう。帰伏まもない左京日教師が、日有上人門下の重鎮の南条日住師の信頼を得て『化儀抄』蒐集に参加したならば、なおさら恣意的な文言など差し挟むはずがないではないか。
むしろ、小林自身が論文中に示した左京日教師の略年譜に、
「文明十二年(一四八〇)このころ日有上人に師事」(東学研一二三頁)
とあるように、このころから左京日教師は日有上人を師匠として薫陶を受け、おそらく『化儀抄』の蒐集を補佐したことにより、より深く大石寺の教義を信解したのであろう。
さらに言えば、『化儀抄』の奥書には、
「仰せに曰く二人とは然るべからざる由に候、此の上意の趣を守り行住坐臥に拝見有るべき候、朝夕日有上人に対談と信力候わば冥慮爾るべく候なり」(『化儀抄』略解一一五頁)
とある。この文を日達上人は、
「日有上人の仰せによれば、一人(日鎮上人)にかぎり申し伝えてよろしいとのことであります。前述の各条を日常に拝見して守っていただきたい。そうすれば、毎日、日有上人とお話しをしあっていると同じであります。そこに、はかり知れない仏様のお心持があると思います」(同頁)
と解説されている。また、日達上人は『化儀抄』について、
「南条日住という人が常々お聞きしたことを、書き留められたのを、日有上人の御入滅(文明十四年・一四八二年)の翌年、文明十五年、これを浄書して、本山第十二代日鎮上人に御渡した書物である」(同二一頁)
とも述べられている。このように、『化儀抄』とは日鎮上人に伝えるために、南条日住師が常々日有上人よりお聞きしたことを書きとどめられたものであり、しかも、その内容は日有上人御自身が認可された上で日鎮上人に申し伝えてよろしいと仰せられたものである。
日亨上人も、
「編者曰く本山蔵南条日住の正本に依って此を写す(乃至)本抄は有師の弟子南条日住が其平素の御談を集記したるものにして云云」(富要一巻七九頁)
と述べられ、また、
「総本山九世日有上人の化儀等の訓辞を日住が集録したるもの、已来宗門教儀の金科玉条と崇敬せられ云云」(同八一頁)
とも述べられて、南条日住師が集記し収録したと仰せられている。これらのことから見ても、小林の言う、「『化儀抄』は南条日住と日教によって編されたものであり、そこに法主絶対論者の日教の恣意的表現が付加されていることも可能性としてないとはいえない」との見解は明らかな誤りである。日亨上人や日達上人の御指南のとおり、南条日住師によって日有上人の言葉がそのまままとめられたものそれが『化儀抄』なのである。
要するに小林は、「可能性としてないとはいえない」だけで『化儀抄』を疑おうとしているのである。「可能性としてないとはいえない」と論じただけで研究論文として通用するなら苦労はしない。いくらなんでも研究員の肩書きが恥ずかしくないか。
小林の疑難は、論難と言うに値(あたい)しない、たわごとと言うべきである。
三、『有師談諸聞書』の文について
小林は『有師談諸聞書』の文について、
「師弟について日有上人は『上行菩薩の御後身・日蓮大士は九界の頂上たる本果の仏界と顕れ、無辺行菩薩の再誕・日興は本因妙の九界と顕れ畢りぬ、然れば本果妙の日蓮は経巻を持ちたまへば本因妙の日興は手を合わせ拝したまふ事師弟相対して受持斯経の化儀・信心の処を表したまふなり、十界事広しと云へども日蓮日興の師弟を以て結帰するなり』(富要二巻一六〇)
というように師弟関係の究極を宗開両祖にみており、この文の立場に立てば、日蓮日興という師弟間の相承に信をおくことが根本ととらえている。そういう意味では歴代法主の立場を『唯受一人血脈相承』で位置づける宗学の流れを受けてはいないのである」(東学研一二二頁・傍線筆者)
と述べている。つまり歴代の御法主上人の立場を「唯授一人血脈相承」で位置づけるのが宗学の流れであり、『化儀抄』はその流れに沿っている。しかし、『有師談諸聞書』の文は『化儀抄』とは異なり、「唯授一人血脈相承」で位置づける宗学の流れを受けていないと主張しているのである。
「歴代の御法主上人の立場を『唯授一人血脈相承』で位置づけるのが宗学の流れ」というのは正論である。小林は日蓮正宗が正しいことを知っているのである。正しい教学も知っているのである。知っていながら、曲げて書いているのである。哀れな人である。
ここでは、『有師談諸聞書』の文を『化儀抄』の文と対比させる形をとって、日有上人の文書には、同じ日有上人の書といいながら、このように宗学的に相矛盾する内容が記されているとして、日有上人文書は信用できないもののように印象づける。そして、
「『化儀抄』は南条日住と日教によって編されたものであり、そこに法主絶対論者の日教の恣意的表現が付加されていることも可能性としてないとはいえない。日教が『化儀抄』の編纂に携わったことは堀日亨上人も認めているところである(要解⑮)。その他の聞き書きも、そのまま日有上人が言ったものとしていいかどうか慎重に考える必要があろう」(同頁)
と言うのである。しかし、『有師談諸聞書』の文と『化儀抄』の文とは矛盾しないのであって、小林の言うことは的外れなのである。
小林は、前掲の『有師談諸聞書』の御文、特に「日蓮日興の師弟を以て結帰するなり」の文を中心に解釈して、日有上人は、「師弟関係の究極を宗開両祖にみており、この文の立場に立てば、日蓮日興という師弟間の相承に信をおくことが根本ととらえている」としている。
しかし、これでは日有上人の御意に著しく反するのである。確かに宗開両祖は根本であるが、歴代上人によってその法脈が継承伝持されなければ、今日に日蓮大聖人の仏法が伝えられることはなかったのである。小林は意図的に根本の宗開両祖のみを強調して、その流れである歴代上人を抹殺しょうとしているのである。これは創価学会の三宝破壊の邪義そのものであり、小林の正体がその走狗であることが明らかである。
まず指摘しておきたいことは、「結帰」は「結縁」の誤りであり、『歴代法主全書』では日因上人の写本によって訂正されている。また、『大日蓮』昭和五十八年八月号の「時局法義研鑽委員会ノートより③」においても、訂正されていることが述べられている。小林もそのことは知っており、論文に注記している。
注意すべきことは、小林が、
「『結帰』は『結縁』と改正されたという。しかし、そう読んでも真の師弟関係を宗開両祖に求めることに変わりはない」(同一二八頁)
としていることである。日因上人の写本があって、そこに「結縁」とあるのだから、素直に「結縁」と訂正した上で論ずべきである。「変わりはない」というならなおさらである。それでもなおかつ日因上人に従わないのは、「変わりはない」というのは本心から述べているのではなく、「結帰」のほうが都合がよいからである。
小林はこの「日蓮日興の師弟を以て結帰するなり」の御文を、そのまま「結帰」とした上で、「師弟関係の究極」と解釈する。「結帰」と読めば、あるいは「究極」との解釈が成り立つかのようにも見える。しかし、「日蓮日興の師弟を以て結縁するなり」と「結縁」と読めばどうであろう。「究極」の語に違和感が生じるのである。
小林は、ここではどうしても「究極」の語を使用したいのである。「究極」の語を使用すれば、唯授一人の血脈とは日興上人までであるかのように錯覚させることができるからである。そして、宗開両祖から日目上人以下を切り離し、歴代上人に伝持される血脈の仏法を隠蔽しょうというのが、小林の狙いなのである。
小林のような姑息な人物の論は、このように注意が必要である。わずかなことのように見えても、どんな策謀を企んでいるか判らないからである。
そこで熟拝しなければならないのは「日蓮日興の師弟」との文である。二箇相承の『日蓮一期弘法付嘱書』には、
「日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり。
弘安五年壬午九月 日 日 蓮 花 押
血脈の次第 日蓮日興」(平成新編御書一六七五頁)
とある。この「血脈の次第 日蓮日興」の「日興」とは、横に六老僧のなかで別して日興上人に血脈が伝えられたことを示すのであるが、縦には日興嫡々(ちゃくちゃく)の意義が込められ、総じて代々の御法主上人を指していることは当然である。創価学会の以前の理解がそうであったことは諸文献に明らかである。
『有師談諸聞書』の「日蓮日興の師弟を以て結縁するなり」の御文は、本因本果、師弟相対の法門を宗開両祖の師弟の上に示されたものであるが、『日蓮一期弘法付嘱書』と同様に、ここにも総別の意義が拝せられる。
すなわち、この師弟相対とは、唯授一人血脈相承の上の師弟相対である。つまり、別しての弟子とは、師である仏宝の日蓮大聖人に対する憎宝の随一・日興上人であるが、総じて言えば代々の御法主上人の御事であり、日蓮大聖人と歴代上人の師弟不二をもって至極と拝するのである。
ところで、「結縁」とは下種結縁の結縁であって、人法一箇の南無妙法蓮華経の法体が日興嫡々の御法主上人に伝持され、そこに仏法の一切が存し、一切衆生に結縁するの意である。
このように、「日蓮日興の師弟を以て結縁するなり」の御文は別の義の表現であるが、内には総の義を含むのであり、総じて言えば「日蓮日興嫡々の師弟を以て結縁するなり」の意と拝すべきである。
したがって、この御文は、小林の言葉を借りて言えば、「そういう意味では歴代法主の立場を『唯受一人血脈相承』で位置づける宗学」そのものなのである。
よって、『有師談諸聞書』の文と『化儀抄』の文とは矛盾しないのであって、小林の言うことは的外れであることが明らかである。
《お わ り に》
小林は、日有上人文書全般に対し、悪いイメージを抱かせ、そこに示される本宗本来の師弟相対の尊厳なる意義を乱して僧宝を破壊し、僧俗の信心を汚染しょうとしている。しかし、検証してきたように、所詮、小林の説は邪義である。また、小林は、聞書の文書は他人の表現が付加される危険があるから信用に値しないと言いながら、自分の都合によっては、日有上人の聞書や大橋慈譲師の聞書を利用するなど、その姿勢は一貫していない。
小林は本宗本来の血脈へicon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 19:58:44
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(下) 法義研鑽委員 岡 崎 道 清
《二、『日満への書状』に関する小林の謬(びゅう)見(けん)を破す》
小林正博は、『佐渡国法華講衆御返事』に説かれる「日興上人→直弟子→信徒」という富士門流の師弟の在り方を、大聖人と六老僧だけの関係にすり替え、さらに、『日満への書状』の一部の文を曲解し、引用して、
「結局、日興上人も、師弟子の法門について六老以外の阿仏房の門流に認め、前言を撤回しているのである」(東学研一二〇頁)
と言い放ち、結論として、
「法主絶対論を宗門草創期の文書から伝統法義として立証することは不可能」(同頁)
と述べている。このように小林は、日蓮正宗の「師弟子の法門」を否定するため、文証をすり替え、曲解し、間違った結論を導くという、二重、三重の誤りを犯している。
よって今回は、小林の引用する『日満への書状』を中心に述べ、破折を加えていく。
(一) 宗門上代における佐渡の状況
小林が宗門誹謗のために引用した『佐渡国法華講衆御返事』と『日満への書状』の関連について述べるに当たり、まず、それらの書が著された背景、すなわち、当時の佐渡方面の状況を考える必要がある。
佐渡方面が日蓮大聖人ならびに日興上人有縁の地域であることは、前回の「『佐渡国法華講衆御返事』に関する小林の謬見を破す」で既に述べた。
佐渡方面の僧俗の状況を見るとき、信徒としては、阿仏房の系統が法統相続して、代々、佐渡方面の中心的役割を果たしていた。一方、僧侶としては、大聖人御在世から学乗房、豊後房、山伏房という弟子がおり、そのほかにも大和房日性師や、阿仏妙宣寺や世尊寺に所蔵されている御本尊の脇書(わきがき)から佐渡日行師などの存在が窺(うかが)える。
学乗房は、大聖人が佐渡離島後、一谷(いちのさわ)入道の屋敷内に法華堂を造り、一谷妙照寺を開いたと伝えられている。また、豊後房も弘安二年ころ、阿仏妙宣寺の基礎を作ったと言われている。この両寺には、それぞれ日興上人の御本尊や御消息文が所蔵されているところから、当時、日興上人に連なっていたことが理解できる。
大和房日性師は、大聖人御在世に入信したと伝えられ、のちに本六僧の寂日房日華師に弟子入りしている。日性師については、本間重連の子との説や、中興(なかおき)入道の子との説もあるが、総本山第五十九世日亨上人は、
「順徳上皇の観音堂の堂守でなかったか(取意)」(富士日興上人詳伝五七八頁)
と仰せになっているように、佐渡には縁の深い人であった。佐渡本光寺所蔵の御本尊脇書などによれば、日性師は、延慶三年(一三一〇)六月に日興上人より御本尊を頂いて、十月には本光寺を創建している。日性師は日華師の弟子であるから、重須(おもす)の日興上人とは密接な関係をもって佐渡法華講衆を教化されていたのであろう。その後、日性師は、正和元年(一三一二)に日興上人より、
「佐渡の国の住平十郎安重一周忌菩提の為に舎兄大和房に之を与ふ」(富士宗学要集八巻二一八頁)
と脇書きされた御本尊を授与されている。本光寺の過去帳によれば、日性師はそれから二年後の正和三年(一三一四)に亡くなった。本光寺が創建されてから四年目のことである。
佐渡日行師については、阿仏妙宣寺所蔵の日興上人御筆御本尊の脇書に、
「正安二年九月日沙弥日行」(同二二三頁)
とあるように、正安二年(一三〇〇)当時は沙弥であったが、それから二十一年を経た元亨元年(一三二一)には、「日行房」としたためられた御本尊を賜っている。また、佐渡世尊寺所蔵の日興上人御筆御本尊の脇書には、
「元亨三年六月十三日、聖人御弟子蓮持尼七年(他筆)日行房之を相伝す」(同二一九頁)
とある。つまり、大聖人の弟子である蓮持尼の七回忌の追善供養のために日興上人が御本尊を授与なされ、それを日行師が相伝したのである。これからすれば、日行師は蓮持尼の子供であったとも考えられる。また、日行師は、嘉暦三年(一三二八)にも、「佐渡の国日行房」としたためられた御本尊を賜っている(同二二〇頁)。
このように佐渡においては、大聖人の在世より常に日興上人の流れを汲む僧侶が存在していたことが理解できる。
しかし、一方、他門流においても佐渡に入り、布教する動きが出始めていた。例えば日昭は、風間氏の外護を得て鎌倉に妙法寺を建立したが、文保元年(一三一七)に弟子・日成にあとを譲り、この寺を越後国の風間氏の領内に移し、北越弘通の拠点にするよう遺命した。これによって、寺泊(てらどまり)の隣に当たる三島郡村田の地に村田妙法寺が建立されるに至った。寺泊は佐渡渡島の玄関でもあるので、日昭門流の者達が北越弘通を企て、佐渡に渡ったことは想像に難くない。また、日朗門流も、のちに佐渡塚原に根本寺を建立しているように、佐渡の地に関心を持っていた。
日亨上人は、『佐渡国法華講衆御返事』述作の背景について、
「阿仏房日得の没後より、その曾孫如寂日満帰佐の三十年(筆者注、五十年か)ばかりの間に、富士系ならぬ宗徒が弘教せしことありと見えて、この雑乱を防がんがために、この状が発せられたのであろう。師資の系統明かならざる風来僧を師と仰ぐなの厳制が長文の各所に顕われており」(富士日興上人詳伝四二九頁)
と述べられている。つまり、阿仏房没後五十年が過ぎ、次第に他門流の宗徒が佐渡に入って法華講衆の信心を乱すことを日興上人は憂慮され、式部公や宰相殿を派遣されたのではないだろうか。そして、まず佐渡法華講衆に対して、当御返事をもって正統血脈のない他門流の僧を排除し、日興上人の弟子である「富士の僧」を師と定めるよう教えられたものと拝される。
小林は、『佐渡国法華講衆御返事』について、
「日興上人の言う『しでし』とは、宗祖を師とし、宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とするのであって、その六上足のいずれかの門流以外にはしでしの筋目を認めないという立場にたっているからである(中略)要は六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡なのである」(東学研一一九頁)
などと言っているが、日亨上人の「富士系ならぬ宗徒が弘教せしことありと見えて、この雑乱を防がんがために、この状が発せられた」との仰せからすれば、これがいかに的はずれであるか、誰にでも理解できよう。
(二) 如寂日満師について
如寂日満師は、阿仏房から三代目の遠藤盛正の次男として、延慶元年(一三〇八)に佐渡において出生したと伝えられる。そして、十二、三歳の年に、重須(おもす)の日興上人のもとに出家得度した。これについて日亨上人は、『日興上人年譜』を引用され、日満師の登山得度の年を元応元年(一三一九)と紹介されている(富士日興上人詳伝六八二頁参照)。
日満師は、元応元年の得度以来、元弘二年(一三三二)に北陸道の大別当として佐渡に帰国するまでの十余年間、重須の日興上人のもとで修行に励んでいる。
これからすると日満師は、『佐渡国法華講衆御返事』がしたためられた元亨三年(一三二三)の四年前には日興上人のもとに入室しており、元亨三年当時には十六歳であった。日興上人が、佐渡法華講衆に対して、
「そうしてさるべき人の御かうしうに御わたり候こそ、かたかたのためにもありがたきことにて候へけれ」(歴代法主全書一巻一八三頁)
と仰せられたことは、あるいは十六歳になる日満師の将来を見据(す)、えられてのことかも知れない。果たして日興上人は、それより九年後の元弘二年(一三三二)、積年の修行を修め、二十五の年齢を迎えた日満師に、佐渡法華講衆のための御本尊と御書等に関する置文を与えられた。
元弘二年七月二十四日付の、この書には、
「日満阿闍梨相計ひて信心を守り子孫迄之を付し、阿仏房の本堂に之を安置し本門寺の重宝たるべし、然らずんば富士本堂に入れ奉るべき者なり、縦(たと)ひ子孫たりと雖も私に之を与へ若(も)し又売買する者は同罪たるべきなり、此の旨に背きて師匠の教訓を用ひざる大謗法の輩に於ては自今以後永く本尊を之を付与すべからず」(富士宗学要集八巻一四五頁)
と記されている。つまり、日興上人は日満師に、佐渡法華講衆に対する「手続(てつぎ)の師」としての立場を与えられたのである。
なお、この文中の、「富士本堂に入れ奉るべき者なり」「師匠の教訓を用ひざる大謗法の輩に於ては自今以後永く本尊を之を付与すべからず」の語に注目すべきである。これこそまさに、日満師が富士門流である明らかな証拠ではないか。
続いて同年十月、日興上人は『師弟並に別当職に補する事』を定められ、
「右佐渡阿闍梨日満は学文授法に於ては日興が弟子たりと雖も代々の由緒有るに依て日蓮聖人の御弟子なり(中略)然れば阿仏房の跡相続の子孫は北陸道の法燈たるべきの由、日蓮聖人の御筆跡の旨に任せて日満阿闍梨は北陸道七箇国の法花の大別当たるべき者なり、大衆此の後此の旨を存知せらるべし、惣じて日興門徒の僧俗等聊(いささか)も之を違失することなかれ、若し此の旨に背くの輩は大謗法たるべきなり」(同頁)
と記されて、日満師を富士門流における北陸道七箇国の大別当に任ぜられ、この手続の師を中心に佐渡講中の盤石なる発展を期せられた。
(三) 「日興上人も前言を撤回した………」との小林の邪説を破す
しかるに、小林は、
「さらに、この書簡の九年後の日満への書状では、次のようにある。
『日満への書状』元弘二(一三三二)年十月十六日『本弟子六人を定め置かれる然りと雖ども阿仏房に於ては直弟子、聖人号を蒙りて仏法を(ママ)慧命を相続し(中略)日満阿闍梨は北陸道七箇の国の法華の大別当為る可き者也』
結局、日興上人も、師弟子の法門について六老以外の阿仏房の門流に認め、前言を撤回しているのである」(東学研一二〇頁)
と述べ、『師弟並に別当職に補する事』の『置状』の文をもって、「師弟子の法門」撤回の証拠として騒いでいる。
しかし、ここで小林は、二つのミスを犯している。
つまり、一つは『佐渡国法華講衆御返事』をもって、「六上足いずれかに属することが『師弟子の筋目』を通すことになる」との前提自体が狂っていることである。日興上人は、師弟子の筋目を教えるために、譬えとして大聖人在世における大聖人と六老僧の関係を示されたのであり、師匠を飛び越して「大聖人の直(じき)の弟子」と称する在り方を誡められているのであって、決して六老僧いずれかに属することを教えたものではない。
次に、当『置状』は、小林の言うように、六老僧いずれかに属することを否定し、阿仏門流を認めるために書かれたものではない。冒頭の、「右佐渡阿闍梨日満は学文授法に於ては日興が弟子たりと雖も代々の由緒有るに依て日蓮聖人の御弟子なり……」の文を拝しても明らかなように、まず、日満師は日興上人の弟子であり、また、代々の家柄によって日蓮大聖人の弟子ともされるのである。
また、結文には、「大衆此の後此の旨を存知せらるべし、惣じて日興門徒の僧俗等聊も之を違失することなかれ、若し此の旨に背くの輩は大謗法たるべきなり」と記されている。つまり、日興上人は、日満師が北陸道七箇国の大別当であることを佐渡の大衆に宣言し、僧俗ともにこれに背かないよう誡められた。
もし、小林の言うように、佐渡の僧俗大衆が五老僧の流れに与同し、富士門流ではなく、日満師も日興上人の弟子でないのなら、わざわざ「大衆此の後此の旨を存知せらるべし」とも「惣じて日興門徒の僧俗等聊も之を違失することなかれ」とも「若し此の旨に背くの輩は大謗法たるべきなり」とも、言われる必要などないではないか。
しかるに、小林は、『日満への書状』を引用し、〝日興上人が師弟子の法門について前言を撤回した〟との論を進める上で、「学文授法に於ては日興が弟子たり……」「惣じて日興門徒の僧俗等……」という大切な前後の文証を無視したのである。なんという卑劣さであろうか。
明らかに当『置状』は、日興上人が富士門流である佐渡法華講衆に対して、弟子である日満師を、その家柄や大聖人との因縁、そして法華講衆との結縁を考慮して大別当にされた所以(ゆえん)をしたためられたものである。故に、小林が当書の一部分だけの解釈によって、逆に阿仏房門流を認める文証とすること自体、見当違いも甚だしいと言わなければならない。
日亨上人は、日満師に関する御本尊や『置状』等の文献を挙げて、
「満師が、富士より北陸道の大導師大棟梁として下られし事は明晰(めいせき)であり、曾祖父阿仏房日得の聖祖門下の大地位、すなわち北陸道の大導師格をその子の藤九郎盛綱が伝えて大聖人より御信任を受けた家系が、九郎太郎守(盛)正の妙覚に、またその長男の右馬太郎守(盛)安の妙行に伝わったなかに、次男の興円の如寂丸が阿仏房の伝統の源泉なる富士に登りて猛修練の上、日順日代等の法兄にも提撕(ていせい)せられて、公明に両個の置状を賜わりて佐渡に下りて全佐は申すにおよばず越後地方の法縁にも君臨したのであり、大本門寺建設の要員として重大な広布の御奉公ができたのはとうぜんの事である」(富士日興上人詳伝六八五頁)
と解されている。小林よ、日興上人の時代には「阿仏房の門流」など存在せず、佐渡は純然と日興上人の門流だったのである。
まして、『日満への書状』が、〝師弟子の法門を撤回した文証〟であろうはずがないのである。
《結 論》
以上述べてきたように、日満師への大別当職授与についても、日興上人との師弟相対の信心を抜きにしてはありえないことを知るべきである。
『佐渡国法華講衆御返事』の「六老僧」に関しての御指南も、日蓮大聖人の御在世には、大聖人に連なる六老僧を軸にした師弟関係が強調されたと同様に、日興上人の御在世には、日興上人に連なる本弟子を軸にした師弟関係が大切になることを示されたものに他ならない。日興上人が、大聖人在世の六老僧を譬えに出した所以は、決して小林の言う「六人の上足を正統な弟子とする」などの意味ではなく、日興上人を中心とする師弟子の筋目を正した唯授一人血脈にかなった信仰をすることを教えんがためである。大聖人御在世の六老僧制定の意義を、小林は虚心に考えるベきである。
師弟子の在り方については、例えば『弟子分本尊目録』にも如実にその姿が拝せられる。つまり、日興上人は、日目上人や寂日房日華師などの本六僧については、
「日興第一の弟子也」(歴代法主全書一巻八九頁)
と記されている反面、孫弟子の肥前房日伝師などには、
「寂日房の弟子也」(同九〇頁)
と記されている。すなわち、肥前房は寂日房日華師を通して日興上人に連なっているのであり、直ちに日興上人に連なってはいない。このように日興上人は、師弟子の筋道を厳格に説かれている。
故に、日興上人は、『佐渡国法華講衆御返事』の結文に、
「うちこしうちこしぢきの御でしと申やからが、しやう人の御ときも候しあひだ、ほんでし六人をさだめおかれて候。そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといはせんずるためにて候。あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人はうばうにて候也。御こうしうらこのむねをよくよくぞんぢせらるべし」(同一八四頁)
と、大聖人の御在世にも、また滅後にも、師匠を飛び越して師弟を乱す間違った信仰の者がいたことを示し、師弟子の筋目を正さなければならないことを重ねて誡められたのである。
ちなみに、大聖人滅後に自分こそ大聖人の直弟子であると名乗り、師弟子の筋目を乱した謗法の末弟として、波木井日円入道をあげることができよう。波木井日円は、正応二年六月五日の日興上人への書状に、
「日円は故しやう(聖)人の御で(弟)し(子)にて候なり申せば老僧たち(達)もおなじ(同)どう(同)ぼう(胞)にてこそわたらせ(渡)給ひ候(中略)御経にこう(功)をいれ(入)まいらせ候、師匠の御あはれみ(愍)をかぶ(被)り候し事おそらく(恐)はおとり(劣)まいらせず候、ぜん(前)ご(後)のしや(差)べち(別)ばかり(計)こそ候へ、さ(然)れば仏道のさはり(障)になる(成)べしともおぼへ(覚)ず候なり」(富士宗学要集八巻一四頁)
と述べている。要するに日円は、もともと日興上人の弟子であるにもかかわらず、「自分は大聖人の弟子であり、あなた方老僧とは同じ仲間である。御本尊のために功績を積み、大聖人より慈悲を受けたことは、おそらく劣らないだろう。ただ入門の前後の違いだけである」と言ってのけたのである。
これこそ、今の創価学会の体質と全く同じではないか。
日興上人は、このような波木井日円の事例を加味されて、佐渡法華講衆に師弟子の筋目を正すよう厳誡されたと拝される。
しかるに、小林は、この「師弟子の法門」について、
「今回の宗門問題では、宗門側は信徒のあるべき姿勢として師である法主への絶対的信奉に立たなければ仏法は成り立たないとする『師弟子の法門』を強調している。すなわち『師弟の筋目』『師への信』を宗旨とすることは宗開両祖以来の伝統といってはばからないのである。この論理は葬送儀礼における僧侶の介在を正統化する有力な根拠にもなっている。もちろん師弟の筋目を通すことは教団運営の上で必要不可欠であり、宗開両祖以来の伝統であることには、いささかも否定するつもりはない。しかし、強要するあまり、宗祖の仏法を狭隘化させ、息苦しいものにして、信徒を束縛しているところが問題なのである」(東学研一一八頁)
と述べている。これを見ただけでも、小林のそれが学術論文という次元のものではなく、ただ単に小林個人の感情論であることが明白である。
小林は、成仏のための深い教えである師弟相対の法門について、宗開両祖以来の伝統であることを二の次にして、教団運営の上で必要不可欠と言っているが、これは明らかに本末転倒の考えである。このような本末転倒の考えを起こすこと自体、常日頃から師弟相対の信心を教団運営の手段としか捉えていない小林の心根を如実に物語っている。
また、「信徒を束縛している」などの言葉も、彼自身や学会組織の一部の人間が、そのように一方的に思い込んでいるだけのことで、決して宗門では束縛も強要などもしてはいない。逆に、「強要する」「束縛している」などと被害妄想を抱いているようでは、そのうち一般社会からも相手にされなくなるであろう。なぜなicon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 19:45:56
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(上) 法義研鑽委員 岡 崎 道 清
《は じ め に》
東洋哲学研究所員の肩書きを名乗る小林正博は、
「中世・近世における宗門の法主絶対論者は、特に開山・日興上人の段階で法主絶対が存在しており、開山以来の伝統教義と位置づけているのである。これが現宗門の法主絶対論になると、彼らの存在に関わる根本宗義にまで押し上げた手前、なんとか宗開両祖以来の伝統教義であることを、多くのそれらしい文証を集めて立証しょうと必死である」(東学研一〇八頁)
と述べ、その「法主絶対」なるものの文証の一つとして、日興上人の『佐渡国法華講衆御返事』を挙げ、
「日興文書の『師弟子の法門』『師弟の筋目』という表現をもって、歴代法主への信順を伝統宗義とする論理は成り立たない」(東学研一〇九頁)
との見通しを立てて『佐渡国法華講衆御返事』をあげつらい、『日満師への書状』を曲解した上で強引に、
「法主絶対論を宗門草創期の文書から伝統法義として立証することは不可能(中略)法主絶対路線の強行は宗開両祖からの逸脱」(東学研一二〇頁)
との結論を導き出している。
私は、『佐渡国法華講衆御返事』と『日満師への書状』に関する小林の邪見を破折するため、この二書をめぐり二回に分けて検討を加えたい。
《一、『佐渡国法華講衆御返事』に関する小林の謬見を破す》
なんとしても御法主上人への信伏随従を否定したい小林は、「師弟子の法門」が述べられている『佐渡国法華講衆御返事』の存在が不愉快極まりないらしい。そのために小林は、「日興文書の『師弟子の法門』『師弟の筋目』という表現をもって、歴代法主への信順を伝統宗義とする論理は成り立たない」と述べ、当御返事の「師弟子の法門」を頭から否定しょうとする。
そのため小林は、二つの理由を挙げている。すなわち、
一、『佐渡国法華講衆御返事』が日興上人の著であることが疑わしい。
二、仮りに日興上人の真書であっても、ここでいう「師弟子の法門」とは、御法主上人に信順する文ではない。
というものである。
(一) 『佐渡国法華講衆御返事』が日興上人の御作でないとの疑難について
まず、一の理由について小林は、
「この書簡の取扱いについては、はたして日興作かどうかを検討する必要がある。『日興・日目御筆御本尊略目録』の花押の研究の部では、この書簡の花押『白蓮(日興)花押』を疑点があるとしているのである。この目録は、宗門内部の研究グループである歴代室の業績であるが、これが宗門の公式見解であるのかどうかを筆者は知らない。しかし、このような宗門内部の研究成果など無視するかのように、法主への信順を正当化する文証としてさかんに引用しているというのが現状である」(東学研一一九頁)
として疑問を投げかけ、姑息にも体(てい)よく本山歴代室に責任を負わせる形で、当書を否定しょうと試みている。しかし、小林の言う『日興・日目御筆御本尊略目録』は、山口範道師個人の研究になるもので、「宗門内部の研究グループである歴代室の業績」などではない。山口師は、研究成果を小林に勝手に悪用され甚だ迷惑をされている。
ちなみに山口師は、先般、「『佐渡国法華講衆御返事』の疑論を糺す」を『大日蓮』誌に掲載され、花押について書体と墨色の相違こそあれ、御本紙を拝見すれば日興上人の真書であると論証されている。そして結論として、
「この消息(『佐渡国法華講衆御返事』)は開山(日興)上人の正文書である」(大日蓮五八二号七三頁)
と断言されている。
よって小林による、山口師の研究をもっての非難は的はずれと言うべきである。
(二) 日興上人の真書であるとしても、「師弟子の法門」は大聖人と六老僧の関係を述べたとする邪推について
小林は、〝もし『佐渡国法華講衆御返事』が日興上人のものであったとしても、唯授一人の御法主上人に信順する文ではない〟と主張する。
小林は、「師弟子の法門」について、宗門がよく引用する文証として、
「『このほうもんはしでし(師弟子)をただして、ほとけになるほうもんにて候なり』
『しでしをただしてほとけになり候、しでしだにもちがい候へば、おなじほくえ(法華)をたもちまいらせて候へども、むげんぢごくにおち候也うちこしうちこしぢきの御でしと申すやからが、しやう人の御とき候しあひだ、ほんでし六人をさだめおかれて候、そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといわせんずるためにて候』」(東学研一一九頁)
と、『佐渡国法華講衆御返事』の二文を取り上げている。そして取り上げたその二文だけを中心にして推論し、
「日興上人の言う『しでし』とは、宗祖を師とし、宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とするのであって、その六上足のいずれかの門流以外にはしでしの筋目を認めないという立場にたっているからである」(同頁)
などという、思い付きの虚言を吐いている。そして、さらに続けて、
「したがって六上足によらず、阿仏房の流れにあって『じきの御でし』と称する佐渡講衆の姿勢を否定しているのである。要は六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡なのである」(同頁)
と言うのである。
この小林の所論は、おおむね四つの点にわたって誤りを犯している。今これを列記すると、
① 師弟子は大聖人と六老僧に限定するとの誤謬(ごびゆう)
② 悪意に満ちた文章の改竄(かいざん)
③ 五老僧与同の邪見
④ 佐渡法華講衆が阿仏房門流であるとの邪説
となる。
① 「師弟子」は大聖人と大老僧に限定するとの誤謬を破す
まず小林は、『佐渡国法華講衆御返事』がいつ著されたかを考えてみるべきである。大聖人御在世に著されたのであれば、大聖人と六老僧との「師弟」の関係を説諭する必要性も場合によってはあるだろう。しかし当書は大聖人が御入滅されてから四十一年後のものである。つまり日興上人は、当書において大聖人の御在世当時の「師弟子の筋目」を主眼として説いているのではなく、元亨三年当時の富士門流における「師弟子の筋目」を正されたのである。それは『佐渡国法華講衆御返事』を最初から最後まで通して拝せば誰にも理解できる。
すなわち、小林は、
「このほうえはしでしを、たゞして、ほとけになるほうもんにて候なり」(歴代法主全書一巻一八二頁)
の文を引用しているが、『佐渡国法華講衆御返事』にはその前のところに、
「さいしやうどの御事、しきぶのきみのほんじやくのほうもんを申を、きこしめして、御かう、一とうにならせ給たるやうにきゝ候しあいだ、さのとおもふて候へば、そのぎなきに御かうしうよりも、さいしやうどのよりもうけ給候。さては御しはたれにて、御わたり候けるぞ、たれより、さうでんしたりとも候はす。かうしうは、しでし、ぞんぢせぬと申され候。かやうに、あらかに御わたり候けるを、一とうの御かうに、しまいらせ給けるこそ、ふさたに候へ。じこんいごは、しをさだめて、かうしうにも、一とうせられ候べし」(同頁)
の文が冒頭から述べられている。この文は明らかに、師弟相対の信心ができない法華講衆に対して、師を定めた信心をするよう制誡なされたものである。つまり日興上人を中心として、それに連なる弟子と信徒の師弟子の筋目を正した、富士門流の在り方が示されている。それを、「日興上人は師弟子を大聖人と六老僧に限定する」などと言うようでは、小林の目は節穴と言うべきである。
日興上人は続けて、日本国の一切衆生が初発心の本師釈迦如来を捨てて、無縁の阿弥陀・大日・薬師如来を師と頼み本師に背いている故に、無間地獄に堕ちるのであるとの大聖人の御指南を拝し、いかに初発心の師に随順することが大切であるかを説いている。
引き続き、
「さいしやうどの御しんじんを、をこし、ほんじやくのほうもんをきこしめしうけとらせ給ける、しはたれにて候けるぞ。御しだにもさだまし候はゞ、御こうにも、一とうこそ候はめたゞしは御しさだまらず候けるあひだ、こぞよりして、かうしう一とうしまいらせぬよしうけ給候はありがたく候。そうしてさるべき人の御かうしうに御わたり候こそ、かたかたのためにもありがたきことにて候へけれ。さいしやうどのよりの御じやうにも、御しはたれとも候はす、かうしうよりも、しでしぞんちせぬと申され候あいだ、御くやうおさめまいらせず候」(歴代法主全書一巻一八三頁)
と述べられている。いずれにしても小林は、これらの文の「師弟子」を、どう読めば「大聖人と六老僧」だと言うのだろうか。
「そうしてさるべき人の御かうしうに御わたり候こそ、かたかたのためにもありがたきことにて候へけれ」と述べられているように、日興上人のもとから佐渡法華講衆のために正統な僧侶が派遣され、この師を中心に信仰していくよう、日興上人は望まれている。また日興上人は、師弟子を弁えない法華講衆の御供養を納められなかったが、これは師弟の筋目を正す日興上人の御精神のあらわれである。
さらに、その師弟子の法門を重ねて諭されたのが、「なをなをこのほうもんは、しでしをただしてほとけになり候………」の文なのである。
要するに当書は、全体を通して「日興上人→手続(てつぎ)の師→信徒」という師弟の在り方を説示されたものである。よって、この文のなかに大聖人と六老僧の師弟のことが書かれていても、それは弟子と末弟子、弟子と信徒の関係を解りやすく理解させるために過去の一例として示されたもので、日興上人の主眼ではない。
それすらも解らないのは、小林が当書をすべて拝読していないからか、読解力がないからか、それともすべて解っていながら人を欺くために解らないふりをしているか、のいずれかであろう。いずれであっても小林は学者として失格である。
② 文章改竄による小林の悪意を破す
次に小林の文章改竄を暴き、その欺瞞(ぎまん)を粉砕する。
小林は、『佐渡国法華講衆御返事』の「師弟子の法門」を大聖人と六老僧の関係だけに限定させるために、あえて都合の悪い前後の文を削除した。
小林が『佐渡国法華講衆御返事』の文として挙げたのは、
「『このほうもんはしでし(師弟子)をただして、ほとけになるほうもんにて候なり』
『しでしをただしてほとけになり候、しでしだにもちがい候へば、おなじほくえ(法華)をたもちまいらせて候へども、むげんぢごくにおち候也うちこしうちこしぢきの御でしと申すやからが、しやう人の御とき候しあひだ、ほんでし六人をさだめおかれて候、そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといわせんずるためにて候』」(東学研一一九頁)
の二つであるが、前文については前項で破折を加えたので、ここでは触れないことにする。しかし後の文については特に悪質な改竄を行っているので、徹底的に破折を加えていきたい。
まず小林は、「しでしをただしてほとけになり候………ほんでし六人をさだめおかれて候、そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといわせんずるためにて候」と引用して、いかにも「師弟子の法門」のすべてが大聖人と六老僧の関係であるかのように取り繕っている。しかし小林は、その後に続く肝心な文を無視するのである。すなわち、次下には、
「あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人はうぼうにて候也。御こうしうらこのむねをよくよくぞんぢせらるべし」(歴代法主全書一巻一八四頁)
と述べられている。
要するに、〝大聖人の時代にあっても直接の師匠を飛び越して、末弟や信徒が大聖人の直弟子であるなどと称して師弟の筋目を混乱させる者がいたのであり、それを防ぐために大聖人は六老僧を中心とする師弟子の筋目を説かれたのである。案の定、大聖人の入滅後も大聖人直結を唱える者が多く出てきた。これらは謗法であり、日興の門弟においては絶対にそのような師弟子を弁えない行為があってはならない〟以上が日興上人のお心である。
つまり、一例として挙げられた大聖人御在世の六老僧の文と、「あんのごとくしやう人の御のちも………」という結文とは一連の文章である。
しかし小林は、なんとしても日蓮正宗の「師弟子の法門」を否定しなければならないため、引用を六老僧の例文までに止め、都合の悪い最後の文を隠蔽(いんペい)している。しかも『歴代法主全書』に「うちこしうちこしぢきの御でしと申やからが、しやう人の御ときも候しあひだ………」とある文を、「うちこしうちこしぢきの御でしと申すやからが、しやう人の御とき候しあひだ………」と改竄するほどの念の入れようである。
小林が改竄して削除した「も」とは、①特定の事物をあげて、その他にもそれと同類のものがあることを暗示したり、②同類のものを列挙する係肋詞である(新潮国語辞典より)。
小林にしてみれば、「師弟子」の関係を大聖人の御在世だけに限定したいので、類型を示唆する係助詞の「も」が邪魔だったのだろう。つまり、「あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人はうぼうにて候也」という最後の結文に続くことを予想させないために「も」さえもはずしたのである。それでいて小林は、日蓮正宗に対し、
「日興書状による師弟子の法門の強要は、切り文による自己正統化のそしりを免れない」(東学研一二〇頁)
と言い放ち得々としている。しかし、これなどはあたかも泥棒が善良な市民をつかまえて泥棒だと叫んでいるようなもので、滑稽ですらある。このような魔に魅入られたかのような行為をして、当宗の伝統法義を破壊せんとする小林とはいったい何者なのだろうか。
③ 五老僧与同の邪見を破す
小林は、『佐渡国法華講衆御返事』から随意に文を抜き出し、そのわずかの文を手がかりにして、自分に都合のよい結論を導き出した。その過程で、
「宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とする」(東学研一一九頁)
「六上足のいずれかの門流以外にはしでしの筋目を認めない」(同頁)
「六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡」(東学研一二〇頁)
と主張する。小林の解釈によれば、〝日興上人は佐渡法華講衆に対して、五老僧の門下でもよいからとにかく六老僧のいずれかに属するよう教えられた〟ということになる。
たしかに大聖人は、御入滅に先立つ弘安五年十月八日に六老僧を選定なされた。しかしそれとは別に大聖人は、六老僧の選定をはさむ九月と、十月十三日に、身延・池上両相承書をもって日興上人に唯授一人の血脈相承をなされている。これらのことをどのように会通するかといえば、六老僧の選定は、教団組織の維持・発展の便宜のためであり、また、それぞれの縁故の弘教地域における掌握指導をしていくためである。それに対し唯授一人血脈相承は、滅後の法嗣選定である。要するに、六老僧選定はあくまで信仰の筋目を示すものであって、法体を付嘱される血脈相承とは別次元のものと拝さなければならない。
大聖人の御在世に限って言えば、小林の言う「宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とする」ことも決して誤りではないだろう。
しかし大聖人の御入滅後に、日興上人を除く他の五老僧達は、唯授一人の血脈を承継される日興上人に信順できず、法門を改変し敵対してしまったのである。
実際、『佐渡国法華講衆御返事』をしたためられた元亨三年(一三二三年)の十四年前に当たる延慶二年(一三〇九年)には、既に日興上人が寂仙房日澄師に命じて『富士一跡門徒存知事』を書かしめ、五人の立義を破折し富士の正義を宣揚されている。特に同書には、
「此の相違に依って、五人と日興と堅く以て義絶し畢(おわ)んぬ」(平成新編御書一八六八頁)
と記されて、本迹勝劣・神社参拝の可否・修行の行儀・戒法・御書・本尊等と、多岐にわたって日興上人と五老僧との相違・勝劣が説かれている。
このような状態であるのにもかかわらず、何も日興上人が佐渡法華講衆に対して、本尊も教えも修行もすべて混乱している五老僧に「師事せよ」と言われる道理などないではないか。ところが小林は、平然と『佐渡国法華講衆御返事』の文を指して「六人の上足を正統な弟子とする」などと述べている。これはまさに、五老僧の不相伝家を肯定し与同する行為と言わなければならない。
さらに言えば、このような考え方をすること自体、小林には日興上人の門流に身を置く必要がなく、日昭門流や日朗門流、身延門流の信仰でもよいと平気で考えているのではないか。小林の所論を用いて池田・大作が指導を行い、各地の学会会館で小林に講演を行わせている実態からすれば、むしろ学会が、身延や池上、中山等の日蓮他門流との合併に向けての理論構築をしているようにも思える。
ちなみに不相伝家では、大聖人の仏法の奥義が六人平等に付嘱されているという六老僧平等論なるものがあるが、既に総本山第二十六世日寛上人は『当流行事抄』において、
「間ふ(中略)日興上人は上足の第三なり何ぞ是結要付属の上首ならんや(中略)答ふ六老の次第は受戒の前後に由り伝法の有無は智徳の浅深に依る(中略)吾開山上人は智は先師に等く徳は諸弟に超えたり、故に塔中伝受の秘要を附して本門弘通の大導師と称し末法万年の総貫首と定め二箇の相承を授けて延山の補処と為す」(富士宗学要集三巻二一四頁)
と仰せられ、六老僧の次第と唯授一人血脈相承の相違から、日興上人お一人に血脈が具わっていることを教示されている。
また、創価学会発行の『仏教哲学大辞典』にも、【血脈の次第】の項に、
「仏教の真髄は、口決相承・血脈相承でなくてはならない。また日蓮大聖人の相承は、六老僧に対して平等になされたなどという迷論もあるが、それは血脈相承の本質からいっても歴史的にみても誤りである」(同書二巻七四頁)
と記されていることを、念のため付け加えておこう。
④ 佐渡法華講衆が阿仏房門流であるとの邪説を破す
小林は、
「阿仏房の流れにあって『じきの御でし』と称する佐渡講衆の姿勢を否定し(中略)結局、日興上人も、師弟子の法門について六老以外の阿仏房の門流に認め、前言を撤回している」(東学研一一九頁)
と言っている。要するに彼は、「佐渡の阿仏房系の法華講衆が、六老僧の次第を飛び越して大聖人直結を訴えたので、日興上人がそれを注意された。しかし、そののち日興上人は、前言を撤回され、六老僧以外の流れである阿仏房の門流を認めた」と主張するのである。
しかし、もともと佐渡方面には、小林の言うような「阿icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 19:34:47
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の文について 法義研鑽委員 近 藤 恒 道
《は じ め に》
小林正博の論証方法が、切り文を多用した悪意的なものであることは、これまでの『大日蓮』掲載の破折論文によって明らかにされてきた。
小林は『法主絶対論の形成とその批判』において、教団草創期に表れる唯授一人血脈相承に関する文として、妙蓮寺第五代日眼師の著した『五人所破抄見聞』の中に見られる、
「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也、在世には唯我一人の大導師は釈尊也、末代には上行菩薩本門の別付属唯我一人也」(富要四巻九頁)
の文を挙げて邪説を吐いているので、今回はこの『五人所破抄見聞』に関する小林の邪説を破折しておきたい。
《頭も切り足も切り》
小林は、この文に関して何ら具体的な論証もせずに、
「唯授一人を日興上人にかぎっているので、歴代法主の相承には結び付かない」(東学研一一六頁)
と一言で結論づけている。
たしかに「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の部分だけを見れば、この文はあたかも歴代法主上人を除外して「唯授一人」が日興上人に限っているように読めるが、この文の前後をあわせて引用するならば、
「名字の妙法を通達し玉ひ釈尊出世の設化爾前四十余年にも秘し迹門十四品の間にも秘し本門寿量品に於ても秘密し玉ふ処の御内証結要五字の真文を譲り給ふと云へども、無常の相を娑婆に訓へ、一瓶の法水を日興に御付属あり、日興も寂を示し玉ひ次第に譲り玉ひて当時末代の法主の処に帰り集る処の法花経なれば法頭にて在す也、秘す可し口外す可からず、六老僧有りと雖も法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也、在世には唯我一人の大導師は釈尊也、末代には上行菩薩本門の別付属唯我一人也、争でか告勅に背いて唯我一人の法花経を六人までに御付嘱あらん乎、六人の上首は日興上人也(傍線は筆者)」(富要四巻九頁)
とある。
小林よ、よく見るがよい。「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の文頭には、「六老僧有りと雖も」とあるではないか。さらに次下には「争でか告勅に背いて唯我一人の法花経を六人までに御付嘱あらん乎、六人の上首は日興上人也」とまで記されているのである。
これらの文を虚心に読めば、五一相対の上から法主は日興上人に限られるのであり、他の五老僧には唯我一人の付嘱をされていないとの意味であることは明らかである。それを小林は、前後の文を切り取って、五一相対の意義を日興上人と日目上人以下の歴代法主上人との関係にすりかえ、あたかも『五人所破抄見聞』に示される「法主」が日興上人に限られ、歴代法主上人には及んでいないと読ませようと仕立てたのである。まさに小林は、貴重な文証の頭を切り、足を切ったのである。
《歴代上人もすべて法主》
小林が主張するように、法主が日興上人に限るというならば、その前にある「日興も寂を示し玉ひ次第に譲り玉ひて当時末代の法主の処に帰り集る処の法花経なれば法頭にて在す也」の文は、小林の言い分と矛盾する内容になる。
この文こそ、大聖人より日興上人へ付嘱された結要五字の妙法が、日興上人滅後においても順次に譲られ、当代法主上人に伝えられていることを明確に示しているではないか。
これほど歴代法主上人と唯授一人血脈相承について明言されているにもかかわらず、この大事な一文を小林は「教団草創期に表れる唯授一人血脈相承に関する文」として挙げていない。おそらくは、小林はこの文が唯授一人血脈相承を述べるに近い表現のもの、すなわち明確に述べていないものと見なしているのであろうが、この読解力の低さこそ、小林の似非(えせ)学者ぶりを如実に示す一例である。
《卑劣な小林の検証態度》
ここで、小林の『五人所破抄見聞』に対する論述姿勢を見てみたい。
小林は、『五人所破抄見聞』が大聖人滅後百年頃に存在していたとなると自分の主張に不都合なため、何とかしてその成立年代を下げようと難癖を付けている。『五人所破抄見聞』の系年についての小林の見解に対しては、他の委員によって破折が加えられるのでここでは具体的に触れないが、小林が、『五人所破抄見聞』を上代のものではないとしている事実のみを確認しておきたい。
小林は、『五人所破抄見聞』の「日興も寂を示し玉ひ次第に譲り玉ひて当時末代の法主の処に帰り集る処の法花経なれば法頭にて在す也」という歴代法主上人ならびに唯授一人血脈相承に関する文を自己流に解釈して「法主絶対」を述べたものと決めつけ、その上で同書に対して、
「これらはいずれもそう仮託されているものばかりなのである」(東学研一一三頁)
とか、
「妙蓮寺日眼説に大きな疑問が投げかけられている。むしろ同名の西山八世日眼(十五世紀後半)の著作とした方が落ちつきがよい」(東学研一一五頁)
といって同書を疑い、その上で、
「(五人所破抄見聞など)の文をもって、法主絶対を宗開両祖以来の伝統法義とみなすことはできない」(東学研一一五頁)
などと、ウソぶくのである。
ところが、小林は、次の項になると、
「教団草創期に表れる唯授一人血脈相承に関する文を列記すれば以下の通りである」(東学研一一五頁)
として、『五人所破抄見聞』の「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の文は、教団草創期の文として再び挙げるのである。
ひとたびは否定しておきながら、都合によって再び持ち出してくる小林の論述姿勢は、ただただ卑劣と言うほかはない。
《重なる誤り》
さらに、小林は、三位日順師が著した『本因妙口決』の、
「此の血脈は高祖聖人・弘安五年十月十一日の御記文・唯授一人の一人は日興上人にて御座候」(富要二巻八四頁)
の文についても、『五人所破抄見聞』の場合と同じように「唯授一人」とは日興上人に限るとして、歴代法主上人の相承に結び付かないというのである。
しかし、「弘安五年十月十一日の御記文」とは『本因妙抄』を指しており、『本因妙口決』は『本因妙抄』を解説したものである以上、『本因妙抄』との関連の上で、その文意を考えなければならない。したがって、小林が挙げた『本因妙口決』の「唯授一人の一人は日興上人云云」の文意についても、『本因妙抄』の、
「此の血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承唯授一人の血脈なり」(平成新編御書一六八四頁)
の御文をもとに判読しなければならないのである。
小林よ、この『本因妙抄』の御文における「唯授一人の血脈」が、なぜ歴代法主上人を含まずに日興上人に限ると言えるのか。もし、そうであるならば、日興上人以後、法は伝わらないとでも言うのであろうか。
『本因妙抄』に示される「日蓮嫡々」「伝法」の語をよくよくかみしめるがよい。その上で『本因妙口決』の「唯授一人の一人は日興上人にて御座候」の文を正直に拝するならば、これが歴代法主上人を否定した文ではなく、『五人所破抄見聞』の文と同じく、五一相対の上から日興上人を唯授一人の一人とされたことが理解できるであろう。
《お わ り に》
『五人所破抄見聞』についての小林の誤りは、まず「六老僧有りと雖も」との大前提と、結論である「争でか告勅に背いて唯我一人の法花経を六人までに御付嘱あらん乎」の文を切り離したことにより、本来、日興上人と五老僧とを対比し解釈すべき文を、日興上人と歴代上人とを対比させてしまったことである。考えてもみよ。『五人所破抄見聞』という題名が示すとおり、『五人所破抄見聞』は五老僧の破折を目的に書かれたものである。したがって、同書の文は当然、五一相対の上から読むべきなのである。
次に、小林は、同じ『五人所破抄見聞』の「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の文をもって「唯授一人を日興上人にかぎっているので、歴代法主の相承には結び付かない」と一方的に主張し、その直前にある「日興も寂を示し玉ひ次第に譲り玉ひて当時末代の法主の処に帰り集る処の法花経なれば法頭にて在す也」の文を敢えて隠蔽するという誤りを犯している。
また、『本因妙口決』についても、小林は『五人所破抄見聞』の誤りと同じく、日興上人と五老僧とを対比し解釈すべき文を、日興上人と歴代上人とを対比するという誤りを犯している。
小林は、宗史を学ぶ上での基本的精神を忘れ、邪心をもって清浄なる唯授一人血脈相承を否定せんとして、自ら用いた文によって自説を破る結果を招いたのである。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 18:57:00
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
「一覧表」について 法義研鑽委員 森 岡 雄 樹
《法主絶対論と一覧表》
今回取り上げる「一覧表」は、小林正博が『法主絶対論の形成とその批判』(東洋学術研究第三二巻第二号一〇四頁)と題する邪論の中に掲示したものである。小林はこの「一覧表」について次のように述べている。
「現宗門が引っ張り出してきた文を中心に、宗史に見る法主絶対論的表現の問題点を考えてみたい。
まず、これらの引用を一つ一つ検討するにあたって、初めにある程度の見通しをつけておきたい。
一に、宗史において明確な法主絶対論を標榜するのは、十二世日鎮上人を支えた左京日教が最初であって、宗開両祖の段階では法主絶対論を見出すことはできない。
二に、唯授一人血脈相承の法主という位置づけは、日興門流の激しい正嫡争いを背景として表出した時代の産物である。
三に、日興文書の『師弟子の法門』『師弟の筋目』という表現をもって、歴代法主への信順を伝統宗義とする論理は成り立たない。
この見通しを論証するにあたり、宗開両祖から左京日教までの、宗義書について、関連する記述の有無を一覧化してみた。表を参考にしていただきたい」(東学研一〇八頁)
まず小林は、宗史に見る法主絶対論的表現の問題点に対する「見通し」をつけるとして、一から三までの「見通し」を挙げている。「一覧表」はその三つの「見通し」を論証するために、各宗義書の内容を分析した結果を表示したものだそうである。
ところで、小林の論は、『法主絶対論の形成とその批判』という題にも見られるように、「法主絶対論」という新造語を中心に論が展開されている。なにげなく聞けば、唯授一人血脈相承のことを指しているかのような、この新語には、実は唯授一人血脈相承を否定し破壊しょうとする、池田/大作率いる創価学会の怨念と悪意が込められている。
つまり、「法主絶対論」の語と、それに付随する小林の論理は、血脈相承が宗史の中間に造り上げられたものであるかのように錯覚させることを目的としている。したがって、御法主上人に対するイメージは、宗史の中間で捏造(ねつぞう)された権威を背景とする「非道の絶対者」のように変質させられることになる。
平成三年より行われてきた、創価学会による宗門攻撃の一環として御法主上人のイメージダウンを謀(はか)り、日蓮大聖人の血脈法水そのものを隠蔽(いんペい)しょうとする狙いを込めて、いかにも論理的であるかのようによそおって、特に学会員向けに用意されたのが、小林の論である。
小林の邪論には、このような悪意・魔性が隠されていることを、まず指摘しておく。
さて、小林論文が邪論であることを明らかにするに当たり、彼の論理が妥当であるかどうかを考えてみた。特に「一覧表」は、宗義書の内容を分析表示することをもって、小林の論証が客観的研究態度による考察であるかのように、読者に印象づけようとしているから、「一覧表」に表示された分析結果に偽りや誤りがあれば、それを根拠とする論文の内容が不当であることは明らかである。
結論から述べれば「一覧表」は、謀略性に富んだインチキなものであり、小林論文が邪説であることを端的に証明している。
《項目の設定》
小林は「一覧表」に『本因妙抄』等の二十八種類の文献を挙げている。このうち、日有上人の文献は更に数種類に分かれているので、実際には三十種類の文献を挙げていることになる。これらの文献の記述の中から、次の十項目の内容が含まれているかどうかを探るのである。
その十項目とは「上行再誕」「日興正嫡」「富士正意」「寿量文底」「釈尊脱仏」「本因妙」「名字即位」「久遠元初自受用身の再誕」「唯授一人・血脈相承」「法主絶対」である。これらの項目に該当する記述が文献にあるか否かを探索し、その上で、○(表現があるもの)、◇(後加分にあるもの・◇は本文では破線の○である)、△(近い表現のあるもの)印を付して選別している。
この中で注意しなければならないことは、「法主絶対」という項目が設定されていることである。前述のように、小林が「法主絶対」の語を使用する意図は、一般学会員および世間に対して、御法主上人は「悪」とのイメージを抱かせて、人々を欺(あざむ)こうとするところにある。
そのため、法主絶対化の具体的例証として、最近、宗門は創価学会問題をめぐって「宗制宗規」を改正し、法主が「宗制宗規」上の絶対的権限を確立したとしている。さらに、その法主絶対の背景となっているのは宗義上に法主絶対論が存在することによるが、宗祖・開山には法主絶対論はなく、後世の産物、特に左京日教師によって発生するとしているのである。
しかし、日蓮正宗において御法主上人は、大聖人以来、その血脈を伝持し、本尊の書写、教義の裁定等、本宗を統率される、現時における至尊の方であることは宗門不変の伝統であり、「法主絶対」などという用語は使用されることはない。
故に、この「法主絶対」の項目を含む「一覧表」は、項目の設定自体に悪意が存するのである。このような「一覧表」を作成する人物であるから、その分析結果もおのずと信頼できるものでないが、一往、その分類にしたがって「一覧表」に分析されるような記述が各文献にあるかどうかを確認してみたい。
※ 一 覧 表(EXL作成版へ)
《内 容》
第一に、小林の分析では、『本因妙抄』には、本文に「上行再誕」がないとしているが、二十四番勝劣の中に、
「彼は薬王・此は上行」(富要一巻六頁)
との記述があり、天台大師が薬王の再誕であることは大聖人の御書中に見られる表現であるから、ここにいう「此は上行」は、大聖人の上行再誕を意味することは当然である。百歩譲っても、これは近い表現であるから、△印を付けるべきであるが無印である。
第二に、『百六箇抄』には、堀日亨上人が後加分とされた部分に、
「本地自受用報身の垂迹・上行菩薩の再誕」(富要一巻九頁)
とあるから、「上行再誕」の項目は「後加分にあるもの」の◇(本文では破線の○)印を付すべきである。
第三に、同じく『百六箇抄』には、本文の種の十二番に、
「我等が内証の寿量品とは脱益寿量の文底の本因妙の事なり」(富要一巻一六頁)
と、明らかに「寿量文底」が記されている。しかし、「一覧表」は空白である。
第四に、『産湯相承事』には、本文に、
「上行菩薩の御身を凡夫地に謙下し給ふ」(富要一巻二七頁)
とあるから、「上行再誕」が述べられている。譲っても「近い表現のあるもの」とはすべきである。しかし、△印はない。
第五に、『御本尊七筒相承』の、
「代々の聖人悉(ことごと)く日蓮なり」(富要一巻三二頁)
との御文を「法主絶対」と判断し、後加としているが、いうまでもなくこの御文の真意は、小林のいうような「法主絶対」を意味してはいない。しかも、これは後加文ではなく本文である(前号所載・国井師の論文を参照)。
第六に、『本尊三度相伝』には、後加分とされている箇所に、
「日興に相伝す」(富要一巻三八頁)
とあるから、「日興正嫡」の項目に◇(本文では破線の○)印を付すべきである。
第七に、『三時弘経次第』には、本文に、
「上行菩薩 日蓮聖人」(富要一巻四九頁)
とあるから、「上行再誕」の項目に、○でなくても△印は付すべきである。
第八に、『誓文』には、
「日蓮聖人は・恭(かたじけな)くも上行菩薩の後身」(富要二巻二七頁)
とあるから、「上行再誕」の項目に、○印か△印を付すべきである。
また、『誓文』には、
「富山独(ひと)り正像已過の権迹を廃して新に本地の妙法を弘む」(富要二巻二七頁)
ともあるから、「富士正意」の項目に、○印か△印を付すべきである。
これらはほんの一例であるが、小林が「一覧表」に挙げた史料文献のほとんどにわたって、その分析結果に明らかな漏れや誤りが見られた。小林は、この「一覧表」を作成した理由について、
「この見通しを論証するにあたり、宗開両祖から左京日教までの、宗義書について、関連する記述の有無を一覧化してみた」
というように、これによって本論文を論証しようとしているのてあるが、その論証基盤がこのようなデタラメなものである以上、はじめからこの論は成立のしようがない。
これらの分析結果の漏れの原因は、ただ文献をろくに読んでいないという、あまりにもおそまつなものなのである。
日蓮大聖人は、『報恩抄』の中で真言宗に対して、
「ぼう書をつくるゆへにかゝるあやまりあるか」(平成新編御書一〇二七頁)
と、謀りごとの書を作るために、逆に謀りごとが露見するミスを犯すのであると御指南されている。
小林も真言宗と同様である。「法主絶対論」をデッチ上げ、それが左京日教師あたりから発生したように見せかけようという、幼稚な謀略を企て、その小道具として「一覧表」を作成したのであったが、はからずもその「一覧表」の「あやまり」のために、論文自体が成立しなくなるという大失態を演じてしまったのであった。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 11:08:52
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
小林正博の意図的な文献検証 法義研鑽委員 国 井 位 道
東洋哲学研究所学術研究員・小林正博は、「法主絶対論の形成とその批判」において、昨今の創価学会問題の原因は、現宗門の「法主絶対論」にあると決めつけた上で、法主絶対論が宗開両祖からの伝統法義ではないことを論証しようとしている。
そのために、小林は、日興上人門流の上代の宗義書として『富士宗学要集』より二十八書を選び出し、それぞれの内容について検討を加えながら、法主絶対論は宗開両祖からの伝統法義ではなく、第九世日有上人の滅後、左京日教師(一四二八〜 ? )のころにならなければ見られないと述べている。そして彼は、大石寺では宗祖本仏論を悪用した形で法主の権威化を図ってきたと主張し、唯授一人の血脈も門流保全のために後世に作り出された論理である、と言う。最後に小林は、
「あえて、宗史からなぞらえれば、現宗門の体質は、日教の逸脱路線の継承、日教亜流といえるのである」(東学研一二六頁)
と決めつけている。
しかし宗門には、小林が言うような「法主絶対論」はもともと存在していない。ところが小林は、宗門の「唯授一人の血脈の大事」を、むりやり「法主絶対」にすり替えて、難くせをつけているにすぎない。
小林の論文を見ると、意図的な史料文献の取り扱い方が目につく。そこで私は、彼の史料文献の検証方法について、その誤りを指摘しておきたい。
《『富士宗学要集』における一線と二線との違い》
小林の文献の検証方法を見てゆく前に、彼は文献の引用を『富士宗学要集』によっているので、最初に『富士宗学要宗』を拝する場合に注意すべき事柄を確認しておきたい。
第五十九世日亨上人は『富士宗学要集』を編纂されるに当たり、真書はもちろんのこと、同一本の複数の写本にも自ら目を通されている。そして、収録文書の全体にわたって細かく対照した上で、必要個所に一線または二線を付し、頭注を加えられている。
この一線と二線について日亨上人は『百六箇抄』の文末に、
「後加と見ゆる分の中に義に於いて支吾なき所には一線を引き、疑義ある所には二線を引いて読者の注意を促がす便とせり」(富要一巻二五頁)
と注記されている。つまり、大聖人滅後に加筆されたと思われる個所に線を施され、しかもそのうち、義において支吾(差しつかえ)ない部分には一線を、疑わしい部分には二線を、それぞれ付されたのである。
次の表は、『富士宗学要集』第一巻において、日亨上人が一線または二線を付された文献をまとめたものである。
『富士宗学要集』に日亨上人が付された一線と二線
文献名
線種
付線に関する日亨上人の御説明
本因妙抄
一線
後加と見ゆる部分には一線を引く
百六箇抄
一線
後加と見ゆる分の中に於いて支吾なき所には一線
二線
疑義ある所には二線を引いて
産湯相承事
二線
二線を引きたるは後人の偽托なるが故なり
御本尊七箇相承
二線
二線を引きたるは後人の偽加なるを以つてなり
寿量品文底大事
二線
二線を加へたるは後加にして削除すべきが故なり
上行所伝三
大秘法口訣
二線
*御説明なし
(「日興之を記す」のみに二線)
日亨上人が線を付された六種の文献は、すべて相承書である。しかも、一線のみが付された『本因妙抄』の御説明が「後加と見ゆる部分」となっているのに対して、二線のみが引かれた三文献には「後人の偽托」「後人の偽加」「後加にして削除すべき」となっている。表現の違いは一目瞭然である。一線と二線の両方が付された『百六箇抄』でも、前述の通り「義に於いて支吾なき所」と「疑義ある所」と、その意義に差異が認められる。
《いい加減な文献の用否》
さて、小林の全体を通しての論述姿勢を端的に表しているのは、
「まず、これらの引用を一つ一つ検討するにあたって、初めにある程度の見通しをつけておきたい」(東学研一〇八頁)
との文である。小林は、二十八もの文献の内容検討を始める前に、既に見通しをつけている。すべての文献を公平に検討したあとに結論を導くのではなく、検討以前から結論を決め、それに沿った形で論述を進めている。
だからこそ、小林自身の論旨に都合のよい文献は尊重するが、そうでないものに対しては、意図的に無視し軽視するのである。
小林の文献の検証方法を一口に言えば、疑義ありとする文章を根拠として、それに類似する文章の真偽を検証するという方法である。この手法をしばしば用いて、真書の文献をいとも簡単に否定するのである。
例えば、絵画の本物とニセ物があった場合に、本物を基準とするのではなく、ニセ物を中心として本物を見るようなものである。いくらニセ物に似ているからといって、本物の絵画をニセと認定しては、いつまで経っても本物を見極めることはできない。これと全く同じ誤りを、小林は犯しているのである。
《類似文を悪用して真書を軽視》
この手法によって、小林が無視し軽視した真書の文献には、『御本尊七箇相承』と『産湯相承事』が挙げられる。
まず、『御本尊七箇相承』に関する小林の所論を見てゆくこととする。小林は、『御本尊七箇相承』の、
「一、日蓮在御判と嫡々代々と書くべしとの給ふ事如何、師の曰く深秘なり代々の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」…………A(富要一巻三二頁)
との御文の真偽を検討するに当たり、わざわざその前に記述されている、
「又本尊書写の事予が顕はし奉るが如くなるべし、若し日蓮御判と書かずんば天神地神もよも用ひ給はざらん、上行無辺行と持国と浄行・安立行と毘沙門との間には・若悩乱者頭破七分・有供養者福過十号と之を書く可し、経中の明文等心に任す可きか」…………B(富要一巻三二頁)
との御文を採り上げている。そして、
「実はこの文とほとんど変わらない文が『百六箇抄』の写本には存在していた」(東学研一一四頁)
として、
「五十九世堀日亨上人はこの『百六箇抄』の文には、一線ではなく、二線を引いて疑義ある所と判じているのである。ということは同じ追加部分にある③の文(筆者注、前出Aの御文)だけを日興上人に寄せることは到底できない」(東学研一一五頁)
と、『御本尊七箇相承』の「一、日蓮在御判と嫡々代々と云云」を日興上人の御文ではないと断定している。
しかし、実際に文献を検証してみれば、『富士宗学要集』の『御本尊七箇相承』の御文にはまったく線が引かれていない。小林自身がBの御文と「ほとんど変わらない」と述べた『百六箇抄』の御文には確かに二線が引かれているが、『御本尊七箇相承』の御文には二線どころか一線さえも引かれていない(写真①を参照)。
しかも、『御本尊七箇相承』の末尾に、日亨上人が、
「編者曰く(中略)年月御名判等の三行に二線を引きたるは後人の偽加なるを以ってなり」(富要一巻三三頁)
とわざわざ記しておられるように、『御本尊七箇相承』では「後人の偽加」に対して二線を引かれたことが明らかである。つまり日亨上人は、『富士宗学要集』の『御本尊七箇相承』においては、「年月御名判等の三行」のみが「後人の偽加」であって、AおよびBの御文を含むそれ以外の部分は「後人の偽加」ではなく真書であると、判じておられるのである。
ところが小林は、『百六箇抄』に引かれた二線のみに執着して、『御本尊七箇相承』の御文に線が引かれていないことに関しては何も論述していない。むしろ、このことには目をつぶり、あえて触れないようにしている。
これでは、小林の検証方法がまったく公正さに欠けたものであることは、誰の目にも明らかである。
《小林の言う類似性は的はずれ》
次に、小林が軽視したもう一つの『産湯相承事』に関して、検証をしてみる。『本因妙抄』の末文で、一線が引かれている、
「此の血脈並に本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書塔中相承の稟承唯授一人の血脈なり」…………C(富要一巻八頁)
との御文と、『産湯相承事』の、
「予が一期の功徳は日文字に留め置くと御説法ありし儘、日興謹んで之を記し奉る。聖人の言く此の相承は日蓮嫡々一人の口決、唯授一人の秘伝なり、神妙神妙との言給ひて留め畢んぬ」…………D(富要一巻二八頁)
との御文を比較して、小林は、
「『日蓮嫡嫡』『唯授一人』という表現など類似性を指摘できるので、④の文(筆者注、前出Dの御文)を日興上人の記とは断じ難い」(東学研一一六頁)
と決めつけている。
「類似性が指摘できる」と小林は言っているが、実際にCとDの二文を見比べてみれば、「日蓮嫡々」「唯授一人」以外に、いったいどんな類似性があるというのか。共通している文は皆無であるし、共通の言葉は「相承」の一語しかない。『産湯相承事』の八十数文字の文の中で、たった十文字しか共通していないにも関わらず、類似性が指摘できるとする小林の感覚は、誰でも精神に異常をきたしていると思うに違いない。
《『富士宗学要集』の一線部分を「偽加」と曲解》
百歩譲って、CとDが類文だと仮定しても、前項と同様の誤りを犯している。『富士宗学要集』の『産湯相承事』を拝してみれば、前出の『御本尊七箇相承』と同様に、日付・御名判の部分に二線が引かれているだけで、Dの御文には一線さえも引かれていない(写真②を参照)。
さらに、小林が『産湯相承事』のDの御文を否定する根拠とした『本因妙抄』には、もともと二線ではなく、一線のみが引かれていることを見逃してはならない。つまり、『本因妙抄』のCの御文は、同抄の文末に、
「後加と見ゆる分には一線を引く」(富要一巻八頁)
と記されているように、大聖人滅後に書き加えられた部分でも、この小論の冒頭で確認済みの『百六箇抄』文末の「義に於いて支吾なき所」に当たるのである。
ところが小林は、Cの御文を「後加」すなわち「偽加」と曲解し、これを根拠にして、安易にDの御文を否定しているのである。
ここに、文献の用否における小林の身勝手さが、如実に表れているのである。
《小林の論述は我田引水の見本》
小林が無視し軽視した実例を二つ挙げてみたが、彼の論述姿勢とは、文献を公平に取り扱うのではなく、意図的にその用否を前もって決めつけるものである。
「唯授一人の血脈」を無視して三宝破壊を続ける創価学会のお先棒をかつぐ小林としては、今まで挙げた御文が存する文献を偽書と位置づけるか、自分たちに都合の悪い御文は宗開両祖のものではないとしたいのであろう。なんとか文献の不備を突こうと、あら探しに血眼になり、ようやく捜し出した『富士宗学要集』の一線と二線を悪用して、このような論述となったのである。これでは、いかに多くの文献に目を通したとしても、けっして公正に文献を検証したことにはならない。悪意を持った文献検証では、真実は永遠に得られるわけがない。
小林よ、もっと公平な眼で文献を拝し、真摯に検討していきなさい。君の論文は、まさに我田引水の見本である。我意我見で文献の用否を決定し、邪教・創価学会の都合に合わせた勝手な推量で論を進める君に、研究員と名乗る資格が全くないことを、ここに断言しておく。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 10:06:57
icon
「Re:小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す 」
小林正博の論述姿勢について 法義研鑽委員 古 藤 志 道
《はじめに》
「東洋哲学研究所学術研究委員」の肩書きを名乗る小林正博は、平成五年十月十五日発行の『東洋学術研究』(以下、『東学研』と略す)に「法主絶対論の形成とその批判」という研究論文を発表したが、もとより日蓮正宗には、小林のいうような「法主絶対」なる教義などないのである。
小林は、その「はじめに」のなかで、
「本稿では、大石寺宗門の主張である『法主絶対論』を取り上げ、その形成過程を追い、法主絶対論は、宗開両祖以来の伝統法義ではないことを論証していきたい」(東学研一〇四頁)
と述べ、日蓮正宗に「法主絶対論」なるものが存在すると決めつけた上で、本宗の宗史に難くせをつけようとしている。
その内容は、荒唐無稽(こうとうむけい)ではあるが、放っておけば「嘘も百回言えば本当になる」を主張してきた創価学会のこと、この小林の論旨を平然と定着させてしまう恐れがある。
今後、小林論文に対しては、他の諸師より、完膚(かんぷ)なきまで鉄槌を加えられるであろうが、今回、私は、小林の基本的論述姿勢にスポットを当てながら、その悪質さをあばくこととする。
《悪質なスリカエ》
最初に問題としなければならないのは、小林が勝手に思い込み、本宗の伝統教義と決めつけている「法主絶対」である。
小林は、『大日蓮』号外の、
「私ども日蓮正宗の信仰をする僧俗は、御法主上人に対したてまつるとき、御法主上人の御所持あそばされる大聖人以来の血脈の法体を、ひたすら合掌礼をもって拝するのです。したがって、御法主上人の御指南は、護持される法体の上から、大聖人の仏法を根源的な意義においてお説きあそばされるのであり、私どもは真摯な態度で拝聴することが大事なのです。つまり、私どもは信伏随従して、御法主上人の御指南を拝すべきであり、そこにこそ本当の師弟相対の信心、即身成仏の大直道があることを知らねばなりません」(平成三年三月十五日発行 五六頁)
との一文を紹介した上で、
「宗門側の姿勢をよく明示している表現の一例だが、ことほどさように法主絶対がまさに絶対の尺度となっているのである」(東学研一〇五頁)
と決めつけている。
ところが、小林が挙げた引用文は文証にはなってはいない。なぜなら、引用文の意味するところは、至極当然の「法体の血脈の大事」に関する伝統宗義についての記述であり、「法主絶対」の用語もなく、「絶対服従」を強制するものでもないからである。この部分を小林のような解釈しかできないとすれば、それは文章の読解力の低い人間か、初めから悪意をもって読もうとする場合であろう。
小林がこのような読み方をする理由の根本には、今回の「創価学会問題」がある。
小林は、
「池田名誉会長の発言を法主批判と断じて法華講総講頭罷免に始まり、解散勧告、除名、破門と信徒処罰を繰り返し断行するものであった。その一つ一つを取り上げて論じる余裕はないが、いずれも『法主批判』を理由にしての処断であった」(東学研一〇五頁)
と、今回の学会問題を分析しており、結論的には、
「突き詰めれば、事の争点は『法主絶対』をめぐっての問題とも集約できる」(東学研一〇四頁)
と、怨みがましくその元凶が「法主絶対論」だと憤慨している。
すなわち、小林の「法主絶対論」は、創価学会および池田/大作の処遇問題が、深く絡んでいるのであり、背景には、創価学会の存在があることを、自ら露呈している。
創価学会といえば、「まず創価学会ありき。池田/大作ありき」であるために、その意にそぐわなければ、たとえ「法主」であろうとも、無節操に見解を変えてしまう組織である。したがって、そのお先棒をかつごうとすれば、必然、小林のようなねじ曲がった文章解釈になってしまうのである。
かつての創価学会は、
「日蓮正宗の根幹をなすものは血脈である。大御本尊を根本とし、代々の御法主上人が、唯授一人でこれを受け継ぎ、令法久住をされてこられた」(広布と人生を語る三巻二五六頁)
「法水写瓶の血脈相承にのっとった信心でなければ、いかなる御本尊を持つとも無益であり、功徳はないのである」(広布と人生を語る八巻二二八頁)
等と言っていたのだが、以前から比べれば、昨今の主張はまったく逆である。これは、本宗信仰の根本の筋目どころか、人間としての良心を捨てなければ、とてもできないことである。
その変節した創価学会にとっては、「御本尊御書写の権能」と「現時における宗義等の決裁権」等が、日蓮正宗の御法主上人御一人に在(ましま)すことが、不愉快きわまりないのである。
要するに、小林は、本宗の「法主上人への尊崇」「法主上人の権能」という法義・信仰の精神を、政治的・世俗的な「法主絶対」なる意味にスリカエようと企んでいるのであり、その底意は怨念そのものなのである。
御書の随所に示されるように、仏法には「教相・観心」「外用・内証」「総・別」等の立て分けがあるのは当然のことである。
平成三年に、創価学会に対して説諭された、いわゆる『能化文書』にも、
「三宝一体とは、まさに本仏大聖人、戒壇の大御本尊、歴代の御法主上人が、その内証において、一体不二の尊体にましますということであります。外相においては、確かに仏法僧は別体でありますから、日顕上人や日達上人の仰せのように、歴代の御法主上人が、ただちに御本仏大聖人ではありません(傍線は筆者)」(大日蓮五四八号一三六頁)
とある。
日蓮正宗において法主上人に対し奉り、「不二の尊体」と申し上げ、また、「信伏随従」申し上げるのは、御法主上人の「内証」に金口(こんく)相承されているところの「宗祖の御法体」すなわち「内証の血脈」に対してである。
仏説観普賢菩薩行法経には、
「諸仏を見たてまつると雖も、猶お未だ了了ならず。目を閉ずれば則ち見、目を開けば則ち失う」(開結六八四頁)
とあり、仏法は心眼、すなわち信心をもって受け止めねばならないと説かれている。小林には、この一点が欠落している。
つまり、小林のいう「法主絶対」と、日蓮正宗の「法体の血脈の大事」とは、初めから異なった次元なのである。本来、それくらいの立て分けは、仏教を論ずる者なら充分、心得ていなければならない常識である。
にもかかわらず、小林がこのように本宗の伝統宗義である「法体の血脈の大事」と「法主絶対」とを混同させ、「日蓮正宗の法主は絶対君主」とのレッテルを貼ろうとする目的は、ひとえに宗門を誹謗し、会員を誑惑(おうわく)するためなのである。
《不公平な文献の取り扱い》
小林は、自論を立てる前提として、本宗の宗義書(相伝書を含む)を羅列して一覧表を作成し、A(本迹勝劣)・B(宗祖本仏論)・C(法主絶対論)と割り振り、○(はっきりとした表現のあるもの)とか△(近い表現のあるもの)の記号をつけて区分している(東学研一一〇頁〜一一一頁)。
しかし、小林が挙げている一つひとつの文献に当たってみれば、彼が文献をまともに読んでいないために、誰が見ても、その一覧表がデタラメであることが判るであろう。
しかも、この一覧表には、本宗の重要な相伝書である『二箇相承書』『日興跡条条事』が無視されている。本宗の血脈を論ずるのに不可欠なこの二書を何故、取り上げないのか、小林はその理由を全く述べていない。
この重要書を外して、小林はいったい、なんの血脈、なんの相伝を論じょうというのであろうか。
このような史料文献に対する不公平な態度や御都合主義の姿勢こそ、愚劣な底意を端的に示している。
《悪質な、切り文テクニックの例》
◆『本因妙口決』に関して。
小林は、自ら文献区分のために作成した一覧表の欄外の注に、
「要解⑩一般日蓮宗では、本因妙口決は後人が順師にたくして、天台色のあるものを書いたものとみている」(東学研一一一頁)
と、あたかも堀日亨上人が、一般日蓮宗の論調と同意されているかのように、補足している。
ここで小林が取り上げた『要解⑩』とは、現正継寺御住職である大橋慈譲師が、日亨上人の御教示を元として執筆された『富士宗学要集の解説』のことである。
この『富士宗学要集の解説』(以下、『要解』と略す)は、創価学会発行の『大白蓮華』に、昭和三十四年二月号から同三十五年四月号までの十五回にわたって寄稿・連載されたものである。
小林は、この『要解』の文章を、日亨上人の談として紹介しているのである。
しかし、実際の『要解』には、続いて、
「しかし日蓮大聖人のもの、そのものが、中古天台の説を使用している。ゆえに順師がそうだからといって偽作にするのは変である」(大白蓮華一〇二号二八頁)
とある。
日亨上人がここで述べられたのは、一般日蓮宗の『本因妙口決』への疑難に対して、当門流としては、三位日順師が天台の学問に造詣が深かったというだけの理由で『本因妙口決』を偽作扱いすることはできないと、一般日蓮宗とは正反対の御見解を示されているのである。
ところが、小林の引用では、狡猾(こうかつ)な切り文(カット)によって、まるで日亨上人が『本因妙口決』を偽作扱いしているかのように記している。
あえて『要解』を引用していながら、次下に続くこの文章を無視するやり方も、小林の悪質な論述姿勢の一例である。
◆『日順雑集』に関して。
小林は、再び『要解』を引いて、
「⑩日順雑集は『無題の本をあつめて雑集とした。伝来には、房州のものと、要法寺のものとある。雑集を分類すると、数多くあって、すべて断片である。写本には、天文度のもの、延徳度のものもある。(★)そうとうに慎重に考えてあつかわねばならない」(東学研一一〇頁〜一一一頁・注(★)印は筆者)
と、あたかも日亨上人が『日順雑集』にも疑問を持たれているように仕組んでいる。
この引用文で小林は、重大な改竄(かいざん)を試みている。それは、当方が(★)印を付した箇所についてであるが、この箇所にある長文を小林は、なんの断りもなしに削除していることである。しかも、この文が削除されたことにより、日亨上人の御真意がねじ曲げられているのである。
そこで、日亨上人が実際に仰せになっている(★)印の部分を、全文引用してみる。
「満足に、そのまま古写本を写したものもある。全部、雑集である。
頭に丁づけがあるが、丁づけのとおり、つづいているわけではない。古写本としては、おもしろい価値のあるものである。丁づけがのこって断片的にあるのは、かえって古写本としての価値がある。これは丁づけするとき、すでに散乱していたものらしい。
『従開山伝日順法門』は、要法寺の写本にそうあるだけで、順師の原本にあるものではない。これは、まとまっているが、御書の内容ではない。これには、そうとうの肝要の法義が書いてある。このような、バラバラの法門を研究するには、その時代の法門を頭にいれる必要がある」(大白蓮華一〇二号二八頁)
とあって、このあとに「そうとうに慎重に考えてあつかわねばならない」と続くのである。
これと、先に小林が引用した部分とをつなげて読んでみると、日亨上人は、『日順雑集』に対する文献批判の目的で「慎重に」と仰せられたのではない。
実際には、『日順雑集』中に集録された『従開山伝日順法門』に対しての解説をなさって「そうとうに慎重に考えて」と仰せなのである。
つまり、この引用文の正しい読み方は、『日順雑集』の中味は既存の御書に関しての内容ではなく、日興上人より伝えられた重要法門であり、時代的な背景を念頭において置かなければ、なかなか難しい。だからこそ、より慎重に、ということなのである。
日亨上人は、『日順雑集』全般に対しては、「かえって古写本としての価値がある」と仰せではないか。
小林および創価学会の邪義は、日亨上人に対する反逆であり、師敵対謗法に当たることを知るべきである。
このように、小林は、恣意的な決めつけ論やスリカエ論で終始しており、さらには、なんとしても自論に結びつけようとするあまり、「意図的なスリカエ」「史料文献を御都合主義で扱う」「故意的な文章の読み変え」「悪質な切り文」等の幼稚なトリックを、随所に使用している。
つまるところ、この小林論文は、学術的な体裁を装った、似非(えせ)論文というべきものである。
icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: 21世紀さん
2009/05/31 10:00:28
icon
小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す
大日蓮・第584号(平成6年10月・63頁)
小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」
に対する破折論文の掲載について
昨平成五年十月に発刊された『東洋学術研究』第三十二巻二号に、小林正博なる者が「法主絶対論の形成とその批判」という論文を発表した。その内容は、学術研究論文とは名ばかりで、史料文献を曲解・悪用し、無理に唯授一人の血脈を破らんとする、いわば初めから結論が定まっているという、極めて恣意的(しいてき)なろんである。もとより、このような稚拙な論が通用するはずはなく、当初、反駁(はんばく)するに足らざるものとして捨て置いてきた。
しかし、その後、池田/大作がこれをベースに「『法主絶対論』は絶対に邪義」(平成六年二月十八日)などと放言し、また小林自身、各地の創価学会会館で「法主絶対論批判」と題する講演を行っている。要するに、「法主絶対論の形成とその批判」とは、邪教池田創価学会そのものが主体となって行なっている誹謗なのであり、けっして小林個人だけの説でないことは明白である。
このたび、法義研鑚委員会として、この邪論を破折したので、以後、数回にわたって、委員諸師より提出された破折論文を掲載していくものである。
大日蓮・第584号(平成6年10月・64頁)
小林正博の論述姿勢について
法義研鑽委員 古 藤 志 道
大日蓮・第585号(平成6年11月・84頁)
小林正博の意図的な文献検証
法義研鑽委員 国 井 位 道
大日蓮・第586号(平成6年12月・76頁)
「一覧表」について
法義研鑽委員 森 岡 雄 樹
大日蓮・第587号(平成7年1月・79頁)
「法主は白蓮阿闍梨に限り奉る也」の文について
法義研鑽委員 近 藤 恒 道
大日蓮・第589号(平成7年3月・79頁)
「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(上)
法義研鑽委員 岡 崎 道 清
大日蓮・第590号(平成7年4月・82頁)
「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(下)
法義研鑽委員 岡 崎 道 清
大日蓮・第592号(平成7年6月・68頁)
日有上人文書に対する小林の疑難を破す
法義研鑽委員 影 山 広 道
大日蓮・第594号(平成7年8月・72頁)
『五人所破抄見聞』の著者についての小林の邪論を破す
法義研鑽委員 高 橋 粛 道
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 8
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-