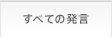サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: 21世紀さん
2011/09/03 15:07:44
icon
「Re:池田大作の実像」
【貸し金業】
<「金集め」に腐心した青春時代>
池田大作は第2代会長・戸田城聖がやっていた金貸し業の社員出身である。彼は1949年(昭和24年)1月、21歳になったばかりのとき、戸田の経営する出版業「日本正学館」に「小僧から入った」が、同社はその年10月には倒産、同時に、池田は戸田が専務理事をつとめる小口金融「東京建設信用組合」の社員に移動した。
「重苦しい中を、仕事のことで、部長と、O学園にゆく。またO第一小学校に回る」(50年5月10日『若き日の日記』1)
池田は戦前の創価教育学会員や、個人的な知り合いなど、誰彼問わず訪ねては、カネを貸すよう頼み回った。信用組合は取り立てにからんで、刑事事件までひき起こしていた。
50年8月、東京建設信用組合は大蔵省から営業停止を命ぜられ、ここに戸田は事業家として致命的に敗れた。組合法違反に問われ、債権者からは告訴されるハメに陥る。そのため戸田は創価学会理事長の椅子を去り、後任を矢島周平(後に大宮・正因寺住職=故人)に譲って夏期講習会にも出られず、一時は城聖の名を城外と変え、雲がくれした。
だが、戸田も一筋縄ではいく男ではない。いつ起訴されるかもしれない身にもかかわらず、裏では同じく小口金融の「大蔵商事」を用意していた。同社の初代代表役員は矢島周平(2代は和泉覚)だったが、実権は専務理事の森重紀美子、それに戸田自身が握った。森重は公然とした戸田の愛人である。池田は直接の上司である奥山和平が責任をとって去ったため、50年11月に営業部長に昇格した。(『フォーラム21』H15.1.1)
●ちょっと池田大作のことを調べたことがありましてね。そうしたら、かなりひどいことをやってるんですよ。池田大作は青年部にいた前、財務を担当してたんですね。そこで高利貸しをやってたんですよ。それで、苦しい商店街とかあるでしょ?そこに金を貸して、返せなくなると、即刻、土地を担保に取っちゃうんですよ(脚本家・笠原和夫『昭和の劇』太田出版/佐高信『噂の真相』H15.4)
-----------------------
取った後に、新しい職を見つけてやったり、店を開かせたりして学会に取り込んでいく。池田より1歳上で、観念だけでは生きられないという同じ戦後的人間の笠原は、それを「偉い」と思って映画化しようとしたがダメだった。(佐高信『噂の真相』H15.4)
●戸田城聖第2代会長は金の面は自分で何とかしようとして、大蔵商事など金貸しや信用金庫などを随分とやったんです。その尻拭いと言うか、酷な言い方をすれば金貸しの手代をしていたのが池田大作です。彼も当初は好きでやっていたわけではないと思うのですよ。しかし、彼には才能があったようで、池田が"ここ金あるよ"という家には、見た目は貧乏な家でも必ず金があった、ということを古参の幹部から聞きました。逆に門構えの立派な家の前で"ここはどうだ?"なんて聞いても、池田が"ここにはない"と言えば、その通りだったそうです。(小川/頼宣=創価学会本部元広報部副部長『週刊新潮』H15.12.18)
●要するに、観念でもって今さら宗教だなんて言うやつはおらんと。金だと。食うためにやるんだと。現実主義で、金を集めるために宗教をやるんだと。じゃあ、それを誰がやるのかという時、俺がやってやると出てきたのが池田大作なんですよ。宗教家なんていうのは、みんな金貸しなんてことはやりたくないわけでしょ?それで返せなくなったら土地を取り上げるなんてことは1番汚い。要するに手が汚れる話ですよ。それを誰がやるのかという時に、俺がやってみせると。それが池田大作の今の出世の基なんですよ(脚本家・笠原和夫『昭和の劇』太田出版/佐高信『噂の真相』H15.4)
-----------------------
池田に対するホメ殺しのような笠原の「礼讃」だが、多分、学会員は猛反発するに違いない。金正日と同じように「伝説」は十分につくられているからだ。(佐高信『噂の真相』H15.4)
●(※大蔵商事に入った頃)昭和25年に池上でやった最初の同窓会に現れた時だったな。あの時のことは今でも忘れられない。昭和17年卒業組は今昔会という同窓会を開くんだけど、その時、池田は遅刻してきた。同窓会に顔を出したのは後にも先にもその時だけだよ。遅刻してきたのに、恩師に挨拶もせずに、どっかりと席をおろして、いきなり演説を始めたんだ。大きな声で。みんな驚いたよ。遅刻してきたのに、いきなりですからね。ひとしきり自分の話が終わったら、初めて"おっ先生、元気か"なんて片手をあげた。田中角栄みたいなあれだよ。目立たないだけのあの男が、いつの間にかそういう尊大さを身につけていたんだ。(小学校時代の同級生『週刊新潮』H15.12.18)
-----------------------
大蔵商事時代の彼が、水を得た魚のごとく活き活きとし、さらに周囲が驚くほどの尊大さを身につけ始めたのは注目に値する。
<会長就任後に発揮したほんとうの酷薄さ>(『フォーラム21』H15.1.1抜粋)
池田は大蔵商事では、戸田の愛人である専務・森重紀美子に密着して仕えた。戸田夫人に対してより、いっそう彼女にゴマをすった形跡がある。
大蔵商事の社業は順調に推移し、57年には甲賀(※当時国鉄大宮機関区の経理係長で、東京建設信用組合の協力者のひとり)が退職者の58人のカネを取りまとめて貸していたカネ600万円も返すほどの勢いだった。甲賀は学会本部に呼ばれ、戸田からこういわれる。
「大蔵商事はカネもできた。だからこのカネは返したいのだが、どうだろう。ワシに一の友人である精文館書店の北村宇之松にそっくり貸してやれないか」
甲賀は出資者とも相談のうえ、戸田から、まして学会本部で頼まれたことでもあり、精文館書店にカネを回すことにした。戸田の保証つきと受けとめたのである。戸田が生きている間は、精文館書店もきちんと利子を届けて、何1つ問題は起こらなかった。同社は戸田の『巻頭言集』、『人間革命』(池田の同名書とは別)、湊邦三の宗教小説、経本などを刊行して、相応の利益をあげている会社だった。
ところが58年に戸田が死に、60年に池田が創価学会の第3代会長に就いてから、事態は一変した。
「池田は、これから戸田先生の関係はいっさい切ると宣言して、取引の継続を頼み込む北村さんの願いを頑として聞かなかった。」(甲賀)
北村は池田によってすべての糧道をたたれたのだから、精文館書店の倒産は当然である。連鎖的に甲賀が道義的な責任を負う58人分の貸し金回収も不可能になり、600万円の重荷はすべて甲賀1人の肩に掛かってきた。
「北村さんはその年のうちに、池田を恨んで憤死してしまった。病床では私にすまないと泣いて謝りましたが、池田がそれまで通り精文館書店に仕事を続けてさえいれば、すべてが順調にいったんです。何も倒産する状態ではなかったのだから。 しかも私が森重さんに戸田さんとのいきさつを何度話しても、森重さんは弁護士に会えと逃げるし、池田は知らぬ存ぜぬで、何一つ面倒を見ようとしない。北村さんの葬式では遺族に600万円は香典に上げますからといって、それから私は出資者への弁償のために無我夢中で働きました(甲賀)icon
-
from: 21世紀さん
2011/09/03 14:54:10
icon
「Re:池田大作の実像」
【日本正学館入社の"真相"】
************************************************************
山平(忠平)は戸田に言った。
「先生、山本伸一君です」
「わかっている」
山本伸一は、だまって履歴書を提出した。やや長い睫(まつげ)が、影を落とし、まだ少年らしい面影を残している。
戸田は、ていねいに履歴書をひろげ、仔細にじっと眼を注いでいた。(中略)やがて顔をあげると、微笑みながら山本をじっと見つめ、一言、こう言っただけである。
「頑張るか」
山本伸一は、間髪を入れず答えた。
「はい。おねがいいたします」
一瞬の気合いであった。決定的な瞬間である。時はすでに熟していたのだ。……1年前、戸田と邂逅(かいこう)したあの夏の夜……山本伸一が予感したことは、避けがたく、いま現実となって、立ち至ったのである。
(『人間革命』第3巻)
------------------------------------------------------------
戸田会長との"運命の糸"の強さを強調し、"どこの、誰の世話にならずとも、2人は出会い、師弟の契りを結ぶ運命にあったのだ"と思わせ、池田が入信当初から不思議な因縁の人物であったかのように脚色しているのがよくわかる。
●"鳴かず飛ばず"の信心だった池田大作を、戸田先生の日本正学館に連れていき、就職を斡旋(あっせん)したのは私の母でした。それまで池田は、蒲田工業会という小さなところに勤めていたんですが、私の母が「辞めたほうがいいんじゃないの」と声をかけて。
私の家は、戸田先生とはずいぶん懇意(こんい)にさせていただきました。目黒区白金の戸田先生のお宅にも、何回もおじゃましたし、先生の事業などにも協力させていただきました。そんな関係から、池田のことも気安く頼むことができたのだと思います。
けれど、それに対する感謝の言葉を、池田から聞いた覚えは、1度もありません。(三宅妙子『慧妙』H16.4.1)
-----------------------
三宅妙子さんの父親は地元・蒲田の支部長を務め、しばしば自宅で座談会が開かれていた。池田が入信を決意したという座談会場こそ、彼女の自宅だったのである。さらに、彼女は、池田の片思いの相手でもあった。(<恋文に認めたお粗末な「詩」>参照)
池田が恋文に認めたお粗末な「詩」
--------------------------------------------------------------------------------
―これでは入信神話もボロボロ総崩れ―
(『慧妙』H16.3.16・H16.4.1・H16.5.16)
入信後の池田であるが、信仰面、というより"成果"の面で頭角を現わし始めたのは、文京支部に派遣されてからのことで、昭和24年1月、戸田会長の日本正学館に入社するまでは、しばらく"泣かず飛ばず"が続いたという。
そんな池田だったが、"女好き"はやはり生来のものと見え、信心は"泣かず飛ばず"でも、女性に対してはマメに働きかけることを忘れなかった。その対象は、他ならぬ三宅妙子さんであった。
三宅さんの写真をほしがる池田に、三宅さんが不承不承、証明写真ほどの大きさの写真を1枚、渡したことがあった。
これに狂喜した池田は、その写真を肌身離さず持ち歩いていたという。池田は、そのことを、問わず語りで三宅さんに語っている。
●あれは、昭和23年頃、池田が20才頃のことだったと思います。「映画の券をもらったから」と池田に誘われ、2人で映画を観(み)に行ったこともあります。
でも私は、池田に対し、恋愛感惰を持つまでには至りませんでした。
つい最近、池田から当時もらった手紙が出てきましたので、手紙のやりとりをしたことはあったんだと、改めて思い出したくらいです。(三宅妙子)
-----------------------
そう言いながら三宅さんが見せてくれた池田の手紙からは、文学青年を気どりながら、何とか自分の"熱い想い"を伝えようとの池田の苦心が伝わってくる。
たとえば、三宅さんから写真をもらった時の心境・三宅さんへの想いを、池田は次のように書いている。
●賢女のphotoを無理に頂いた私の心境を!妙子さん、お互いに若いのです。未完成です。故に、完成を目指し未完成の歌を高らかにうたほうではありませんか。(池田のラブレター)
-----------------------
文学青年を気どる池田の、三宅さんへの想いは、文面からよく伝わってくる。ちなみに、池田の手紙には、次のような自作の「詩」が添えられていた。
体で見たことをゆう。
体で見たことを書く。
体で見たことを行ふ。
目で見て見えるか?
耳で聞いて聞えるか?
体で読んだものが本当だ。
体で祈ったものは実現する。
体で語ることは誰にも聞える。
体で悟った真理だけが我がものである。
爾(なんじ)の願いを高めよ。
爾の願いを潔めよ。
爾の願いを深めよ。
爾の願いを広めよ。
私欲を離れた願いならば死ぬまで願いつずけよ。
諦めるから叶わぬ。
応答を信ぜよ。
正しき願いは実現する。
想いを寄せた人に送った「詩」であれば、これは、推敲(すいこう)に推敲を重ねた、池田の自信作(?)なのだろうが、あまりに稚拙(ちせつ)で、とても詩などと呼べる代ろ物ではない。
さて、これと較(くら)べて、池田の「入信神話」に登場する、かの即興詩はどうか―。
旅びとよ
いづこより来り
いづこへ往かんとするか
月は沈みぬ
日はいまだ昇らず
夜明け前の混沌に
光 もとめて
われ 進みゆく
心の 暗雲をはらわんと
嵐に動かぬ大樹を求めて
われ 地より涌き出でんとするか
練りに練った自信作と、その場の思い付きで詠んだとされる即興詩。その、あまりの違いについては、小中学生の目にも明らかだろう。しかも、その「即興詩」たるや、当時の池田が知り得るはずのない、戸田会長が後年に作った『青年訓』にソックリなのである。
もはや、池田の入信神話がデッチ上げであることは、誰の目にも明らかであろう。
閑話休題。
こうした池田のアプローチを受けても、三宅さんはこれに取り合わなかったため、2人の関係は"信仰の同志"以上になることはなかったようだ。
それを逆恨みしたのか、池田は後に、三宅妙子さんに連なる人々を、ことごとく冷遇した。
●私はそういうことに無頓着(むとんちゃく)なので、人から指摘されるまでまったく気付きませんでしたが、言われてみれば、たしかに私たちは冷遇されていたようです。
でも私たちは、少なくとも学会に在籍していた当時は、池田から感謝されこそすれ、冷遇されなければならないようなことは、何一つしていないと思います。
そもそも、池田が戸田先生の日本正学館に入社できたのだって、私の母が「蒲田に、こういう青年がいるんですが」と戸田先生に取りなしたからこそなんですから。(三宅妙子)icon