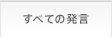サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: orimasaさん
2009/03/11 11:39:05
icon
日本周遊紀行(166) 延岡 「延岡版・西南の役」
写真:北川・表野の児玉熊四郎邸(西郷隆盛宿陣跡資料館)の西郷の最後の軍議の様子
可愛岳周辺は、「西南の役」における西郷軍の最後の激戦地であり、退却地でもあった・・、
現在、北川の「表野」辺りは実に長閑で雛びたところであり、時が止まっているような地である。 だが、明治初期の一時期、この辺りは一大騒乱の地であった。
可愛山稜の伝説の地から東側に沿っての表野集落の一角に旧邸らしい「岡田邸」があるが、元は児玉邸という邸宅であったらしい。 現在、この地は可愛岳への登山口になっており、、登山愛好者が集うところでもある。 併せて、ここには「桐野利秋宿営の地」と白の看板が立ち、更に、横に「可愛嶽突囲戦薩軍登山口」とある。 案内板の主文には『明治18年8月15日、和田越の戦いに敗れた西郷軍は、ここ表野に集結した。17日の夜には官軍の包囲網は完成していて、翌朝は西郷本陣を総攻撃する手筈になっている・・・』 とある。
児玉熊四郎邸は、当時、西郷軍の本陣であり最後の軍儀が開かれた所で、最後の決戦か、降伏か、あるいは鹿児島への脱出か、三者択一を迫られた場所であった。 本営地の頭上は、岩峰鋭い天険の山・「可愛岳」が聳えていて行軍には最大の難所であるが、それでも西郷は栄光の脱出行を決断し、選択したのである。 そして遂に西郷は、薩軍解散の命を出し、陸軍大将の軍服を裏庭で焼いて捨てたと言われている。 現在この場所は「西郷隆盛宿陣跡資料館」となっていて、西郷軍が最後の軍議を開いたときの様子が、人形(ひとがた)を使って再現してある。
「西南戦役」については先に熊本の項・「田原坂」でも記したが、熊本では谷干城司令官(土佐藩士、軍人・坂本竜馬の同輩)率いる政府軍がたてこもる熊本城に総攻撃をかけたものの城を落とすことはできず、頼みの田原坂の防衛ラインも分断され、田原坂も政府軍の手に落ちてしまう。この後、西郷軍の敗走が始まるのである。
政府軍に追われて右往左往する西郷軍は、矢部(現、上益城郡山都町)から「椎葉越え」をして人吉へ、更に、薩軍は人吉盆地での攻防戦を経て小林-野尻-高岡から宮崎と向かっている。(別働隊は人吉から米良村の横谷峠を越えて村所、一ノ瀬川沿いを宮崎方面へ)実に九州の脊梁山地といわれる急峻なる難所を踏破し、漸く(ようやく)にして現在の宮崎市広島1丁目近くの農家・黒木某宅に本陣を置き、約2ヶ月滞在している。跡地には「西郷隆盛駐在の地」として「敬天愛人」の石碑と案内板が当時の様子を伝えている。
しかし、そこにもそう長く落ちつくことは出来ず、佐土原-美々津と日向各地を転戦し、さらに延岡まで退却することになる。 延岡が官軍の手におちる直前、延岡の山中から五ヶ瀬川を下り、東海港(延岡市東海)を経て北川を遡り、野峰の吉祥寺(国道10、326号の分岐点)に入る。 隊士たちも続々北川・長井村に集結し、西郷軍は最後の決戦となる「和田越戦」の軍議を開き、この席で、西郷は「明日の和田越戦の指揮は、直接自分が執る」と伝えたと言われている。
「和田越の戦い」は、西南の役、最後の激戦地としても有名で、西郷軍三千に対して、政府軍は山県有朋指揮いる五万の大兵力であり、朝から昼過ぎまで灼熱地獄の中での死闘5時間続いた戦闘であった。しかし、善戦はしたものの多勢に無勢、所詮勝ち目はなく西郷軍は敗れて空しく敗走、再び北川の俵野に至る。 和田越は、現在、延岡市無鹿町の北側丘陵に当たり、北川西岸の国道10号線と日豊本線の和田越トンネルが抜けている。
和田越の案内板より・・、
『8月15日晴天、南洲翁は開戦以来初めて戦場・和田越山上に立つ。薩軍3,500は長尾山、小梓山、和田越、無鹿山に布陣し、樫山山上に立った。この戦い南洲翁死処を求めし最後の決戦なり。』
トンネルの入口には「西南の役・和田越戦跡」の標柱と、反対側の出口には野口雨情の・・、
『 逢いはせなんだか あの和田越で 薩摩なまりの 落人に 』
の歌碑や案内板が建っている。
西郷隆盛最後の本陣となった俵野の児玉熊四郎宅で最後の合議がなされたのは、時に明治10年8月15日であった。そして、8月16日、最終的に西郷が解軍を決意し令を出した。
『我軍の窮迫、此に至る。今日の策は、唯、一死を奮つて決戦するにあるのみ。此際、諸隊にして、降らんと欲するるものは降り、死せんと欲する者は死し、士の卒となり、卒の士となる、唯、其の欲する所に任ぜよ』
これより降伏するもの相次ぎ、精鋭のみ 1,000名程が残ったという、そして、8月17日の夜、可愛岳突破を敢行するのである・・、
先頭に2人の猟夫と数人の樵夫(きこり)を道案内に立て、険しい岩場や鬱蒼とした樹木の間をくぐり、傷だらけになっての山越えであったという。 実際に、この山を越えたのはわずか200名足らずだったそうで、あとはこの地で、官軍に投降したという。 その後、薩軍は、上祝子(かみほうり)、鹿川(ししがわ)、三田井(みたい)、七ツ山(ななつやま)、松平、御門と九州山地を南下するが、道なき道の山岳逃避行は故郷・鹿児島まで半月近く続いた。 そして、9月1日には懐かしの鹿児島に到着し、城山・岩崎谷において最後の籠城するも、同24日、西郷らは自刃し、ここに半年間に亘る西南戦争は終結するのである。
次回は、「九州山地」
日本周遊について・・、(gooブログ)
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005
【閑話休題】
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005/e/4dfa002b08cac15762829cf82b132ce0-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/10 11:50:49
icon
日本周遊紀行(166) 延岡 「可愛山陵」
可愛岳は、天孫・ニニギノミコトが降臨した後の御陵墓が安置する山であった・・、
日南海岸の青島より美々津に至る海岸は、約60kmにわたっては直線状をなした美しい砂浜海岸で特徴づけられる。 これは大淀川・一ツ瀬川・小丸川・耳川などの大きな河川によって運び込まれた大量の土砂が、 沿岸流と波浪の作用によって集積され、形成されたものであろう。 砂の堆積によって周辺は沖積平野を形成し、これらの河川の河口には発達した砂州が形成されている。
対して、北部地域の海岸線は、美々津より北の佐賀関あたりまでは、九州山地が海まで迫り、岬や入江や島が多く、沈水海岸(海面の上昇または地盤の沈降にもとづいて形成された海岸、河川にし浸食された陸地の沈水で形成される)で形成されたリアス海岸の様相を呈している。 特に、延岡以北の海岸は屈曲の多いリアス海岸で、急崖が海に臨み、沖合には大小の島々が点在する。
岩手の三陸リアス海岸もそうであったが、こんな地形の箇所はなかなか海岸へは近付くことが困難である。したがって、風雅な日南海岸を北上してきた主要国道10号線も、ここ延岡から北側は内陸の山地へ向かっている。 小生もこれに倣って国道10を行くようになる。
マラソンで有名な宗兄弟の旭化成、その赤白縞模様の巨大煙突を左に見ながら北川を渡り、その川沿いを走る。 左側にそう高くはないが裾野を大きく広げる山容が見える、気が付くとこの山は「愛可山」(あいらさん)という。 標高727メートル、この可愛岳は、ニニギノミコトが降臨した御陵墓伝説が伝えられてる山である。
先に、薩摩・川内の「新田の宮」でも記したが、古事記によると、天孫ニニギノミコトは高天ヶ原より「筑紫の日向の高千穂のくしふる峰」に降りてこられたと記され、日本書紀にはニニギノミコトが亡くなられた時「筑紫の日向の可愛の山陵に葬りまつる」と記されている。
可愛岳の西方、県境の地に高千穂峡でも有名な高千穂町があり、神話の町としても知られている。 天上界を治めていたアマテラスは、地上の国が乱れている事を知り、孫にあたるニニギを地上に降ろした。ニニギは多くの神を従え地上、日向・くしふるの峰へ降り立つが、この時、ニニギは千の穂を持って降りたとされ、言い伝えにより、この地を「智穂(千穂)」となずけられ、そして高千穂と呼ばれるようになったという。
町には、にはアマテラスが身を隠した天岩戸(洞窟)を祭る「天岩戸神社」があり、百万(やおよろず)の神々が集まって相談したと言われるところ「天安河原」がある。更に、古事記に「筑紫日向の久志布流多気・・、」と記されていて、ニニギが地上へ降り立った(降臨)の地とされている「くしふる神社」も存在する。 ニニギが降臨されたのが高千穂であり、その東方、大洋を見下ろし天上界のも近い「可愛岳」(727m)に御陵墓を鎮めたことは、説得力がある。
「可愛山陵」は、江戸期より調査がされて人々の関心を呼び、明治維新後、時の政府や国学者や宮内庁の調査によって可愛岳山麓の古墳が「可愛山陵伝説地」として認定されたともいう。
高く聳える可愛岳の頂上に「鉾山」といわれている所が御陵墓とされ、往時は、この山腹に社殿を営んでいたというが、人々の参詣に不便なため、さらに社殿をふもとの「江」(可愛)という里に移し、「可愛山陵大権現」として崇めて奉仕しているという。 寛政4(1792)年7月、高山彦九郎(1747-93年、江戸後期の尊皇思想家、寛政の三奇人の1人)は、可愛岳に登り、「筑紫日記」の中で記している・・、
『可愛村に着く。北川でみそぎをする。石橋を渡り、鳥井を入る。壱丁余(約800メートル)登って行くと山間に可愛山陵大権現の社殿が南南東に向かって建っている。ニニギノミコトを祀る。西の山を可愛岳という。これを山陵と伝えている。可愛岳山上迄一里(4キロ)の登りである』と・・。
この山は特徴的なのが、中腹より上部は巨石群に覆うわれ、更に、人工的なストーンサークルが存在するとされている。頂上に散見するこれら巨大石の石組は、原始石槨(せっかく:石でつくった、棺を入れる外箱。日本では古墳時代にみられる) とか弥生時代の立石(メンヒル)であるらしいと学者間でも言われている。
大正3年、考古学者・鳥居龍蔵は可愛岳頂上のこれらの巨石群を調査し、拝み石、鉾石、盤鏡などを一緒にして巨石遺跡としている。
可愛岳が、はるか昔から霊山として人々の祈りや儀式の場になっていたことが想像でき、初代・神武天皇の四代前の先祖というニニギノミコトは、日本が歴史を刻みはじめたとされる神話の世界の神である。 陵墓の存在は「伝説」の域を出ないものの、多くの巨石群と相まって御陵墓とされている所以であろう。 小さな可愛岳の陵墓は、大きなロマンをかきたててくれる。
旧道、日豊本線沿線の可愛の地に「御陵伝説地」の御陵と碑があり、野口雨情の歌碑には
『 こころして吹け 朝風夜風 ここは日向の 可愛山稜 』 とある。
【追記】
同じような伝説地とされる鹿児島県川内市の新田八幡宮にも、ニニギの御陵墓とされる「可愛山陵」があり、所謂、宮崎と鹿児島で御当地論争が起こっている地柄でもある。
次回は、延岡の「西南の役」-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/10 11:50:18
icon
日本周遊紀行(166) 延岡 「藩主・内藤家」
写真:鎌倉材木座「光明寺」の歴代内藤家の墓所(重文)
陸奥国・磐城平と日向の国・延岡の内藤家とは・・?、
国道10は日向市街の中心地、日豊本線・日向駅に達した。
市街地は海岸の方向に広がっていて、その町外れの海岸には壮絶な風景が広がっている。 通常、黒潮洗う太平洋に面した宮崎の海といえば、すぐにフェニックスロードと言われる長閑な日南海岸を思い浮かぶが、こちら県北部は日南海岸とは対照的な「日豊海岸」(国定公園)といわれる壮絶なリアス海岸が、日南とは勝るとも劣らない特異な景観を誇っている。 そのなかでも日向市西方郊外の絶景ポイントである「日向岬」は、特に、馬ヶ背(馬が背)といわれる付近一帯の岩が柱状節理の断崖絶壁を成し、越前海岸の「東尋坊(とうじんぼう)」をも凌ぐともいう。
日向駅から日向市街、日向岬、日向灘と日向ずくしのこの地は、町並みと自然のおりなす大景観が隣合った珍しい地域の一つであろう。
門川町から延岡に入った。
この「延岡」は小生の田舎・実家(福島県いわき市)と非常に縁が深いということが判明している。 「延岡」は水辺の町で、各河川が合流している水郷の町である。事実、「日本の水郷百選」にも選ばれていて、五ヶ瀬川、大瀬川、そして祝子川の清流を街の近隣に抱き、「水郷・延岡」の愛称でも人々に親しまれている。
この五ケ瀬川と大瀬川に挟まれた三角州・高さ50m余りの延岡山の山丘に縄張りしたのが平山城・延岡城である。 今は「千人殺し」と言われる城跡の石垣が、その名残を留め、城山公園として市民の憩いの場になっている。
最初に城が築かれたのは遥か遠くの昔・天平時代(奈良時代の後期)のことらしいが、江戸期まで下って1614年 (慶長19年)、有馬直純が島原から入封し、城および城下町建設に力を注ぎ、本格的城郭が完成している。 以降城主は三浦氏、牧野氏と替わり、延享4年(1747)・内藤正樹が七万石で入封すると、そのまま世襲して明治に至っている。
牧野氏の時代、牧野貞道(1719〜1747年までの日向延岡藩二代藩主、寺社奉行や京都所司代を歴任)の出世で経費が嵩み、藩財政は困窮するに至った。 そのため、江戸中期(1747年)の「三方領知替え」の制度により、牧野氏は常陸国・笠間藩に転封となり、代わって陸奥国・磐城平藩(たいらはん)より内藤政樹が7万石で入封した。 なお、磐城平藩には笠間藩より井上氏が入封している。
「三方領地替え」とは江戸期に徳川幕府が行った大名に対する転封処分の手法の一つで、大名三家の領地を互いに交換させることを言う。 例えば、大名家Aを大名家Bへ、BはCへ、CはA領地へ同時に転封することで、「三方領地替え」、「三方所替え」、「三方国替え」とも称した。 江戸時代を通じて何回か行われているが、中には、四家が関係した「四方領地替え」の例もあったという。
さて、話は飛んで、小生の実家・田舎、福島県いわき市(磐城藩)であるが・・、
江戸期においてはこの地方を磐城平藩と称して、鳥居、内藤、井上、安藤の四大名が領地を支配していた。 中でも内藤家は永く、江戸初期の1622年から1747年まで125年間、六代の永きに亘って治めていた。 内藤家は、徳川家譜代として戦国期より活躍し、大阪の陣では江戸城の留守居役を任されるなど、江戸幕府を開くにあたり功績は大きい。
江戸中期、六代目内藤 政樹の代の磐城平藩では、天地変による洪水や凶作、また過去の悪政などにより藩財政の破綻が続き、そのため重税で苦しめられた領民の不満が鬱積していた。そして、ついに元文3年(1738年)に「元文百姓一揆」と呼ばれる大規模な百姓一揆が発生するのである。 四方から平城下に押しよせた一揆勢は凡そ二万人ともいわれ、富豪や商家を打ち壊し乱入、 役所、獄舎をも襲ったという。4日間、武士団に抗し訴え続け、ついに減免措置を勝ち取ったという。 だが、この騒動で領主・内藤政樹は責任をとられ、日向・延岡藩7万石へ移封となり、磐城平を去ることになる。 去るに及んで次の歌を残したという。
『日に向ふ(日向) 国に命を 延べおかば(延岡)
またみちのくの(磐城平) 人に逢うべし』
こうして九州・日向延岡・内藤氏は、磐城平藩と同様の年月(124年)に亘り藩政を治めることになる。 江戸幕末、延岡藩・内藤家は、薩摩藩を筆頭に倒幕派の南九州諸藩の中にあって、徳川譜代藩であるがゆえに佐幕の立場を採らざるをえず、苦況に立たされるが・・。
このあたり、「鎌倉」(日本周遊紀行・特別編)の項でも記したが、内藤家・江戸上屋敷は江戸城外郭門の虎の門に続く外堀辺りにある。 内藤本家は磐城平藩より財政難の連続で、内藤貧乏の守・・と、そのあまりの質素な暮らしぶりを揶揄(やゆ・たとえ)されたほどのであったという。 しかし、七万石の小藩ながら、その後もなお私財をつぎ込み城下町の再興に尽くすなど、民衆に支持された名家でもある。
そんな生活ぶりの中、内藤家は代々「浄土宗」を崇拝信仰している。 菩提寺は鎌倉材木座「光明寺」で、寺院は徳川家康によって関東十八檀林(だんりん・栴檀林の略 仏教の学問所、平安時代の檀林寺に始まるが、学問所を檀林と呼ぶようになったのは室町末期で、近世、各宗で設ける、関東十八檀林の類、学寮のことでもある)の一つに数えられ、その筆頭に位置づけられた名刹である。 総門より、巨大な山門をくぐると本殿があり、その横奥に内藤家の廟所があって、磐城・平藩の初代から日向・延岡藩の幕末までの、代々の墓所が一同に祭られている。 このように江戸初期から末期まで、代々の大名の墓が整然と全部一箇所に揃っているのは大変珍しいという。 墓石が順よく並ぶ姿は美的でもあり、壮観であって、鎌倉市の史跡にも指定されている。
先にも記したが、延岡城の内藤家は日向灘の海を望める高台にある。 江戸住まいの日々、彼岸や盆の参詣のひと時には、内藤家の人々は鎌倉・材木座の海に重ねて、日向灘を思い出していたに違いないと思われる。
城址内の一角、延岡城の西の丸、もともと延岡藩主の御殿があった地に「内藤記念館」があり、延岡藩の歴史を伝える貴重な資料や書・絵画などが保管されているという。
次回、延岡の「可愛山陵」-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/09 11:45:52
icon
日本周遊紀行(165)日向 「美々津」
.
美々津は、神武天皇の「御東征」の出発地である・・、
ここは日向市である・・、
先の宮崎の項でも述べたが、「日向の国」の中心は古代は宮崎であり、中世から江戸期にかけては島津氏や伊東氏の居城であった都城や佐土原がその中心であった。 そして、古代神代の時代におけるここ日向の美々津は、神武天皇の「御東征」の出発地として知られ、初代天皇として名を残した神武天皇の伝説の地であって、古代の片鱗がここにも残るという。
「神武天皇」という名は有名ではあるが、近世に至るまで、天皇の名は諡号(シゴウ=おくり名)として後から付けられたものであって、その時代に人々にそう呼ばれたわけではなかった。 たとえば神武天皇の名前は本来、古事記では神倭伊波礼毘古命・カムヤマトイワレビコノミコト、日本書紀では神日本磐余彦尊・カンヤマトイワレヒコノミコトといった。 その他の呼び名もあるようだが、 神武天皇という名前は、彼の死後に送られた称号である。
ところで東征というと、東国、つまり我々の認識では関東や東北地方を平定したように聞こえるが、 邇邇芸命(ニニギ)の天孫降臨以来、九州に国家を構えていた天皇家(宮崎)にとっては、東国とは近畿地方あたりを指したようである。 即ち、この神話は九州に都を持つ国家の王が、近畿地方までを勢力下に組み入れ、名実共に大八島(オオヤシマ=日本全州)の中央を制圧したという事である。
神武天皇45歳のとき、宮崎市の皇宮屋(こぐや:神武天皇の居所、宮崎神宮・摂社)で東征のための軍議をなされ、大和へ向かうことを決心する。そして船出の地に選ばれたのがここ美々津であったと伝えられている。 この地から舟出した神武天皇一行は、沖に浮かぶ一ッ神と七ッバエと呼ばれる二つの岩礁の間を通って旅立ったとされ、その後、天皇一行が二度と戻られることがなかった。 因みにその後、この岩礁の間を通ると二度と戻れないとされ、現在でもこの間を通って沖に出る漁船はないといわれる。
出港後は、豊国(大分宇佐宮)、筑紫岡田宮(福岡芦屋)から阿岐の国(広島安芸)へ、そして吉備国高嶋宮(岡山)から瀬戸内海を経て、浪速(大阪)に入った。 浪速では、上陸を阻止しようとナガスネビコ(大和地方の豪族の長で、イワレビコの東征に抵抗したとされる)との戦いが行われ、この時、イワレビコは「日に向かって戦うことは不吉である」として更に、南の方へ回航しその後、紀州に回って大和に入ったとされている。 大和を平定した後に橿原宮(かしはら宮:奈良)で即位し、初代天皇となるが、この日が紀元節と言われる現在の2月11日とされ、つまり「建国記念日」である。
神武東征御船出の地として美々津港の右岸、耳川に面して「立磐神社」いう社が建っている。神武天皇東征の折、ここで戦勝と海上安全を祈願したといわれ、後に景行天皇の時代に、東征を記念して創建されたと伝わっている。 東征の船出を待つあいだ、腰かけていたという「腰かけ岩」も祀られている。
又、この社のすぐ近くに「日本海軍発祥之地」の記念碑が建つ。 神武天皇親率の水軍が初めて編成されて進発した地とされ、即ち、日本海軍は天皇が統治された海軍で有っことから、国が美々津の地を海軍発祥の地と定め建立したという。
『紀元二千六百年』 紀元2600年奉祝会選定(昭和14年日本放送協会製作)
金鵄(きんし)輝く 日本の
栄(はえ)ある光 身にうけて
いまこそ祝え この朝(あした)
紀元は二千六百年
ああ 一億の胸はなる
荒(すさ)ぶ世界に ただ一つ>
揺るがぬ御代に 生立ちし
感謝は清き 火と燃えて
紀元は二千六百年
ああ 報国の血は勇む
次回は、「延岡」
日本周遊について・・、(gooブログ)
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005
【閑話休題】
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005/e/4dfa002b08cac15762829cf82b132ce0
.-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/09 11:45:26
icon
日本周遊紀行(165)日向 「耳川の戦い」
九州の「関が原」と言われる「耳川の戦い」が・・、
国道10号線を快適に北上する。
川南町、都農町は日向灘に開けた明るい地域で、大部分が台地状の所謂、西高東低の、ゆるやかに傾斜した高台となっている。 広大な畑作が広がっていて、きっと南国豊かな農業生産が主体の地域であろうことが想像できる。
日豊本線を跨ぐように、直線の高架線が走っている。 以前になるが日豊本線の都農駅から美々津駅まで、リニアモーターカーの実験が行われていた所らしく、現在は、実験の舞台が山梨に移されていて、施設は取り壊されることなく現在もそこに居残っているのであろう。
まもなく、日向市に入り「美々津」という港へきたようだ、清流・耳川の河口に当る。
耳川は一般の川の趣きとは異なり、巨大な中州を持つ湖のような泰然とした川である。 川面は珍しく、青緑、エメラルドグリーン、黄緑と天候や見る場所によって色が変化する不思議な川だという、五色川ともいうべきか。 耳川は、九州山地(椎葉村三方山)に源を発し東へ向かって宮崎平野を流れ、日向市美々津町から日向灘に注いいでいる、長さ100kmの水系で美々津川とも呼ばれる。
この川に「幻の魚」と呼ばれる、「アカメ」という魚が生息することでも知られてる、スズキ目アカメ科の魚で、名前の通り目が赤く、北川、耳川のほか、高知県の四万十河口域など汽水域に生息し、体長1メートル、重さ20kの巨大魚になるという、地元では“マルカ”とも呼ばれているらしい。 尤もアカメは、ここ数年は魚影が見られなくなって、2007年には環境省のレッドリストの中の「絶滅危惧種」に指定されているとか・・。
往時はやはり「耳川」も河川流通路としての重要な地位を占めていたという。
江戸期、この地方の産物である木材や炭を高瀬舟で河口の美々津に集め、大型船・千石船で大阪方面に送り出していた。当時の美々津はそれら特産物の積出港として大いに賑わい、元禄年間には回船問屋や商家が数多く軒を連ね、「美々津千軒」とも呼ばれるほどの繁栄ぶりであったという。
現在、美々津、耳川の南部、国道10号線と海岸に挟まれた狭い一角は、江戸時代の回船問屋や明治、大正、昭和初期の商家などが数多く残されれており、当時の隆盛ぶりを知る事ができる。 中でも現在、日向市歴史民族資料館となっている元廻船問屋・旧河内屋は間口が広く、美しい京格子と白壁で当時の繁栄を偲ばせている。
この美々津の町並みは、1986年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されている。
耳川の中流域は「奥日向」とも呼ばれて、鄙びた景観を呈しているが、この周辺は古戦場としても今なお秘められた足跡を残している。 戦国期の天正6年、九州制覇を狙う豊後国の大友宗麟と薩摩国の島津義久が、日向高城川原(木城町)を主戦場として激突した合戦で、「耳川の戦い」とも云われる。
九州の覇者「大友氏」(九州探題)と九州南部に勢力をもつが北部への進出口を押さえられている「島津氏」、この両者が九州の覇権をかけて戦いで、主戦場は「高城」(現、木城町南部)と、そこを流れる小丸川を境に両軍は対峙することとなる。 激戦の末、勝敗は大友軍が三千余の将卒を失い、壊滅状態となって敗退した。 大友方は、さらに敗走する途中、城の北方の耳川で島津軍の迫撃に合い、戦死者の総数は二万人にも達したともいわれる。 結果は、島津氏が勝利し九州の覇権は島津氏に移って行くが、更にそのことが起因して、天下を平定しつつある豊臣秀吉の九州出兵を促す原因となる。 結末は秀吉軍が島津を抑えて、九州地方は平定されることになるのだが・・。
ところで、この合戦に島津勢が勝利した戦いを「耳川の合戦」と呼ばれるが、一方では、主戦場は耳川ではなく、宮崎県児湯郡木城町にある「高城」と城下の高城川(現在の小丸川)であることから、「高城の戦い」とするのが妥当とする向きもある。
耳川と高城川は、凡そ20キロの行程幅であるが、豊後地方に勢力をもつ大友軍から見ると、この耳川は南進北帰の生命線であり、そしてこの地で追撃する島津軍に完敗した地であることから、「耳川の合戦」が妥当であるとも言われる。
その後、九州攻略のため本州勢力の秀吉軍が大挙して島津軍を攻める際、この時の主戦場がやはり「高城」であった。この時、秀吉の先鋒として戦ったのが大友の残兵(大友義統)でもあり、結果、秀吉軍が勝利したため大友家は一国を安堵されている。 この戦も「高城の戦い」と称している。
次回は、日向・「美々津」-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/08 11:16:20
icon
日本周遊紀行(164) 佐土原 「野田泉光院・旅日記」
「厳重を極めたといわれる箱根の関所も、江戸後期ともなると・・、」 野田泉光院の「日本九峰修行日記」より・・、
因みに、作家・石川英輔氏の「泉光院江戸旅日記」の中で、小生の居住地である神奈川県厚木市近郊の“くだり”について記してみると・・、
『 文化十四年丁丑(ていちゅう)元年:西暦1817年2月16日・・五月八日(6月22日)〜十日(24日)鎌倉の主要な神社仏閣巡り・・・藤沢から寒川泊まり、 十一日(25日)相模一の宮(寒川神社)そして四之宮(平塚・前鳥神社)を参回している。 ここでお供の平四郎が二と三はいいんですかい・・と理屈をいったが、泉光院は無視している--平塚八幡、坂東札所・金目山(第七番・光明寺)へ参って納経印をもらいに行くと、住職に笈仏(箱に収まっている戒名)を開帳して欲しいと頼まれた。 長々、読経せられたり・・。石田村(伊勢原市石田)の浄心寺泊り。 十二日(26日)大雨なので、「憂きことの はてや旅路の 五月雨」と一句作ったら、住職が見て、それほど雨が難儀なら、もう1日いなされ、といってくれた・・、幸いなりと滞在す。かようなるときは発句も役に立つものなり・・。 十三日(27日)、アツ木(厚木市)へ出て相模川を船で渡り、相模国分寺(海老名市国分)参詣。坂東札所・星の谷(第八番星谷寺・座間入谷)の門前に泊まった。 十四日(28日)、坂東札所・飯山寺(第六番・長谷寺(厚木市飯山)、日向薬師(伊勢原市日向)に参り、門前に泊まった。 十五日(29日)大山不動尊(伊勢原市大山)に参詣、菖蒲団子というものを買うて数十匹の犬に食わす・・。 尾尻村(秦野市尾尻)の寺に泊めてもらう。 十六日(30日)十六日坂東札所・飯泉山(第五番・勝福寺 ・小田原市飯泉)参詣。酒匂川を渡って塚原村(同市塚原)泊まり。 十七日(7月1日)この家に笈(背負う荷物箱)を預けて道了尊(最乗寺)へ上って参詣す。――― 十八日(2日)箱根山を登って関所を通ろうとしたところ、引っかかってしまった。 役人「その方ども、江戸屋敷からの関所手形を出せ」 「われわれは日本回国の行者で往来手形はあるが、他には存じませぬ」 「 江戸屋敷へ行って頼むことが出来るはずだ・・」 「 江戸屋敷は存じません、又、お屋敷へ出るほどの身分ではございません」 「そのほうら名を何と申す・・」 「私は一葉坊、この者は合力助と申します」 「今回は内聞で通してやる、次回はそうはいかんぞ・・!!」 「へい・・」・・泉光院が名乗った一葉坊は俳号であった・・、役人とのやりとりが面白いし、関所も、そこそこいい加減であったことが判る。 』
以上本文よりであるが、神奈川県の鎌倉へ入って、箱根を出るまでの神奈川県央、県西部にかけて11日間を要している。 その気になれば山道を1日60kmをも平気で歩き通せる頑健な人であるが、この相模地方は意外とゆっくり、じっくり歩を進めていることが判る、見所が多かったのであろう。
因みに、坂東札所・星の谷(第八番・星谷寺・座間入谷)には、当時のメモ帳なる「つづれ草」が置かれていて、ここを訪れた泉光院のことが記されている。
『 「つづれ草」37号に書いた「野田泉光院」の廻国修験僧、日向の国・佐土原の泉光院が星谷寺に参詣した文化十三年五月十三日当時の住職は「周應」であったはずである。在住期間も長いし、過去帳を整備するなどの事績もあった 』、とある。
気が付くのは泉光院が記した『日本九峰修行日記』には文化十四年五月十三日とあるが、星谷寺の記録には文化十三年五月十三日になっている、丁度一年違いになっているが・・??。
佐土原は中世の頃、伊東氏から島津氏へと領主が代わっている・・、
鎌倉時代において佐土原・伊東氏は、鹿児島で勢力を伸ばしてきた島津氏と日向の支配をめぐって激しい戦いが繰り広げられ、徐々に島津氏が優勢となり、遂に伊東氏は豊後国へと追い払って島津の支配が始まる。 戦国期の最初の佐土原城主は島津家久、次いで江戸期には、その子豊久に引き継がれ、島津の支配体制が整っていく。 野田泉光院の全国行脚の時期は江戸後期であり、当時の佐土原は島津の支配下にあって、島津氏の相当の援助を戴いてもいる。
江戸後期の泉光院行脚中、伊能忠敬が「大日本沿海輿地全図」を完成しているし(1814年)、当時の文化・文政の時代(1800年前期)には、十返舎一九が「東海道中膝栗毛」初編を著し(1802年)、間宮林蔵が樺太を探検している(1814年)。 又、葛飾北斎の「富嶽三十六景」ができ(1832年)、歌川広重の「東海道五十三次」ができる(1833年)など、各階、各層の人々の諸国漫遊も盛んであったのである。
2006年1月「佐土原町」は宮崎市に編入、合併特例区(市町村の合併の特例)に指定されている。
次回は、日向・美々津
日本周遊について・・、(gooブログ)
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005
【閑話休題】
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005/e/4dfa002b08cac15762829cf82b132ce0-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/08 11:15:48
icon
日本周遊紀行(164) 佐土原 「野田泉光院」
野田泉光院は、西の松尾芭蕉とも呼ばれていて・・、
鎌倉末期の1335年、領主・伊東祐聡(祐明から4代目)は、佐土原町上田島の一角に「大光寺」を建立し、以降、伊東氏代々の菩提寺とした。 後に戦国期、領主が島津氏に代わると以降、島津氏の菩提寺になっている。 寺院は、国の重要文化財に指定されている名刹でもある。
この古寺・大光寺の山手の静かな森の一角に「野田泉光院」の墓がある。
「泉光院」は、佐土原の真言宗・安宮寺(新城地区に在った今は無き寺跡〉の八代目住職で、寺跡には、日本九峰修行供養塔があり、彼自身の墓は大光寺境内にある。 本名を野田成亮(のだしげすけ)といい、泉光院とは修験者の院号である。 当時の最高水準の知識人であり高僧だったという。
1811年(文化8)、56歳の時に斉藤平四郎という30代の男性を従え、6年2ヶ月にわたる全国の山伏寺を回る旅に出た。泉光院は、西の松尾芭蕉とも呼ばれていて、後に、『日本九峰修行日記』を著している。 日記は当時の庶民の姿を知る貴重な資料となっている。
作家・石川英輔氏が、野田泉光院の『日本九峰修行日記』を、ノンフィクションに訳して「泉光院江戸旅日記」を著している。
『泉光院江戸旅日記』の書が新聞の広告に出るなり、興味八百と旅好きの小生は早速買い求め、熟読し、大切な蔵書の一角を占めている。 副題には『山伏が見た江戸期庶民のくらし』となっていて、帯紙には表側に「文化文政の6年間、南は鹿児島から北は秋田まで日本を歩き回った僧・泉光院の見聞録」とあり、裏側に「泉光院の足跡⇒佐土原⇒宮崎⇒鹿児島⇒指宿⇒阿蘇山⇒長崎⇒名護屋⇒彦山⇒中津⇒小倉⇒長府⇒萩⇒広島⇒津和野⇒大山⇒鳥取⇒大江山⇒丹後半島⇒三方五胡⇒伏見⇒京都⇒福知山⇒姫路⇒大阪⇒草津⇒白山⇒金沢⇒能登⇒富山⇒野麦峠⇒松本⇒身延山⇒甲府⇒江戸⇒秩父⇒前橋⇒日光⇒浅間山⇒戸隠⇒立山⇒鶴岡⇒出羽三山⇒本庄⇒金華山⇒仙台⇒山形⇒那須野⇒筑波山⇒成田⇒銚子⇒鎌倉⇒箱根⇒下田⇒富士山⇒岡崎⇒岐阜⇒伊勢⇒白浜⇒和歌山⇒吉野⇒高砂⇒岡山⇒今治⇒大分 他」とある。
主人公は56歳で当時としては老年といっていい高齢であること。 執筆者の山伏は出発当時、高地位にある寺院の住職で、大先達という高位の山伏として日向一国の山伏を支配するという階級であったばかりか、佐土原の島津家の縁者として禄も受けており、佐土原では弓術の指導などもしていたという人物であった。
本人著書の『日本九峰修行日記』の興味深いところは、そのような有能な人物が敢えて貧しい人々の間を托鉢・修行をしていて、記録の中から当時の一般の人々、特に農民の生活の一端が伺えるあたりにある。 長いたびの間、斉藤平四朗というお供が付いているが、この男は佐土原の町人で、ある種、道楽人であったらしい・・?。
旅は経路を現在の地名と照らし合わせつつ、当時の一般の生活を浮き彫りにしようという主旨で書かれている。 この住職(泉光院)は6年間、ほんとにまめに日記を付けていたらしく、行程は本著の帯紙の通りで、南は鹿児島から北は秋田の本庄(本荘市)まで、日本中を歩き抜いている。更に驚くべきは、日本の名だたる山岳聖地を登攀しているのである。そのことは、彼が著した旅日記・『日本九峰修行日記』には、多くの山名も記載されている。作者は旅日記を「修業日記」と題したように、修業、参詣の宗教的目的をもって回国している。登山もこの宗教的目的の下におこなわれた。 回国修業の登山によって当時として一流の登山家とも考えられている。
山好きの小生としては興味あるところなので、その内容を記してみる。
野田成亮の日本九峰とは・・、
西より英彦山、石鎚山、箕面山、金剛山、大峯山、熊野山、富士山、羽黒山、湯殿山である。これらは何れも国内有数の山岳霊場で、世に知れ渡っている名山である。しかし、これら九峰修業の旅以外で、彼はもっと多くの山に登拝しているのである。
九峰以外の主な遍歴の山を列記すると・・、
九州・・阿蘇山 太郎岳(多良岳)黒髪山 求菩提山(くぼてやま)
山陰・・妙見山 大江山 三滝山(三岳山)
山陽・・後山 瑜伽(ゆか)山
近畿・・比叡山 朝熊(あさま)山 愛宕山
北陸・・白山 石動山 立山
東海・・光明山 秋葉山
信越・・浅間山 米山
関東・・行道山 中ノ岳(妙義) 八溝山 加波・足尾山 筑波山 鹿野(かのう)山
奥羽・・月山 鳥海山 金華山 水晶山
等等・・、
引き続き、「野田泉光院・旅日記」-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/07 18:59:32
icon
日本の紳士:「白洲次郎」
現在、NHKで日本の紳士:「白洲次郎」が放送されている。
女の城に日本の紳士がいた・・、
先の大戦(太平洋戦争)での敗戦の結果、占領軍が上陸して大臣、閣僚のお偉方が平身低頭して右往左往する中、ただ一人、占領軍・司令長官「マッカーサー」に「NO」といった男・「白州次郎」のことである。
宝塚、西宮郊外、芦屋は六甲の山裾が東、東南へ延びて丘陵地形造り、阪神地区のベットタウンとして発展している。 特に、芦屋地区は、当時は別荘地としても有名であった。 武田繁太郎の昭和30年代・芦屋マダムの生態を描いた「芦屋夫人」が猥褻(わいせつ)小説かどうかは別にして、当時流行の「有閑マダム」の代名詞になったのは事実である。 又、宝塚は宝塚歌劇団で知られる国内トップの、美しき女性専門の歌劇団の所在地でもある。
だが、ここでは女性の事でなく、実は男性の事なのである。
話は大きく転じて・・、
先の大戦(太平洋戦争)での敗戦の結果、占領軍が上陸して大臣、閣僚のお偉方が平身低頭して右往左往する中、ただ一人、占領軍・司令長官「マッカーサー」に「NO」といった男・「白州次郎」のことである。
白洲次郎は1902年(明治35年)、この芦屋に生まれている。
英国留学、更に英国赴任の時、駐英大使だった「吉田 茂」と面識を得、終戦時、英語が極めて堪能な彼は、終戦の始末を就けるべく吉田 茂の側近として、終戦連絡中央事務局(終連)の参与に就任する。
先ずエピソードを一つ・・、
彼は年末の或る日、天皇陛下からマッカーサー一家に贈るクリスマスプレゼントを託され、丁寧に手渡そうとした。マッカーサーは「その辺に置いておけ」というニベもない仕草を見せた。その瞬間、白洲は怒りを爆発させ、「いやしくもかつて日本の統治者であった者からの贈り物を、“その辺に置けとは何事か・・!”」と、そのままプレゼントを持ち帰ろうとした。驚いたマッカーサーは彼に陳謝し、テーブルを用意して鄭重に贈り物を置いたという。 これらの振る舞いにマッカーサー及びGHQは、白洲を「占領下、ただ一人の従順ならざる日本人」と評している。
GHQに従い、日本国憲法の起草に尽力した白洲は「この憲法はGHQによって創られたものであり、後に日本国民自身の手によって、作り替えねば、戦後は終わらない・・!」と称している。
彼の一言は重要である・・!!、あれから今日までの幾星霜、「日本国憲法」はどうなっているか・・??。
サンフランシスコ講和会議の吉田茂首相の演説の場面は、時折、終戦記念などでTVでも放映されているが、この時予定としてはGHQと外務省が用意した演説原稿を英語で話すはずだった。 これを知った白洲次郎は「日本は戦争に負けたのであって、奴隷になったのではない」と怒って、大きな巻紙に全文・日本語に書き換えて首相に渡したという。吉田首相に独立国の面子として日本語で演説するように諫言し、実際、首相は羽織袴姿でテーブルの前に立ち、大きな巻紙をクルクル開きながら日本語で演説していたのである。
白洲次郎は、185cmの長身、流暢な英語力、それに持って生まれた明晰な胆力で占領軍・米国首脳陣と対等に渡り合ったのである。そして条約締結、日本の独立が叶った時、秘書官として同行していた宮沢喜一(元総理)は、初めて白洲が泣くところを見たという。
吉田茂も、白洲を高く評価し「白洲三百人力」と呼んだ。
その後、白州は、少資源国日本が生き残る道として、産業政策を輸出主導型へ転換させようと、「通産省」を設立するなど白洲と吉田は一蓮托生となり、吉田が退陣すると自らも政界から姿を消し、実業界へと転進し活躍するのである。
幼なじみの作家・今日出海(こん ひでみ)に「育ちのいい生粋の野蛮人」と評された白洲次郎は、「葬式無用、戒名不要」の言葉を残して、1985年(昭和60年)、83歳で世を去った。
ところで、その日本国憲法は、1947年に施行されて以来改正されたことはない。
日本国憲法施行以来、自衛隊の合憲化や天皇性などを提言する側から、憲法草案がいくつも発表されてきた。そして、時の政権、自民党(自由民主党)の政策には、憲法改正が優先政策事項として挙げられ、「憲法改正草案大綱」なども作成しているが、いずれも保留又は撤回されている。
2006年、小泉総理から若手の安倍 晋三内閣総理大臣(2006年9月)へバトンタッチされてからは、彼の信条である憲法改正論議がようやく活発になってきた。 安倍総理は政策の中で、施行60周年を迎えた日本国憲法を改正すると宣言し、総理就任後の国会でも「現行の憲法は、日本が占領されている時代に制定され、60年近くを経て現実にそぐわないものとなっている、しかるに21世紀にふさわしい日本の未来の姿あるいは理想を憲法として書き上げていくことが必要と考えている」と述べ、日本国憲法の改正手続に関する法律案を、2007年の通常国会での成立を目指すとしており、 2007年夏の参院選では憲法改正を最大の公約に掲げている。
現在の総理大臣は代わりに代わって麻生太郎氏である。奇しくも麻生太郎は、当時、憲法草案に当たった吉田茂の孫である。果たして、吉田茂の側近であった白洲氏が、「GHQによって創られた日本国憲法は、作り替えねば戦後は終わらない・・!」と言わしめた現憲法の事が、麻生氏の頭の中に有るかどうか・・?、 見守りたい・・!!。 似たようなことは、北朝鮮における拉致問題(人攫い問題)や、三方における領土問題にしても同じである・・!。
日本周遊について・・、(gooブログ)
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005
【閑話休題】
http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005/e/4dfa002b08cac15762829cf82b132ce0-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/06 14:46:06
icon
日本周遊紀行(164) 佐土原 「佐野原聖地」
佐土原は、神武天皇の幼少時の名前・「サノハルノミコト」から起こった・・、
一ッ葉道路は、国道10号の交通渋滞を解消するバイパスとして主に海岸を北上して佐土原に至っている、別名「くろしおライン」ともいう。 北部地域には、隣接している「フェニックス・シーガイア・リゾート」のグリーン地帯があり、こちらは世界でも屈指の施設で、自然と環境を備えた世界に誇れるリゾートだと当事者は自認しているようである。 因みに、シーガイアとは、英語で海を意味する「Sea」と地球を意味する「Gaia」を組み合わせた造語である。
昨夜は、この道路のP・Aで夜を明かした。
車には柔らかな朝日が入り込んでくる、今日もいい天気のようである。 海岸へ出ると陽光が海面に反射して一寸眩しいくらいである、陽気のわりに打ち寄せる波は大きく白の飛沫を上げている、やはり日向の海である。
朝日に見送られながら出発すると、一ッ葉道路は間もなく海岸から離れて10号線に合流する、ここは既に佐土原である。 九州流に言うと“サドバル”であるが、こちらは“サドワラ”と読むらしい。
佐土原は、「神武天皇」が誕生された地とされている・・、
佐土原町上田島地区の小高い丘・・、昼なお暗く鬱蒼と茂る木々の中に、ぽつんと小さな「社」が鎮座している。 この地が「佐野原聖地」と呼ばれる聖なる地というが、賽銭箱などはなく、扉に掛かる鍵は壊れかけていて、まるで森の中に放置されたような空間、年月から無視されたように建っている。 後に、大和の国を平定した人(神)が生まれた場所にしては、あまりに寂しいのである。
佐土原は、始めサノハルと称し「サノハルノミコト」(サノノミコト)は、神武天皇の幼少時の名前である。 この社は、都於郡(とのこおり:現、西都市)から宮居を遷し、鵜茸草茸不合命(ウガヤフキアエズ)が天下を治め、玉依姫命(タマヨリヒメ)を妻に迎えたとされる地で、後に神武天皇が生まれた場所でもあるという。日本の初代天皇の聖地としては余りに粗末であると思われるが・・?。
鎌倉期に、源頼朝から日向国・地頭職に任命された工藤祐経が佐土原を支配し、この時期に佐土原神社が創建されたといわれる。工藤氏は姓を本来の姓である伊東と変えながら、400余年に亘り、この地の支配体制を確立している。 第10代・伊東義祐の頃には佐土原城を中心とし日向・四十八城を支配したともされている。
日向・飫肥の項でも記したが・・、工藤祐経は鎌倉のお膝元で起きた「曽我兄弟の変」の主たる登場人物で、当の本人は兄弟の仇討ちで殺されてしまう。
では何故、佐土原の初代領主なのか・・? 鎌倉期、既に領地を与えられてうたが、祐経本人は鎌倉の地で頼朝の信任厚き重臣として務めを果たしているのであり、領地の管理は、その代官が行っていた。祐経亡き後、その子伊東祐時の四男祐明、つまり工藤祐経の孫が現地に赴いて実質拝領し、初代「田島氏」と称した。 佐土原は、当初は「田島の庄」とも呼ばれていたからである。 佐土原城は、戦国期に伊東氏の中心的城郭となり伊東義祐が居城した頃が全盛期と言われる。
戦国期、島津氏の大軍は、伊東氏の本拠である佐土原を目指して進撃を開始し、戦況不利と見た義祐は、戦わずして退却し、豊後の大友氏を頼い、大友宗麟はその要請をいれて伊東義祐らを庇護した。 その後、大友軍は島津軍と戦ったが敗戦、兵を退くところを追撃され「耳川の戦い」で潰滅的敗北を喫し、こうして、大友氏も一気に勢力を失墜することになった。
奇しくも、伊東氏の出実は伊豆の「伊東の荘」であり、大友氏の出実は相模の小田原の「大友郷」である。 奇しくも伊豆と小田原は隣接していて、東国の雄は親しく九州でも隣国同士となり、共に滅び去ったのである。 そして滅ぼした当の島津氏も大元(初代都城:島津忠久)は頼朝のご落胤との説もあり、この三者とも頼朝のお声がかりで、九州の平家残党の抑えとして派遣された共通目的があり、これも歴史の面白さであろう。
次回は、引き続き佐土原の「野田泉光院」について
尚、本文とほぼ同じ内容で、「gooブログ」にも掲載しております。(追加文有り)
日本周遊紀行 佐土原・「佐野原聖地」 http://blog.goo.ne.jp/orimasa2005/e/301a03654625b49a3414282682ac7343-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
-
from: orimasaさん
2009/03/06 11:24:19
icon
日本周遊紀行(163)宮崎 「グッバイ・ファミリー」
宮崎F・Tの岸壁には、既にマリンエキスプレスが接岸していた・・、
宮崎自動車道から宮崎市内へでる・・、
今夜、ここ宮崎フェリーターミナルから最後の航海と言われる「マリン・エキスプレス」が出航するとのことで、我等の家族もこの船で帰路出航することになっている。出航が午後8時頃とのことで、先ず、宮崎のF・Tを出向いて下見と出航手続をすることになる、手続といっても乗船券に交換するだけだあるが。
未だ、たっぷり時間があるのでお土産や夕食をとる事になったが、さてどちらへということになり、結局、かって知ったる宮崎空港へ行くことになった。 大淀川を渡り返して空港へ向かう、やはりフェリー埠頭とは違って空港ターミナルは賑やかであり、お土産屋も食堂、レストランも充実していた。
夕闇が迫り、町の明かりが灯る頃、一時を過ごしたエア・ターミナルから再びF・Tへ戻る。 空港とF・Tは、宮崎市街の中心を流れる大河・「大淀川」を挟んで其々対岸に在り、一ツ葉道路という宮崎道と直結した湾岸を通る道路で、空港やF・Tを結んでいる。
宮崎 F・Tは、白の四角い事務所の手前が駐車場になっていて、(乗船用ではない)その横つまり事務所の正面の海側に、岸壁をつなぐ大きな道路が走っている。 つまり、ターミナル事務所とフェリ-船は直結されてなく、乗船の際はこの大幅の道路を横断して勝手に乗り込めということらしい。 しかも、事務所玄関から船着場までは、そこそこの距離があり、お年寄りやヨチヨチ歩きの子供は大変だろうことが想像できる・・!、車優先の人間無視の造りである。
岸壁には既にマリンエキスプレスが接岸していた。 人の気配も先ほどより、さすがに多く、孫たちに「あの、大きい船に乗るんだよ・・」と言うと、既にハシャギ回っている。 乗船の客は、既に土産の大きな荷物を抱えて各自待機しているようで・・、その内、乗船の合図があり、各自、一目散に船へと向かう、元気のいい人は駆け足である。 実は急ぐ必要があったのだ・・、二等船室はフリースペースの部屋なので、より良い場所を確保するためである。 我等も幼時三人と80歳の老婆を引き連れて、それでも、急ぎ足で向かったが、やはり思ったとおり最悪の状態になったようである。
指定された二等船室のスペースは、既にコーナーなどの良場所は人が満ちて、中程の中途半端なスペースのみが残されていた、心配していたことが的中してしまったのである。 小生は娘に、駄目を承知で「空き個室」の有無を確認するように言いつけた。 早速、娘と上さんが、実際の交渉に出かけたようだ。 我らは、孫の為にデッキへ出て見物と洒落こんだが、余りの船の大きさに孫たちはピンときてないようである。 「ジジはここでお別れだから、元気でお家へ帰るんだよ・・」、孫達はキョトンとして「ジジ、どうして帰っちゃうの、どうして船から下りちゃうの・・、」と怪訝そうである、父親が説明に躍起であった。
ところで、カーフェリーは、昨今の交通網の発達や原油高騰などの煽りを受け業績が悪化し、分社化や廃止を余儀なくされている。 宮崎カーフェリのマリンエキスプレスは、2005年6月の川崎港発の宮崎港行き(京浜航路)の最終航海をもって、航路は全て休止となっているらしい。 今回の乗船は最終航路の記念として、特別に旅行会社がツアーを企画したものであった。「マリンエキスプレス」は、総トン数・12000t級、全長200m弱で速力25ノットの仕様らしい。
因みに現在、船の大きさは総トン、排水トン、載貨重量トンなど、船の容積や重量であらわされている。 総トン数とは、船の大きさを表すもので「トン」という呼称が付くが、船そのものの重さを表しているわけではなく、船の容積を基に算出したものである。 数字が大きいほど、その船は大きく、商船や漁船などでもっとも広くつかわれている。 他に載貨重量トンとは積める貨物、燃料、清水などの重さをあらわし、おもに貨物船や原油タンカーなどでつかわれている(積載総量)。 又、排水トン数は船の重さをあらわし、船を水に浮かべたときに押しのける水の総重量で表され、主に軍船などでつかう。
日本では昔、船の大きさを五百石船とか千石船というように、積むことができる米の石数で表していた。 当時の日本経済は、米を基準の物指しとしてたので、石数であらわすほうが便利だったからである。明治時代になり、貿易がさかんになると国際化が進み、トン数であらわすようになった。
船や飛行機の速度単位は「ノット」と称して、国際標準の速度の単位であり、時速何海里かということである。 つまり、1ノットは1時間に1海里進む速さと定義されている。 1海里 = 1852メートルなので、1ノットは1時間に1.852キロメートル進む速さとなる。 ところで1海里は、地球上の緯度1分(地球の円周:約40000Km÷360度÷60分)の長さに等しいとされ、航空機や船舶は地球上を長時間航行するので、地図上では非常に判りやすい単位となっている。 因みに、毎時25ノットを換算すると、25ノット*1.852km=46.3km/時である。
航海の無事を祈って皆々と別れ、小生は下船した。
かなりの高位にあるデッキから可愛い孫たちが、絶叫に近い声で別れを惜しんでいて、何かジーンとくるものがある。 天候は良さそうなので、きっと、いい船旅ができるだろう、それを祈るばかりである。 別れを惜しみながら、レンタカーを返却するため再再度、空港方面の大淀川の一ッ葉大橋を渡り返す。
大淀川は、河口に近いこともあろう、1kmにも及ぶ川幅一杯に満々と水を湛えて、滔々と流れ下る。川は、九州でも五番目に大きい川で、その源を鹿児島県に発し、各支流を合わせつつ都城盆地を貫流して宮崎平野を潤し日向灘に注いでいる。
往時、陸上交通の未発達の頃、大淀川は流域で生産された物資などを舟を使って河口まで運ぶ行路であった。 河口部に位置する赤江港(河口の南側地区)からは更に千石船に積み替え、江戸や大坂へ運んだという。 特に、内陸に位置する「都城」は日向地方の中心地であり、交通路は大淀川の船便に頼ったという。 しかし、この川には難所が在った、都城盆地の北部「轟」地区というのがあり、その名の通り「白浪、厳に轟く」と言われるほどで、船を止めてしまうほど「瀬と滝」があったという。 江戸期、都城領主であった島津久倫(しまずひさとも)は、激流のなかで開削の難工事を三年がかりで完成させ、都城から大淀川河口まで舟の通行を可能にすることができたという。(寛政の開削工事)、
空港近くのレンタカー事務所で車の返却手続中、娘から電話で「個室の申し込みは首尾良く『特等室』が二部屋取れました・・!」と喜びの連絡が入った。 小粒の孫三人と年寄りを抱えての船旅なので、何よりもホッとしたところである。
レンタカーの事務員に温泉施設の有無を確認したところ、幸いにすぐ近くに「がらっぱの湯」というスーパー銭湯が在るとのこと。 「がらっぱ」とは、日向、薩摩地方で「河童」のことらしい。 早速、その「河童の湯」を訪ねると、自前の温泉ではないが、岩風呂には霧島温泉の湯を直送しているとの事であった、ご苦労さん・・!。
心身サッパリしたところで、今夜の泊まり場は久しぶりに愛車内とした。
次回は、佐土原-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-