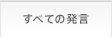-
from: わかさん
2010/05/31 05:43:30
icon
うた声・天国に参加してきました。
昨日は、行きは3時間半かかって電車で立川のうたごえに
参加してきました。
初めてから一年半くらい経つそうです。会を重ねることに
参加者が増えているようです。
驚いたのが伴奏者がPCを見ながらアコーディオンを伴奏していました。
それに東京方面は、歌集もなくOHPで壁に歌詞を映し出すのが
主流で、こちらもそうでした。それも2箇所もやってくれていました。
さらに こちら2時間に拘らずに 3部形式も主流のようで とても
歌った気がして良かったです。
ありがとうございました。
会場になったところの市民会館です。
-
from: わかさん
2010/05/30 05:30:52
icon
大盛況に終わりました
181名の参加で大盛況に終了しました。
小川さんをはじめ田口さん、真下さん、宇野さんの最強メンバーでありがとうございました。
お蔭様で太田の”出前うたごえ”も44回も回を重ねられました。
これも一重に参加される皆様のお蔭です。延べで五千人を越えました。
会場の利便性や色んなことを乗り越えて 現在は、今の会場に留まっています。
ましたさん、うのさん 初参加をありがとうございました。是非、次回の11月にもお出でくださいませ。
50回までに カウントダウンに近づいてきましたね!
今日は、これから”立川・うたごえ天国”に参加してきます。
-
from: わかさん
2010/05/29 05:21:35
icon
文化の質を落とさずに
【社説】
iPad発売 文化の質を落とさずに
2010年5月28日 東京新聞
米国で「電子書籍」の普及が加速。日本でも、アップル社の端末「iPad(アイパッド)」の発売が二十八日から始まる。本の概念を変える電子の本は何をもたらすのか。文化の質は守りたい。
電子書籍は本の内容がデジタル化され、データの形になっており、端末の画面に表示して読む。
米国ではここ数年、「iPad」のほかに、ネット通販のアマゾンの「キンドル」、ソニーの「リーダー」などの端末が発売された。どれも片手で持てるほどの大きさで、iPadは縦二四センチ、横一九センチ、厚さ一・三センチ、重さ約七〇〇グラム。通信機能が付いていて、ネットワークを通じて「本」が買える。千冊を超える本のデータ保存ができ、大きな文字にも変えられる。グーテンベルクの活版印刷以来の本の革命といわれる。
今は英語の本が中心で、日本語の本への本格対応はこれからになるが、出版界への影響は小さくないとされる。
電子書籍は紙も印刷も製本も要らない。極端にいえば作者から読者への“産直”も可能で、安価で販売できる。
実際、「キンドル」は、二五〜三〇ドル(二千五百円前後)するハードカバーの小説を九・九九ドル(約九百円)で発売している。原価を割る戦略的な安売りらしいが、安さを印象づけた。
ただでさえ経営が大変な出版社、取次、書店は、一層苦しくなるかもしれない。一冊の本ができるまでには、たとえば、取材、編集者の協力、デザイン、写真、校正などさまざまな仕事が積み重なる。費用もかかるが、一つの文化を形成してきている。出版の主導権が一部の巨大企業に独占されれば、良質な本はなくなるとの懸念もある。
今年三月に発足した官民合同の懇談会と大手出版社の団体が、著作権を含めた電子書籍のビジネスモデルや、日本語の電子書籍の書式などの検討に入った。作り手にも読み手にも良い対策をお願いしたい。
文化の保護に熱心なフランスでは、定価制を電子書籍にも広げる法案が年内にも提出されるという。大手書店は資金を出し合い、販売システムの開発にも取り組んでいる。
もともと日本では、ソニーが世界に先駆けて端末の開発に取り組んだことがある。守る一方ではなく、電子書籍ならではの本作りに挑戦するなど利便とアイデアも競ってほしい。
-
from: わかさん
2010/05/28 05:34:22
icon
時事川柳 他
2010年05月26日(水) 川越市 宮本祐二 TBSラジオ
「8ヶ月 かけて辺野古に 帰る鳩」
普天間移設先は辺野古周辺?
筆洗
2010年5月27日 東京新聞
過日、発表されたサラリーマン川柳二位の作品は<「先を読め!」 言った先輩 リストラに>だった
無論、先、即(すなわ)ち未来をご存じなのは神だけだが、それを想像する力を持っている動物も人間だけとか。この先どうなるかと、常に気をもむのは私たちの宿命である
最近、景気回復の兆しを思わせる指標も多く、やれやれと思っていたら、また株安だ。直接原因はともかく、日本経済のこうした不安定さの根本問題は外需依存体質にある。裏返せば、内需のひ弱さ では、なぜ日本人は財布のひもを締め続けるのか。言わずもがな、将来が不安だからだ。ある調査では大学生の65%が「日本の将来に夢や希望を持てない」。内閣府の調査では今後生活が「よくなる」と考えている人は6・6%しかいない。この不安を和らげないではどんな手を打っても焼け石に水だ
一足飛びに「明るい未来」が来ないのはみな承知している。今、政治に必要なのは予想される困難も痛みも示した上で、それを乗り越えればこんな希望が見えてくるはずだ-というデザイン、行程表を掲げることだろう
だが、歴史的選挙で生まれたはずの現政権も、“先”の選挙を気にするばかりでそれを示せていない。<先を読め 読めるわけない 先がない>とは、やはりサラリーマン川柳六位の作。こんな状況に無策な政権にこそ先はないだろう。
フォト:アマリリスが満開になったので 急いでロビー展示に持っていきました。
-
from: わかさん
2010/05/27 06:03:33
icon
第二段 事業仕分け
◆事業仕分け25日の判定結果◆
25日の「事業仕分け」の結果は次の通り。
【日本森林林業振興会、日本森林技術協会】収穫調査業務、素材検知業務=実施機関を競争的に決定。事業規模は縮減
【林道安全協会】国有林林道等交通安全管理業務=実施機関を競争的に決定
【全国農林統計協会連合会】登録調査員等講習会委託事業=廃止
【農村環境整備センター】田んぼの生きもの調査=廃止
【全日本トラック協会】都道府県トラック協会からの出捐(しゅつえん)金による事業=見直し
【道路保全技術センター】路面下空洞調査業務=実施機関を競争的に決定
【司法協会】裁判記録等の謄写費用の支出=価格の見直し
【矯正協会】刑務作業協力事業、物品取扱事業=見直し
【労災保険情報センター】労災診療費審査体制等充実強化対策事業=実施機関を競争的に決定。事業規模は縮減
【雇用振興協会】雇用促進住宅管理運営及び譲渡・廃止援助業務=実施機関を競争的に決定。事業規模は縮減
【日本ILO協会】国際技能開発計画実施事業=廃止
【女性労働協会】女性と仕事総合支援事業=廃止
(2010年5月25日22時22分 読売新聞)
このほか日経新聞では:
交通安全協会では、自動車免許証を持つ人が八万人いて 更新時に
手数料を募るし、
教則本は1400万冊を作り32億円の収入を得ている。
この辺も理詰めで指摘した。
フォト:名前が分かりませんが上高地に沢山咲いていました。
-
from: わかさん
2010/05/26 05:45:16
icon
ドラマチック・アイロニー
筆洗
2010年5月25日 東京新聞
観客には分かっているのに、登場人物は気づいていない。映画や演劇ではよくある設定だ
▼そういう皮肉な状況を英語では、ドラマチック・アイロニー(劇的アイロニー)というらしい。最近の民主党、わけても小沢幹事長の振る舞いには、ちょっとそれを疑う
▼例えば、夏の参院選に向けたマニフェストに消費税増税を盛り込むかどうかで民主党は迷っているようだ。財政再建重視の幹部は積極的だが、小沢さんは慎重らしい。一方、幹事長は、郵政民営化見直し法案は今国会で最優先して成立させる考えだ
▼少し前には、いったん凍結した地方の高速道路建設を進めよと政府にねじ込んだ。その財源確保のため、政府は実質値上げの料金案をひねり出したが、悪評頻々とみるや幹事長はそれにもダメを出した
▼個々に“公式”の理由はあろう。だが、名にし負う「選挙至上主義者」。消費税であれ郵政であれ高速であれ、あらゆる言動には、今この国のために、より、とにかく参院選の得票のために、「得」とみればゴー、「損」ならストップの文法が透けている
▼確かに、小沢流で恩恵を受ける組織や人から得る票も多いのだろう。だが、その票目当ての算盤(そろばん)ずくを嫌気して離れる人より多いのだろうか。小沢さんと、この窮地に彼を恃(たの)む民主党の戦略は「劇的アイロニー」なのかどうか。答えは、夏になれば分かる。
フォト:乗鞍、畳平の 鶴ヶ池
-
from: わかさん
2010/05/25 05:35:31
icon
会長に就任
[人 インタビュー]抜粋
<日弁連 会長に就任>
とても素敵な考えの方の 宇都宮健児さんです。
「年越し派遣村」名誉村長から日本弁護士
連合会の会長へ。4月の会長就任後も、子ど
もの貧困をなくす集会などに顔を出します。
背広の襟を飾る、ひまわりとお化けのバッ
ジ。ひまわりは、正義と自由を表す弁護士の
しるし。お化けは?フヒンキー”と言っ
て反貧困運動のキャラクターです。貧困は日
本最大の社会問題であり、人権問題です」
いまも「反貧困ネットワーク」代表です。
* *
生まれは愛媛県の豊後水道に面する旧明浜
町。父親は戦争で米軍機に撃たれ、足か不自
由に。戦後は半農半漁の貧しい生活でした。
「朝も夜もいっしょに漁に出て小舟の櫓
(ろ)をこぎ、夜はそのまま舟で寝る」という
生活。小学生のとき、大分県に開拓農家とし
て入植。くわで林を開き、畑を作りました。
親は教育熱心。中学校は熊本市の叔父宅か
ら通いました。
「立身出世し貧しい親を早く楽にさせたい
と東大法学部に進みました。目標は官僚か大
企業への就職でした」
大学入学後、人生を変える本に出合いまし
た。一冊は部落で育った女性が半生を平仮名
でまとめた手記。貧乏で学校にいけず、おと
なになってやっと字を覚えた人です。もう一
冊は閉山した炭鉱の子どもの詩などをまとめ
た本。。親に泥棒をさせられるのは嫌”とい
う詩を読みました。
「自分よりもっともっと貧しい人がいる、
とショックを受けた。立身出世で、自分たち
だけ楽になるのは卑怯(ひきょう)では?」。
貧困で苦しむ人たちのためになる職業は何
か。いきついたのが弁護士でした。
* *
〜〜中略〜〜
「幸福な人は自分でも権利を守れる。社会的経済的弱者は
自分の人権を守れない。弱者の味方をするのが弁護士の使命です」
と〆ていました。
フォト:ボケてしまいましたが 大正池から河童橋までいたるところにさいている「エゾムラサキ」
-
from: わかさん
2010/05/24 05:30:21
icon
焦点は次の市民判断
【社説】
小沢氏再不起訴 焦点は次の市民判断
2010年5月22日 東京新聞
政治資金疑惑がかかる小沢一郎民主党幹事長を東京地検は再び不起訴とした。検察審査会の一回目の議決は「起訴相当」だった。これから始まる市民による二回目の審査の行方が最大の焦点となる。
疑惑の核心は、資金管理団体「陸山会」の政治資金収支報告書の虚偽記入事件に対する小沢氏の関与である。
小沢氏は東京地検の三度目の事情聴取で、あらためて否定した。元秘書ら三人も小沢氏の明確な指示を否定した-。
検察審査会の「起訴相当」議決を受けた再捜査で、検察が不起訴の結論を出したのは、そうした理由からだ。
今後は改正検察審査会法に基づき、自動的に二回目の審査に入ることになる。十一人の審査員のうち、八人が「起訴相当」と議決をすれば、裁判所が指定した弁護士により「強制起訴」する運びとなる。八人に満たなければ、不起訴が確定する。
問題は一回目の議決に加わった市民のうち、五人の任期が七月末まであり、審査会に残る点だ。二回目の議論は別のメンバーで行われるべきではないだろうか。新しく入った審査員との“情報格差”が生まれる問題点もある。
法的見地からの助言を行う審査補助員の弁護士も、一回目とは異なる人を充てた方がよい。会議が非公開なため、助言が適切かどうか、チェックできないからだ。
「民意の反映」が検察審査会の役目であり、むろん検察官とは異なる視点があってよい。だが、同じ証拠なのに、その評価が検察官と市民とで分かれたことに違和感を覚える人もいる。より公正を図る意味で、審査会は市民も弁護士も一新して、民間人の良識を示す結論に導いてほしい。
検察の再捜査が、審査会の議決から一カ月程度で終結したことは、拙速との批判が出る恐れもある。結論を急いだのは、審査会に下駄(げた)を預けたのかという憶測さえ生みかねない。ゼネコンマネー疑惑はどうなったのか。検察も説得力ある説明がいる。
小沢氏は一貫して「潔白」と主張している。不起訴といえど、検察審査会の二回目の議決を受ける身でもある。自ら政治倫理審査会に出席する意向を示しているが、「陸山会」の土地取引や原資の四億円について、進んで資料などを示し、詳細に語った方が、国民の納得を得られるのではないか。あえて証人喚問に応じ、潔白を証明する道もあろう。
フォト:上高地の ニリンソウ
-
from: わかさん
2010/05/23 05:46:51
-
from: わかさん
2010/05/22 04:47:40
icon
インドで児童労働撤廃
<インドで児童労働撤廃に取り組む>
「日本の人口を超える子どもたちが、インドで働か
ざるを得ない生活を送っている」
インド南部バンガロール市で児童労働をしていた子
どもが共同生活する「ボーンフリーアートスクール」
を運営。二十三日まで講演で日本各地を回る。
世界の児童労働は二億人以上。その半数がインド
だ。五年前に設立したスクールは、子どもが演劇や絵
画などの芸術活動で得た収入で暮らし、読み書きを学
び、自立を目指す。
親がアルコール依存症だったり、虐待された子ど
も。「自由に表現することで傷をいやしていく。路上
で盗みをする子どもに罪があるのか。爆弾を作る大人
は罪に問われないのに」
根底にあるのは平和への願い。「子どもの幸せを考
えることは、ガンジーの非暴力につなかっていく。イ
ンドでも憲法九条ができるのを願っている」。広島の
被爆者との交流から作ったパフォーマンス「白い
花」。ヒンディー語で歌いながら、苦しみ、逃げ感つ
惨状を踊りで表現する。
子どもたちと今、「平和の預言者」と題したドキュ
メント映画を制作中で「オスカーを狙っているよ」。
五十三歳。 (奥田哲平)東京新聞5.21付け
ジョン・デバラジ -John Devaraj-
彫刻家、画家、演劇家、音楽家、フィルムメーカー、写真家、ライター、建築家など多岐分野に渡り芸術家として活躍。インドにて25年以上、芸術を通して子どものエンパワーメントを目指し児童労働問題に取り組んでいる。また、平和問題、ダリット問題(カースト問題)、女性問題などにも取り組む。 2000年NY国連本部にて開催された「子ども兵士会議」や2004年フィレンツェで開催された「児童労働世界会議」のアーティスティックダイレクターとしても活躍。児童労働の現場に踏み込んだドキュメンタリーフィルム「歴史の旅(History Expedition)」(2006年作成)がサンフランシスコ国際ショートフィルムフェスティバルにて選ばれる。 2007年よりピースボートにてシンガポール〜インド間の海路にて児童労働及びアートの役割について講演、パフォーマンス、ワークショップを行う。2008年にはアーティストとして生きる被爆者の方へのインタビュー及び撮影を行う。現在「平和の預言者(Prophets of Peace)」と題した証言ドキュメンタリーフィルムを制作中。また同年にはバンガロール〜ラホール間を自転車で旅する平和サイクルラリーをリードする。インドの子どもたちがパキスタンの子どもたちへ書いた平和メッセージの手紙7000通を集めた。日本の憲法9条をインドに広めようとする活動も開始。広島・長崎の原爆をテーマにしたダンス劇「白い花(White Flowers)」を発表(2008年)。以来、インド6大都市にて50回以上公演。またバンガロール市、コーチン市、バロダ市に佐々木貞子さんの千羽鶴をイメージした平和モニュメントを作成し、各都市に寄贈した。ボーンフリーアートスクールの創設者。
今日は、これからY旅行のツアーで バス旅行で上高地地方に
行ってきます。