サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: mukururu - 2さん
2015/04/15 08:24:05
icon
母が天国にお引越ししました
難病専門の医療療養型病院に入院していましたが、4月11日深夜に旅立ちました。2月25日から肺炎を繰返し、早期治療で乗り越えていました。しかし4回目の肺
難病専門の医療療養型病院に入院していましたが、4月11日深夜に旅立ちました。
2月25日から肺炎を繰返し、早期治療で乗り越えていました。 しかし4回目の肺炎では回復出来ず、抗生剤と維持液の点滴のみで命を繋いでいました。
母は経管栄養、高カロリー点滴等の延命治療は明確に拒否していましたが、末梢点滴は延命治療に含まれないらしく1日1000リットルと抗生剤600リットルを点滴したため浮腫が進みました。
仲良くなった看護士に確認すると、低栄養の体に長期間点滴をすると、更に浮腫が進み最後は少しの刺激で皮膚がはがれたり、見るも無惨な患者さんがたくさん居ると教えてくれました。
その後、主治医や看護部長と話し合いを繰返し、4月9日の朝に点滴を外して貰いました。
それから母は呼吸も穏やかになり、旅立ちの時、ベットサイドにいた私でさえ気付かず眠るようなお別れでした。
点滴を中止した事、いまでも正しかったか?自問自答していますが…
母が望んだ「ロウソクの灯が消えるように逝きたい」は叶えられたように思います。
延命治療に関して様々な考え方がありますが、末梢点滴まで含めて書面にした方が良いかな?と思い、母のケースを投稿しました。
サークルの皆様、ありがとうございました。
1日も早くCBDが完治できる日が来る事を心から願っています。
from: ヨシさん
2015/04/17 07:16:59
icon
お母様のご冥福を心よりお祈りいたします。mukururu-2さんも長い間本当にお疲れ様でした。介護の結果に正解不正解はありません。自問自答を繰り返しな
-
from: mikekoさん
2015/04/20 08:05:38
icon
療養病床へ
再度の肺炎で入院していた父ですが、先週、実家のすぐ近くの医療療養病床に転院しました。せっかく入所した特養は2ヶ月で退所…という形になりましたが、やはり
再度の肺炎で入院していた父ですが、
先週、実家のすぐ近くの医療療養病床に転院しました。
せっかく入所した特養は2ヶ月で退所…という形になりましたが、
やはり遠いのは母にとって大変だったので、今度は通いやすい立地を一番重視しました。
幸い、建物もきれいで明るく、先生も穏やかな物腰で感じの良い病院です。
父は前の病院から経鼻栄養を続けていますが、少しでも再度口から食べることが
出来るよう、口腔ケアを丁寧にしてくださっています。
延命治療の問題は難しいですね。
父の場合、認知症症状もあるので胃ろうは出来れば避けたいな、とは考えますが、
声を掛けると頭をこちらに向ける父の姿を見ると、迷います。
美味しいゼリーや摩り下ろしたフルーツを早く食べさせてあげたいな。
最近は週2ペースで通っています。
-
from: ヤマセミさん
2015/04/14 11:14:01
icon
血液脳関門をすり抜けろ!
春から少し時間が逆戻りして、気温の低い日が続いています。今日も薄日が差すことはありますが、空気が冷たいですね。季節の変わり目、体調には要注意です。「血
春から少し時間が逆戻りして、気温の低い日が続いて
います。今日も薄日が差すことはありますが、空気が
冷たいですね。季節の変わり目、体調には要注意です。
「血液脳関門」を突破する方法の研究が進んでいる、
というニュースがありました。
「血液脳関門」とは、人間の脳の働きに決定的に大切な
脳神経細胞を、有害物質から本能的に守るバリアー機能の
ことです。例えそれが病気を治す治療薬であっても異物と
みなし、脳を守るように出来ているのです。
4月14日(火)付日本経済新聞のニュースからです。
アルツハイマーやパーキンソン病などの脳の病気を治療
するために、届きにくい脳の内部にまで的確に治療薬を
運ぶ技術の開発が進んでいます。
名古屋大学はミクログリア細胞を使って、東京大学は
アミノ酸を使って、この血液脳関門を突破する技術を開発
しました。神戸学院大学は血液脳関門は使わずに、鼻の
粘膜から嗅覚神経を使って脳内に薬を送る技術を開発
しました。
効果が期待できる病気は、アルツハイマー型認知症・
パーキンソン病・脳腫瘍・統合失調症・多発性硬化症などが
あります。
iPS細胞研究と連動して、治療薬の開発と治療薬の効果的
な脳神経細胞への投与技術の開発に期待してます。




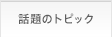




from: ユッキーさん
2015/04/22 23:44:05
icon
私も父が亡くなってから一年半が経ちますが、いまだにあれで良かったのか、こうした方が良かったのではないかと、考えることがあります。そんな事を考えている時