サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: jackさん
2015/12/09 11:35:54
icon
発症から8年目を迎えて現状と希望と課題
発症からこれから8年目を迎えますが、現状と来年の希望、課題について、症状や進行度合いは十人十色と言いますが何か参考になればと投稿します。発症時期:20
発症からこれから8年目を迎えますが、現状と来年の希望、課題について、症状や進行度合いは十人十色と言いますが何か参考になればと投稿します。
発症時期 :2008年暮れ
確定診断時期 :2010年3月都内の大学病院でCBDの疑いあり、但し、PSPの疑いも残る、症状は歩行困難と開眼失行、以降定期的に大学病院を受診。
国立病院入院検査: 2014年7月、大脳全体に軽度の委縮が見られるが 大学病院での前回の検査内容と差異はほとんどない、CBDとPSPの混合型とも考えられる、ゆっくり変化していくタイプとも考えられる、との説明をうけました。
現在の通院先:国立病院、地元の総合病院の神経内科、
現在の介護保険レベルは要介護1。
2012/7 要支援1, 2013/6 要支援1、2014/12 要介護1、2014/11 要介護1,
2016/11更新予定で多分2は必至。
昨年の指定難病更新手続きは4(0~6)と認定。
現在服用薬: Lドーパ、1錠/日(従来1日6錠服用から徐々に減量)、アーテン3錠/日、シンメト レル3錠/日(今後も主治医と相談しながら減量したいと思っています)
今までトライした事項: 鍼治療、漢方薬数種類、血液クレンジング、グルタチオン点滴、ナルトレキシン服用、クロレラ飲用、HALロボットリハビリ(通院先で)、ACSIVE歩行機購入、ルームランナー購入、大腿部への麻酔注射(通院先で)、ドブス服用(通院先で)
効果が顕著な事例: 開眼失行がボ国立病院でトックス治療で劇的に改善し現在も継続治療中です。
介護保険: 車いす、歩行器、椅子(座面後部が上下して立ち上がり動作をヘルプ)
ベッド周りの手すり、玄関上り框手すり、ヘルパーはまだ利用していません。
リハビリ: 年1回、総合病院で2~3か月PTのリハビリ、同じPTさんにリハビ
リを受けています。 都度リハビリ医から弱点、課題を指摘されそれに対応する
リハビリ内容を追加し、自宅でほぼ毎日、PT,OT,STのリハビリを実行しています。
国立病院での検査で前頭葉の血流が少し低下しているとの指摘があり、任天堂の
脳トレゲームを取り入れています。
最初の転倒: 2012年9月
以降平均転倒回数: 月2回~3回、
転倒の主なる原因: 竦み足症状が出て、足が出ないのに上半身が前方に動こうとする
ことで転倒していることと、椅子の真ん中にすわらずその姿勢で斜め方向に何かを捕ろうとし たりして、耐力が少ないためかそのまま崩れ転倒してしまうケースが多い。 また椅子に座ってから下の物を拾えばいいのに、先に拾おうとして前傾姿勢からそのまま崩れ落ちているケースも多い。
国立病院の重心可動域の検査で、前後左右への体の傾斜反応テストを受けて、(結果はグラフで表示される)普通よりもかなりレベルが下がっているので、そのことは理解しているはずなのにいくら注意しても、注意事項を守ろうとしないのが頭痛の種です。
主治医からもこの病は注意力や、集中心が欠ける、落ちていくことが特性としてあるのでやはり周囲の者がしっかりとサポートする必要がある、と言われています。
大腿骨頸部骨折手術(室内での転倒による): 2013年8月、
再転倒による脱臼や再手術を防止のため大転子を防護するインナー式のセーフヒップ
プロテクターを着用しています。
転倒手術以降の歩行状態: 2013年8月転倒前に海外旅行で杖をつきながら12,000歩も歩 行出来ていましたが、転倒して手術してからは、極端に歩行状態が悪化しています。
進行していたから転倒したのか、転倒してから歩行状態が悪化したのかよく分かりませんがとにかく転倒しないように最大限の注意配分をするように、室内の障害物を除去したり、転倒しても最悪な状態を回避するような工夫をすることが大切だと痛感しています。
生活環境: 二階屋で夫婦と愛犬、二階に寝室と陶芸工房(妻の)、洗面所/トイレ
一階はリビングと台所、トイレ、風呂/洗面所、リハビリ室
二階へは階段昇降機を設置して付き添いながら安全確認をしています
室内歩行: リビングではレッツゴーミニ(歩行器)を使用、その他の場所では手すりに
掴みながらの歩行、
散歩 : 公園散歩のときは車いすで行き、園内で空の車いすに愛犬を乗せて(錘がわ
りに)車いす押し歩行。
症状と現状:
①歩行で特徴的な症状は、①竦み足がでること②一定の歩幅で歩行が出来ず不規則になる ので転倒のリスクが多い③踵から着地、つま先で蹴る、いわゆる正常な歩行が出来ず、脚底全体で着地しています。 そのため時には脚がフリーズして上半身から崩れる。(一人歩きは不可能な状態です)
②声の出が悪い(小さい、弱い)、いわゆる構音障害がある、
③字体がかなり小さくなってきている。
④日常生活では、食事は普通の食事を、多少ゆっくりですが、出来ています。
⑤歯磨きやトイレ等も何とか時間がかかりますが、一人で出来ています。
⑥風呂も時々トラブルがありますが、いろいろ工夫(手すり等の増設)や入浴方法の徹底化を指導してなんとか一人で出来ています。
⑦着替え動作もぎこちないですがなんとか時々助けながらできています。
⑧ベッドへの出入りもゆっくり時間をかけて一人でしています。
⑨寝返り動作もゆっくりですがなんとか出来ています。
⑩体全体で言えることですが、固縮はほとんど見られない状態です。
椅子からの立ち上がりもある程度座面の硬い、高さのある椅子を、また介護保険のレンタルで、立ち上がり時腰部分が上がり下がりするものを使っています。
いろいろな工夫:
*室内履きを底がペロッとしたもの(スリッパ類)を止め、そこがある程度しっかりし
た靴を履かせている、これは国立病院のPTさんからのアドバイスで足元をしっかり。
*家の中いたるところに手すりを30数か所設置、必ず手すりを掴んで行動するよう徹底。
*風呂場、洗面所、陶芸工房、寝室等からトラブッタ時や用事がある時リビングへの連絡手段 として、一方通行のワイヤレスコールチャイムを6個設置。 待機姿勢をとってます。
*安全行動のための注意喚起のため、床にテープで、方向表示やSTOP等の指示を示す。
*階段の踏板が出っ張っているところに転倒時顔面をぶつける恐れがあるので、柔らかいクッションを巻きつけて防護体制
*玄関の上り框辺りに隙間にペットシートを並べて置いて万一転倒した場合に床顔面/頭部衝撃を緩和する仕組み
*安全動作を守るよう都度都度注意しています
外出:
外出は一人では不可能なので、車いすで出来るだけ連れ出すようにしています、
陶芸教室、友人との昼食会食、絵画館鑑賞、デパート等
悩み事は、駅のエレベーターの有無や場所の情報がなかなか分からないのと、トイレが多目的トイレが必要で、確保に注意が必要なことと、天気次第で雨の日は予定が組めないことです。
来年の目標
*安全動作に積極的に介入して現状維持が出来るよう頑張る。
*来年末に陶芸作品の展示会があるのでヘルプしながら頑張る。
*症状安定のために何らかの効果的なものがあるかどうか検討する。from: jackさん
2016/01/05 09:36:00
icon
骨折した時点では小生は外出中でしたので詳細は不明ですが、二階の洗濯物を整理しようとして持ち運んだ際ハンガーにつるしてあった長めのタオルに足を踏んでしま
-
from: ヤマセミさん
2015/12/30 11:45:07
icon
「慶応大病院(東京)にiPS外来」
2015年も終了してしまいますね。患者本人さまにもご家族さまにも、いろいろとあったと思う1年ですが、来年は、少しでもいいことがありますように!一日一回
2015年も終了してしまいますね。
患者本人さまにもご家族さまにも、
いろいろとあったと思う1年ですが、
来年は、少しでもいいことがありますように!
一日一回笑顔の瞬間がありますように!
みなさん、ふぁいとです!
「慶応大病院(東京)にiPS外来」
慶応大病院(東京)は、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の研究について
難病患者の疑問に答える専門の「iPSコンサルテーション外来」を来年1月に
設置する、と発表しました。
同外来ではパーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)など14種類の
難病に関して、遺伝性の病気や幹細胞を研究する医師らが最新の研究や、
将来の治療の見通しなどを情報提供する予定です。
尚、診断がつかずに悩む患者に対応する「未診断疾患外来」も設ける予定
です。かかりつけ医からの紹介を受けた患者から血液5ミリ・リットルを採取
したうえで、遺伝子を分析することで診断を試みるとのこと。
「iPSコンサルテーション外来」・「未診断疾患外来」ともに、
現在の掛かりつけ医からの紹介状が必要になります。
詳細は、下記「慶応大学プレスリリース」へ
http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2015/osa3qr000001axvx-att/141224.pdf
-
from: ヤマセミさん
2015/12/18 11:12:34
icon
不整脈・ぜんそく治療薬で神経細胞の減少を防ぐ
不整脈・ぜんそくの治療に使われる薬が、アルツハイマー病で起こる脳の神経細胞の減少を防ぐ効果がある、とのマウスの実験結果を、国立長寿医療研究センター・理
不整脈・ぜんそくの治療に使われる薬が、
アルツハイマー病で起こる脳の神経細胞の減少を防ぐ効果がある、
とのマウスの実験結果を、国立長寿医療研究センター・理化学研究所が
発表しました。
アルツハイマー病患者の脳の中では、神経細胞内において、
「タウ」と呼ばれるたんぱく質が異常に集まり、細胞が死ぬことが知られています。
そこで、不整脈・ぜんそくの治療に使われる「イソプロテレノール」という薬剤が、
この「タウ」が集まるのを抑えることを発見したとのこと。
認知症のような症状のあるマウスはそのまま経過観察すると、3カ月後には
その神経細胞が11〜28%減少するが、「イソプロテレノール」を投与したところ、
3カ月後でも減っていなかったという。そして、脳機能の低下や行動の異常も
抑えられたとのことです。
大脳皮質基底核変性症(CBD)患者の脳内では、
(「大脳皮質基底核変性症(CBD)診療とケアマニュアル」より抜粋。)
http://plaza.umin.ac.jp/neuro2/cbd.pdf
「CBDで亡くなった患者さんの脳をくわしく調べてみると、脳の中にタウとよばれる
蛋白質がたまってきていることがわかっています。タウという蛋白質は、正常な
状態では神経細胞の中の骨格となる線維をつなぎ止める役目をはたしていて、
安定した構造を保てるようにしています。CBDではこの蛋白質に異常がおき、
正常な状態ではたまってこないタウ蛋白が溶けにくい状態になって、
神経組織にたまってくることがわかってきました…」とあります。
「イソプロテレノール」という薬剤が、アルツハイマー病患者の脳内で起きている
状態と同様に、CBD患者の脳内でのタウ蛋白質の異常蓄積にも効果がある
ことがわかると、治癒ではないがその進行を止められるかも知れませんね。
研究を望む。
-
from: youさん
2015/12/16 22:26:27
icon
あおいそら さんへ ご報告
あおいそらさん10月26日から1.5Lのお茶(水)を飲んだご報告です。私の場合、毎日出る、とはならず、効果は有りましたが限定的でした。それでも①クスリ
あおいそら さん
10月26日から1.5Lのお茶(水)を飲んだご報告です。
私の場合、毎日出る、とはならず、効果は有りましたが限定的でした。
それでも ①クスリに頼ることが減ったこと ②2~3日で出る回数が増えたこと が効果
としてあげられると思います。
一時帰国している時に、水けはカウントして、毎食後に200ccのお茶を飲み、何だかんだ
で1日1L以上(1.5Lではなく)飲めば効果は変わらないことを発見したので、今はこう
してます。
1L(以上)のお茶で効果が有ったことを感謝すると共に、私同様便秘に悩まされている
人の参考になれば、と思います。
YOUfrom: あおいそらさん
2015/12/18 23:42:15
icon
毎日でなくても、ちゃんと体が答えてくれましたね。よかったです
-
from: ヤマセミさん
2015/12/09 22:15:31
icon
空気式歩行支援シューズ
最近は、いろんなタイプの歩行支援装置が研究・開発されています。ACSIVE(アクシブ)、HAL(ハル)などなど。。そして、先日ニュースで見たのが、「空
最近は、いろんなタイプの歩行支援装置が研究・開発されています。
ACSIVE(アクシブ)、HAL(ハル)などなど。。
そして、
先日ニュースで見たのが、「空気式歩行支援シューズ」なるもの。
岡山大学大学院の高岩昌弘准教授の研究チームが開発しているようです。
まだまだ研究・開発途中ですが、興味深いですね。
「空気式歩行支援シューズ」
「モーターなどの電気系の動力は使わずに、靴底に内蔵した空気ポンプを
自分自身の体重で踏むことにより生まれる空気圧を使って筋肉の代わりとなる
ゴムを伸縮させて、地面を蹴る力を増幅させるシステムです。」
ACSIVE、HALの様な大掛かりのものではないところが魅力です。
詳しくは、
「装着者の体重を利用した空気式歩行支援シューズ」で検索してみて下され。
お寒い季節になってきました。
身体が強ばってのつまずき、転倒には気を付けましょ!-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-




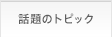




from: youさん
2016/01/06 12:05:12
icon
Jackさんコメントをどうもありがとうございました。横転びして強打したのですね、私も気をつけます。YOU