サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: ぽっぽさん
2025/10/06 13:47:23
icon
◆ 戦後80年その4 ◆
◆ 戦後80年その4 ◆
【戦時の性暴力と向き合う】 8月下旬の記事です。
= 被害者つながり あげた声 = 山本めゆ氏(社会学者)
・岐阜県の「ある町<記事には具体的な町名がありますがここでは非表示とします>」から「旧満州(中国東北部)」に渡った満蒙開拓団関係者に聞き取りを続けてきた。
この開拓団は敗戦直後に現地住民から襲撃にさらされ、旧ソ連将校らに警護を頼み代償に団の未婚女性約15名を性の相手として差し出した。
(公開中のドキュメンタリー映画に描かれている)
・故郷に戻った団員は外には「女性のため」として事実を伏せつつ、「汚れた女」と中傷した。
「戦後の方がつらかった」と書き残した女性もいる。
・そんな二次被害に屈しなかった女性が求めたことにより、現地で亡くなった女性たちを悼む「乙女の碑」が1982年に建てられ、数人が取材に応じ活字にもなった。
・2013年には長野県の満蒙開拓平和記念館での<当時の性被害者の>講演が実現した。
日本の戦時性暴力の被害者が実名で聴衆を前に経験を語ったのはおそらくはじめてだ。
遺族会は<20>18年に碑文を建て、除幕式で戦後生まれの遺族会長が女性に犠牲を強いたこと、戦後の対応についても謝罪した。
・<上記の>岐阜県の町では同年代の女性が同時に被害を受けたことも手伝い、<長野県の遺族会と>深い絆で結ばれて交流が続き支えあった。
・女性が声をあげ、地殻変動を起こした例がもう一つある。
<20>19年に始まった「フラワーデモ」で、性暴力の根絶を求める人びとが、ただ語りただ聴く。
それが性犯罪事件の裁判に影響を与え、「刑法改正」を後押しするまでになった。
つながることの力を物語っている。
= 光あて 監視、記録、忘れぬ = 越智 恵(おぢめぐみ)氏(国際法学者)
・性暴力が国際法上の犯罪と明確化されたのは、第2次世界大戦を経てからだ。
1949年に採択された「ジュネーブ諸条約」は強姦・強制売春を戦争犯罪だと規定した。
ただ、このときはまだ「名誉に対する侵害」という位置づけで、被害者個人の痛みを伴うものだという認識がかけていた。
・転機は90年代の旧ユーゴスラビア内戦とルワンダのジェノサイドだ。
民族浄化を達成する手段として組織的強姦や強制妊娠などの性暴力が使われ、国際社会に衝撃を与えた。
二つの国際法廷ができ、戦争犯罪や「人道に対する罪」といった国際法上の犯罪としての処罰が行われた。 <では、沖縄における米兵による強姦事件はどうなのでしょう?>
・規範はつくられる一方、性暴力が亡くならないという現実があるが、減らしてゆくためには、加害者に性暴力は重大な結果が伴うと思わせることだ。
その一つが刑事訴追だが、他にも国連やNGOが行っているように、性暴力を監視し記録し忘れないということを示し続ける事にも意味がある。
<「示し続ける」だけではなくて「加害者に対して厳しい処罰」をすべきだと思います>
= 今と地続き 私たちの問題 = 深沢 潮(うしお)氏(小説家)
・戦争には必ず性暴力や性搾取がついてきて、「慰安所」を設けた旧日本軍は言うまでもなく他の国の軍隊にも似たような暴力はあった。
沖縄では今も米兵による性暴力が問題となっている。
・戦時中に朝鮮半島から沖縄に連れてこられた慰安婦について、証言を聞いたり資料を読んだりして来て感じたのは「今の私たちの生活と地続きだ」ということだ。
・その背景には貧しさや植民地支配など構造的な搾取や暴力が存在していた。
その姿は<深沢氏>自身の体験とつながる。
<深沢氏が>小説家を目指していたときも、小説家になってからも、「原稿をみてあげる」などと性を取引材料のように扱う男性が何人もいた。
・性被害を告発すれば「うそつき」「売名」というバッシングが待っている。
そういうものに苦しんできた私が沖縄の慰安婦の話に触れた時「これは自分の問題でもある」と感じた。
・過去も現在も「男性優位」の社会では、性暴力は弱い立場の女性に向かい、権力を持つ男性は女性をモノのように扱ってきた。
それは性欲というより「支配欲」だ。
・戦争という国家による支配や権力勾配(こうはい)、性差別、貧困など、背景になった者は今の世界にも存在する。
そう捉<とら>え直せば、「私たちの問題」として考えることができる。
一人ひとりの経験や苦しさを小説で拾い上げ、戦争と性暴力を「女性の権利」という視点で語る社会への道を開いていきたいと思う。
【沖縄 聞き取られなかった声】 「戦後80年」最後の9月下旬の記事です。
謝花(じゃばな)直美氏(歴史研究者・ジャーナリスト)
ー 記者時代から謝花氏が追いかけるテーマは「聴きとられなかった声を聴く」という作業で、沖縄で生まれ育ち、女性の視点からそして「異音」に耳を傾け、見えてきたものは何だろうか。 ー
<登山リーダーから頂いた新聞記事の「戦後80年シリーズ」の最後です。>
= 戦争未亡人の抵抗 気持ちまで失わぬ ミシンに願いを込め =
▲「聴きとられなかった声を聴く」という問題意識はこれまでの仕事に貫かれているが?▼
・1990年に沖縄タイムスに入社したが、男性記事が見ている世界と自分が見ている者が違うという感覚を感じた。
<19>95年9月、米軍兵士3人による少女が暴行される事件が起きたが、基地問題が女性の人権問題だという認識が社内で広く共有されていたかは疑わしかった。
・「第4回世界女性会議(北京会議)<国際連合創設50周年に当たる1995年9月開催>」から帰国したばかりの「高里鈴代氏(当時は那覇市議)」が中心となり、「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」を立ち上げたので、<謝花氏は>高里氏の動きを追い取材した。
高里氏達に「基地の問題を女の問題に矮小化するな」という批判が向けられた時代だった。
男性記事中心の新聞作りにも通じるものがあったと思う。
・沖縄のメディアは基地問題と政治・経済の関係については精力的に報道している。
ただ、沖縄戦と米軍の占領、復帰と続く中で、「そこに生きた庶民の微細なひだのような経験や記憶」が聴き取られていない。
戦後史をきちんと書ける記者になりたいという思いで、「ジャーナリストと研究者の二足のわらじ生活」が始まった。
・記者として、本土復帰までの観光ブームを支えた「琉球人形」をテーマに取り組んだ。
私が子どものころ、「琉球人形」は人気の土産物だったが、今は店頭で見かけることがないので調べ始めるといろんなことがわかってきた。
占領初期の配給時代に少しでも多くの食料を得ようと、「戦争未亡人」を中心とした女性たちが米兵向けの土産として作り始めて、次に取り組んだのが「ミシン」だ。
・「ミシン」を踏んで生計を立てた女性たちも米軍基地のために「土地を奪われた地域の人々」や「戦争未亡人」だった。
生きるために手内職でつくった「既製品」を露店で立ち売りして、那覇市内の「新天地市場」いう場を獲得して復興を担った。
= 急速に進む軍事化 住民目線の歴史観 本土には「異音」か =
▲<19>48年8月6日、戦時の未使用砲弾125トンを積んだ米軍の上陸用舟艇が伊江島の港で爆発し、住民ら107名が死亡、100人以上が重軽傷を負ったこの「事件」を<謝花氏は>追ってきたが?▼
・40年以上後の記者1年目に記事を読んだが、すざましい死傷者数なのに、施政権返還前は補償問題として遺族の声が断片的に紙面化されたたけで島外では忘れられた事件だった。
・沖縄の社会が長く事件を記憶することが出来なかったのは沖縄戦と占領が生んだ砲弾の危機が続く中で起きたという根本をとらえきれなかったことにあるのではないか。
▲今年<2025年>5月、「西田昌司参議院議員(自民党)」が、ひめゆりの塔の展示を「歴史の書き換え」などと発言し、抗議や批判の声があがったが?▼
・沖縄戦の大本営は机上で作戦を立てて、現場のことを見ようとしなかった。
それと近い感覚なのかもしれない。
県内の資料館を訪ねると、体験者たちが苦しみながら絞り出した証言に触れることができるのに見ようとしない。
・琉球諸島で「台湾有事」を想定した急速な軍国化が進んでいる。
「軍隊は住民を守らない」という沖縄の住民目線の歴史観は邪悪な「異音」なのかもしれない。
<いいえ、けっして「異音」ではありません。 沖縄の現実をみない政治家が「異常」なのです!>
・戦後80年の節目と言われるが「戦後」という区切りでものを考えられない重たい感覚がある。
沖縄の人々が感じている軍事化に巻き込まれる危機感を本土の政治家の多くは理解していない。
<全くその通りだと思います、今の政治家は「自分のことしか考えていない!」と思います!
ですから私は以前から「政治家抜きの太平洋戦争白書」の作成を訴えているのですが>
・・・ということで「戦後80年その4」および「たんぽぽへの戦後80年シリーズ」を終了します。
かなり難しい内容ばかりでしたので、上手に要約できていますでしょうか?
なお、頂いています新聞記事にはまだ「日韓国交正常化60年」「安保法制10年」と戦争に関する記事がありますので、ボチボチとアップしますネ!
(下の右は「琉球人形(無料イラストからお借りしました)」です)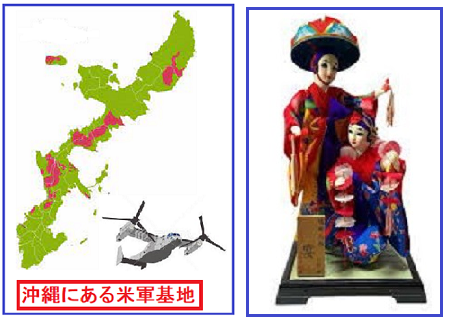
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-
コメント: 全0件








