サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: 沙羅さん
2009/07/13 15:52:18
icon
仏教伝来に関する記事
なんだか、このブログは、めるろーさんが最初、おたてになったのに、沙羅のブログにみえる、、、うぅぅんーーまあー、でも、めるろーさんは、開眼なさったって書
なんだか、このブログは、めるろーさんが
最初、おたてになったのに、
沙羅のブログにみえる、、、
うぅぅんーー
まあー、でも、めるろーさんは、開眼なさったって
書かれていたし、きっと、誤字乱文わたしの一人言ブログに見えるけど、、
空の中の存在として、なんらかの意味があるのかしら?
それより、
もう一度、、
おさらいしてみたいのです、、、
空海に唐へ向わせた大安寺の存在とその前身、百済大寺と、聖徳太子
秦氏なんですよねえーー
何が?ですか?、、って、、
大安寺のHPから抜粋
弘法大師空海の師として知られる勤操大徳は天平勝宝六年(754年)、大和国高市に生を受けました。
弘法大師の『勤操大徳影の讃序』によると、父は秦氏、母は嶋史氏で、初め子がないのを憂え、駕竜寺に詣でて一子が授かるよう祈ったところ、在る夜、明星が懐に入るという霊夢を見て懐妊したとされ、生まれてまもなく父とは死別。母の手一つで養育されたようです。
若き日の空海を伴い和泉の槙尾山に赴いて、出家させた剃髪の師といわれ、また虚空蔵菩薩求聞持法を授けた人物と言われてきました。さらには空海が入唐することができたのも、勤操の力によるところが大きかったと言われます。
弘法大師空海にとって勤操大徳はその生涯において大きな影響をあたえた一人といえましょう。
天長四年(827年)勤操大徳は西寺北院で遷化され、僧正位を追贈されました。
大安寺は、聖徳太子が平群郡額田部に熊凝道場を創建したことに始まります。やがて百済大寺、高市大寺、大官大寺と名と所を変え、平城京に移って大安寺となりました。この間の事情を『三代実録』元慶四年(880年)冬十月の条には次のように記します。
「昔日、聖徳太子平群郡熊凝道場を創建す。飛鳥の岡本天皇、十市郡百済川辺に遷し建て、封三百戸を施入し、号して百済大寺と曰う。子部大神、寺の近側にあり、怨を含んで屡々堂塔を焼く。天武天皇、高市郡の夜部村に遷し立て、号して高市大官寺といい、封七百戸を施入す。和銅元年平城に遷都し、聖武天皇詔を下して律師道慈に預け、平城に遷し造らしめ、大安寺と号す」
天平十九年(747年)に作成された「大安寺伽藍縁起并流記資財帳」(重要文化財・文化庁蔵)には、そもそも百済大寺の造営は、聖徳太子の遺言によるものであったとされております。
舒明天皇がまだ田村皇子と呼ばれた頃、聖徳太子の病が重くなった為、推古天皇は皇子を見舞いに遣わしました。太子は、自らが熊凝村に建てた精舎を、御世御世の天皇のために大寺となし永く三宝を伝えてほしいと皇子に遺言されました。太子の付嘱をうけて皇子は舒明天皇となった時、百済川の畔に熊凝精舎を移し建て百済大寺とされました。
これは九重の塔を持つ当時最大の大規模な伽藍であったとされます。ところが舒明天皇の時代には完成を見なかったようで、造立工事はその後、皇后の皇極天皇に引き継がれました。これには当時最盛期にあった蘇我氏はまったく関与していないようであり、太子の遺志を承けて天皇家が威信をかけて造営した最初の官立寺院であったといえます
百済大寺は今日までその所在がはっきりせず、広陵町の百済寺が比定されてもおりました。しかし数年前に桜井市にある吉備池から巨大な寺跡が発掘され,吉備池廃寺と名付けられました。その群を抜いた規模からこれが従来云われてきた幻の大寺、百済大寺に違いないと考えられています。
、海外の渡来僧も多く、東大寺大仏開眼の大導師をつとめたインド僧菩提僊那(ボダイセンナ)、呪願師をした唐の道(どうせん) 、さらに盛儀に華を添えたのは、林邑楽を披露した林邑僧(ベトナム)の仏哲でした。共に大安寺に居住し、生涯を日本で過ごした人たちです。
前後しますが、聖武天皇は伝戒の師(授戒の導師となる高僧)を求め、大安寺の普照(ふしょう)と興福寺の栄叡(ようえい)が唐に遣わされました。天平五年(733年)四月、二人は遣唐船で難波津を出航して長安に達し、先の道(どうせん)、菩提僊那、仏哲等に渡日を要請。その来朝がかないました。さらに十年、明師を求め、ついに楊州の大明寺に鑑真を訪ねます。その招請に応えて鑑真和上は自らの渡日を決意されたと云います。
鑑真和上の渡航は困難を極め、五度の失敗、六度目にしてようやく日本に到達することになります。その間十二年が経過し、鑑真和上は視力を失い、栄叡は病を得て亡くなってしまいました。一人普照が和上一行二十五名と共に歓喜の帰還を果たしたのでした。
和上は天平勝宝六年春、大仏殿に戒壇を設け、聖武・孝謙天皇をはじめ、衆僧・文武百官など四百余人に戒を授けました。鑑真和上の来朝は授戒という仏教の根幹に寄与するところが大きく、それだけに大安寺僧普照の功績を忘れることはできません。
なるほど、、なるほど、、ここで怪談じゃない、戒壇院が関係してくるんですね。
いやーぁ、、
面白いですねえ、、めるろーさぁーん、、、、
http://www.daianji.or.jp/03-reki.html-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 4
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

from: 沙羅さん
2009/07/14 16:08:53
icon
「Re:Re:Re:仏教伝来に関する記事」めるろ〜さん>>不思議なのは皇子が即位してから、百済大寺の造営に着手するのは10年以後なんですよね?>>>>
-
-
from: めるろ〜001さん
2009/07/30 11:34:38
icon
マニカナで、
>沙羅ちゃんマニカナで、「不二」の意味を間違えて使っている人がいますが、<二つに分けられない>という意味です。空海では、胎蔵界と金剛界の不二の思想とい
>沙羅ちゃん
マニカナで、「不二」の意味を間違えて使っている人がいますが、
<二つに分けられない>という意味です。
空海では、胎蔵界と金剛界の不二の思想といいます。
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト

-




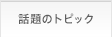




from: 沙羅さん
2009/08/09 03:16:05
icon
「Re:Re:Re:Re:仏教伝来に関する記事」さてさて、ダヴィンチもいいけど、たまに般若心経の玄奘三蔵の事でも書こうかなあー、、、ルンルンなんだか、